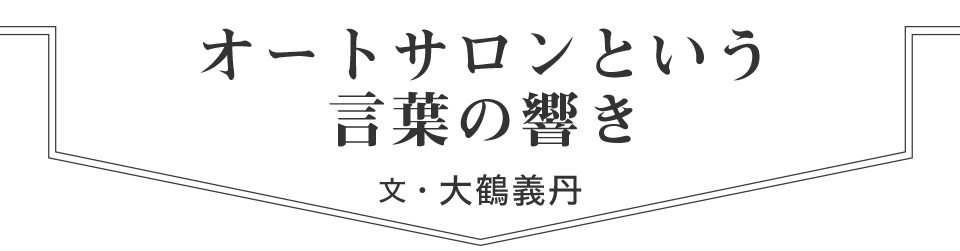今の50代以上のクルマ、バイク好きは、漫画や映画から何かしらの影響を受けていると言っても過言ではない。
いわばサブカルチャーと共に生きて来た世代であり、その文化をメインカルチャーに押し上げた立役者でもある。
自分たち世代にとってクルマやバイクのアインデンティーともいえるサブカルチャーについて振り返ってみたい。

「2023東京オートサロン」に初詣してきた。報道では3日間合計の来場者数は18万人近いという。今回は大手カスタムパーツメーカーがこぞって、新型Zのカスタムデモ車を用意していた。
オートサロンは、クルマの“カスタムモーターショー”として名を馳せ、いわばサブカルチャーとして発展して来た。しかしここ数年でオートサロンは、メインカルチャーである本家「東京モーターショー」を差し置いて、自動車メーカーの新車発表が行われることが多い。今年は海外展開に意欲を燃やす中国の電気自動車メーカー「BYD」が初めてブースを構えた。海外から訪れるインフルエンサーなどが、ライブ配信を行うことも珍しくない。また、クルマのことなどどうでもいいような、「色気目当て」の来場者が多いのも特徴だ。事実上、世界が認める“日本最大の自動車モーターショー”となり、今ではすっかりメインカルチャーとなってしまった。
昔話は好きじゃない。自分が二十歳くらいの頃、昔乗っていたクルマやバイクなどを自慢してくるオジサンが大嫌いだった。しかし気がつくとそのオジサンより今の自分の方が年上になっていた。だが、それでも自分が見てきたリアルは語らなければならない。昔話ではなく史実としてだ。
私が初めてオートサロンへ行ったときのイメージは、今の幕張メッセに充満しているような、ショータイム的な明るいモノではなかった。照明も薄暗く、決して“公の存在”ではなかった。私が初めて足を踏み入れたのは、バブル全盛の平成元年。オートサロンは「東京エキサイティングカーショー」と言われて「晴海会場」で行われていた。「東京オートサロン」に名称を変更したのは1987年の第5回からだったと記憶している。当時は毎年のようにターボ化された国産スポーツカーが登場していた時代だ。それまでは一部のマニアだけで構成されていた「改造車」に、バブルで金の使い道に困った悪いオトナたちが参入し始めた。当時の会場に満ちていた空気感というのは、隆盛を極めていたチューニング業界そのものだった。ルールなき群雄割拠のターボチューンによる大馬力主義が全てだった。各チューニングショップがブースを出しては、うちのクルマは「OPTION」誌の最高速アタックで何キロ出したなど、手書きポップがひしめいていた。とにかく大馬力を出したクルマが一番偉いという分かり易いルールだ。公認改造車という言葉も生まれてはいたが、メーカーが眉をめるような改造車がまだまだ生きていた時代だった。その2年後に、私も自分が所有していた改造車を、某チューニングショップのデモ車として晴海会場に展示することになった。そして、その数年後に、私はクルマを改造することを一切やめた。

クルマの改造というのは、ロマンで語るのは簡単だが、ある意味で罪深い側面がある。その魅力に魅せられた者の、お金も時間も、家庭生活も奪っていく魔力に満ちている。今の若い人たちには想像もできないだろうが、そこまで自分を追い込んでもクルマを改造するような若者が多かった。
「何のための500馬力」 自分たちでもその情熱の理由が分かっていなかった。だが多くの仲間が、借金をしてまでクルマの改造に情熱を注いでいた。またそのお金も、エンジンブローによって一瞬で霧散する。大メーカーが作った高性能なエンジンを、素人に毛の生えたような連中が適当にいじって出力を何倍にもするのだから壊れて当たり前だ。二十代前半は、クルマについて色々なことを知り、同時に深く傷ついた数年間だった。また、その渦のなかで、どこかに消えてしまった仲間もいる。
全ては、今は昔。音と光で演出された華やかな「幕張会場」の中を見回しながら、懐かしい「晴海会場」のことを思い出した。もう忘れてしまおうと思うのだが、「オートサロン」という言葉の響きには、どうしても打ち消せない痛みのようなものがある。