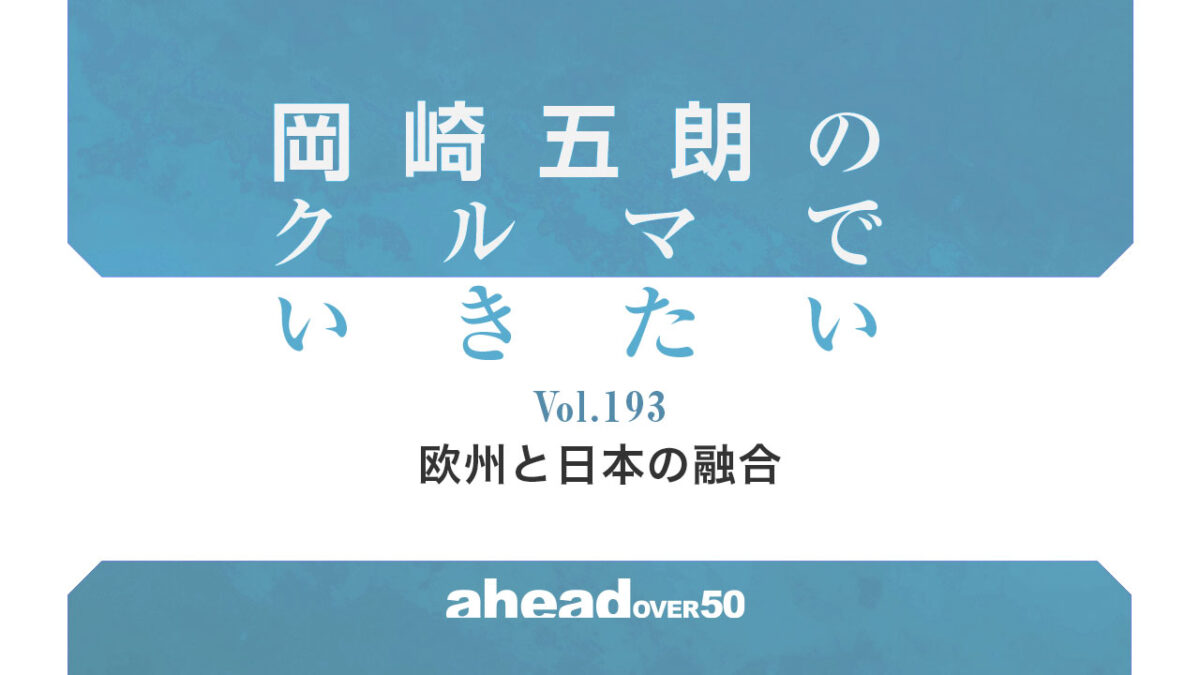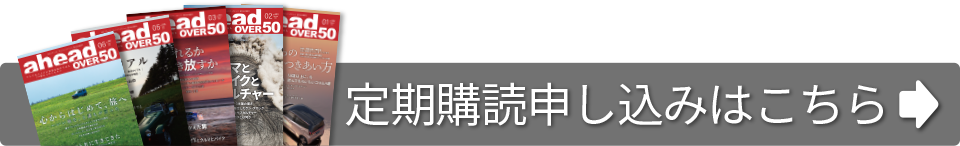ステランティスの会長ジョン・エルカンが「欧州にも日本の軽自動車のような小型で安価な車両を開発する必要がある」と語った。
名門アニエリ家の末裔である彼の言葉は、単なる市場論ではなく、安全基準や規制のエスカレーションに対する異議申し立てでもある。
もちろん安全性は重要だ。だが欧州では、年々強化される基準がコンパクトカーの存立そのものを脅かしつつある。安価な移動手段が消えれば、環境にも社会にも逆行する結果となる。安全安全と唱え続けていたら、ある日気付くと街を歩く人たちがみんなアメフトの防具を着けていた…そんな笑えない将来は果たして健全なのだろうか?
当然、日本の軽をそのまま受け入れるほど彼らはお人好しではない。やるとしても独自の規格を作ってくるはずだ。しかし、1ミリ・1グラム・1円にこだわる日本的合理性はきっと貢献できるだろう。全長3.4m、排気量660ccという厳格な制約のなかで、衝突安全、コスト、パッケージを極限まで最適化した軽規格車には、「知恵の器」たり得るポテンシャルが備わっている。コンパクトカーが消えていく欧州に対し、日本の“制約の中の知恵”が、新しい可能性を示すことになるかもしれない。
思い起こすのはBMWが2011年に発表したコンセプトカー「ロケットマン」だ。年々大型化するMINIのなかにあって、ロケットマンの価値はその圧倒的なコンパクトさだった。だが、ロケットマンの市販化は叶わなかった。理由は明快だ。超小型プラットフォームを新たに開発する必要があるが、投資の回収見込みが付かなかったからだ。
そこにこそ日本の軽が果たすべき可能性がある。スープラがZ4のエンジンとプラットフォームを使ったように、ダイハツがDNGAプラットフォームを提供し、MINIが磨き込めばきっと素晴らしいクルマになる。あるいはシトロエン2CV、あるいはフィアット500でもいい。欧州はこれまで最高に魅力的な国民車をつくってきた。そんな文化に日本が貢献できるなら、こんな素敵なことはない。エルカン会長の発言を聞いて、そんな妄想をしてみた。

Goro Okazaki