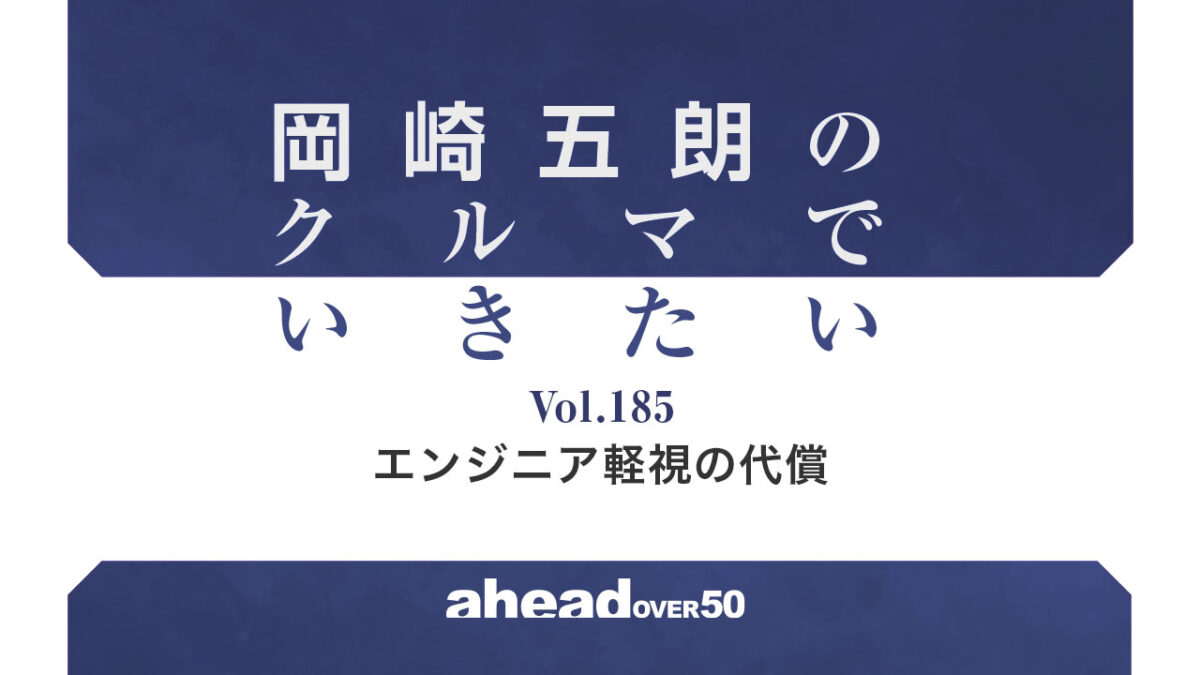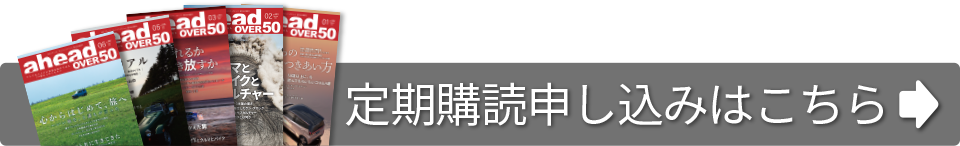日産の業績が急激に悪化している。
’24年4月〜9月期の決算は売上高こそ前年同期比1.3%減の5兆9,842億円を保ったが、営業利益は90.2%減と大幅ダウン。この数字が意味するのは、大幅値引きをしなければ売れない不人気車が大半を占めてるということだ。コロナ後の半導体不足で売り手市場だったときは値引きゼロでも売れていたが、メーカー各社の供給が復活してくると途端に値引き頼みになってしまった。ランクルやアルファード、レクサスLXなど、高価格帯のクルマにいまだ長いウェイティングリストができているトヨタとは対照的である。
中国での苦戦、北米市場へのハイブリッド投入の遅れ、アジア向けとして立ち上げたダットサンブランドの失敗など直接的な原因はいくつがあるが、重要なのはなぜそうなったかだ。煎じ詰めれば、経営陣のクルマに対する熱量が低すぎる。日産には超優秀なエンジニアがたくさんいる。GT-RやZを生みだした彼らの実力はピカイチだ。しかし、そういう人材を傍流と決めつけ、出世するのはカネ勘定が得意な人たちというのが昔からの日産のやり方だった。実際、車両開発責任者を経て役員になった例はほとんどない。それどころか、スカイラインの開発責任者になったら次は関連会社に出向、というのがお約束だった。エンジニアはビジネスを知らないからクルマでもつくらせておけばいい。それを利用して金儲けをするのが経営陣の役割であり、それを担うわれわれこそが日産の中心なのだ、といった雰囲気なのだ。当然、経営はクルマよりもカネ勘定が中心となり、いいクルマをつくった社員より、コストをより多く削減した社員が重用されるようになる。
こんな体制が長く続けば魅力的な商品が少なくなるのは当然の成り行きだ。ちなみにトヨタは豊田章男会長の「もっといいクルマをつくろう。その結果として利益は後から付いてくる」という経営方針の下、佐藤社長と中島副社長という車両開発責任者経験組が舵取りをしている。いまの日産に求められているのは、客が欲しがるクルマをつくるという基本に立ち返ること。実力はあるのだから、必ずできるはずだ。

Goro Okazaki