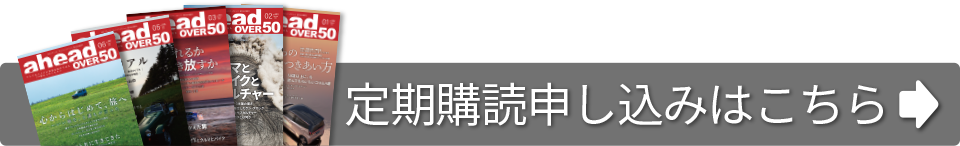国際的なイベントであり、世界3大モーターショーの一角を成してきた「東京モーターショー」が、変革の時を迎えている。
2023年は、名称が「ジャパンモビリティショー」に改められ、発信の舞台を東京からジャパンへ、その枠組みをモーターからモビリティ全般へと拡大。自動車メーカーによる自動車ファンのためのスペースが大きく押し広げられることになった。果たして、そこからなにが見えてくるのか。自動車とそれを取り巻く産業はどうなっていくのか。そしてなにより、ユーザーになにがもたらされようとしているのか。本誌では今後、『僕たちは、これからクルマとどう向き合っていけばいいのか』というテーマの元、多角的にクルマを語っていく。その第一弾として、モータージャーナリストの岡崎五朗氏と本誌プロデューサー近藤正純ロバートの対談、そして自動車経済評論家である池田直渡氏が見た「ジャパンモビリティショー」をお届けしたい。
自動車大改革時代の幕開け
対談 岡崎五朗 VS 近藤正純ロバート
まとめ・伊丹孝裕
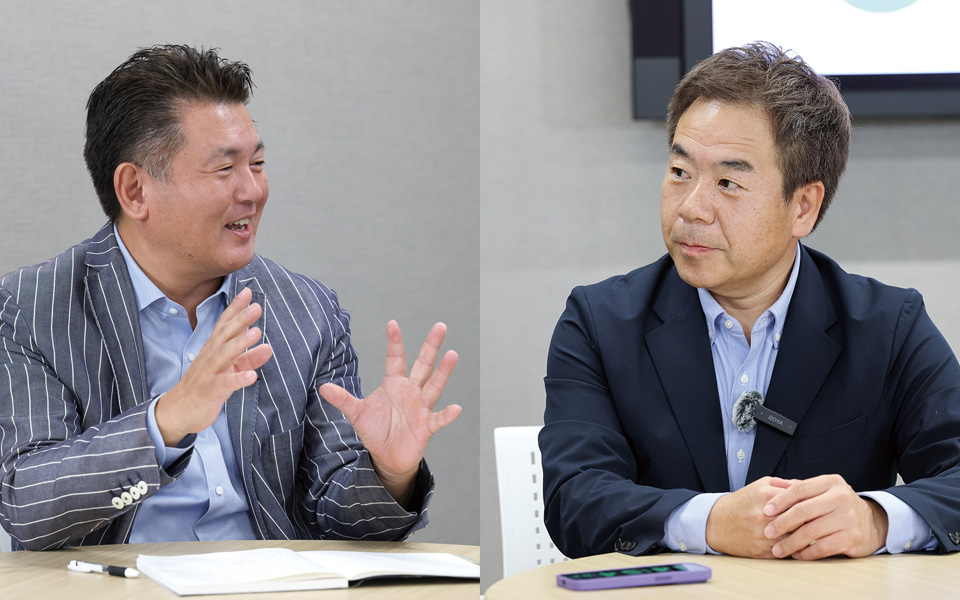
クルマは100年以上も変化してこなかった
近藤正純ロバート(以下、近藤)現在の自動車業界は、しばしば「100年に一度の変革期」だと言われている。それが意味するところを取っ掛かりにして、今回は話を進めていきたい。
岡崎五朗(以下、岡崎)今を変革期とするなら、以前はどうだったか。まずはそこなんだけど、ごく簡単に言えば、自動車メーカーもユーザーもいわゆる「良いクルマ」を求めていた。その指標のひとつが、よく走って、よく曲がって、よく止まることだから、速度無制限のアウトバーンを背景に持つドイツブランドが最高というロジックが成り立っていたんだよ。
近藤モータリゼーションが芽吹いて以来、そうした動的な性能に多くの人が価値を見出してきたのは確かだね。昔、ある自動車メーカーの副社長が言っていたんだけど、「クルマは100年以上もビジネスモデルを変えることなく続いてきた稀有な産業である」と。クルマの中にドライバーが座り、走らせて曲げて止めるのが基本的なスタイルでここまで何も変わってきてない。パソコンの処理スピードやメモリー容量がとてつもない勢いで進化しているのと違って、クルマは人間が操作する以上、生理的にも心理的にも限界がある。だからアウトバーンを200㎞/hで走れるようになっても、いきなり400㎞/hにはならない。スペックは少しずつ向上してきたとはいえ、広義でのイノベーションはなかったということになる。
岡崎確かにそう。自動車産業は、そもそも参入障壁が高い。エンジンひとつとっても、その構造は極めて複雑で、しかも人命にも直接関わるため、技術や知見を持たないメーカーがおいそれとは入ってこられなかった。ところが、近年はパワーユニットの代替をバッテリーが担うようになり、異なる分野から新しいプレイヤーが続々と参入してきた。ドラスティックな変化が生まれつつある。
近藤シンプルに内燃機関を楽しみたいという気持ちはあるし、筑波のラップタイムにも価値はあるのかもしれない。でも、いつまでもそこに留まってもいられないと思うんだ。

「CASE」を受け入れて活用していく
岡崎クルマの在り方が変化する中、「CASE」という言葉が象徴的に用いられている。これは、「Connected」、「Autonomous」、「Shared」、「Electric」の頭文字からなる造語なんだけど、従来はさっきロバートが言ったように、クルマと、その中にいる人というミニマムな関係性の中に収まっていた。しかしCASEの概念では、常に外部と、もしくは誰かとつながり、自ら運転する必要がなくなり、所有より利用するというスタイルが増えて、あらゆるコンポーネントの電動化が進んでいくことになる。
近藤五朗さんは、それに対してどう考えてるの?
岡崎CASEで示されている4つ方向性は、もちろん無視できるものではなく、どんなクルマにも少なからず盛り込まれていく要素だと思う。ただし、変革をリードする絶対的なものかといわれると、それは上っ面でしかない。メディア側に立つ者として大切なのは、様々な情報を短絡的に右から左へ流すのではなく、その読み解き方をきちんと提示することじゃないかな。

IT企業のソフトウェアとクルマは切り離せない
近藤クルマという存在は環境にも政治にも影響を及ぼし、ありとあらゆるソフトウェアが複雑に絡み合って成り立ってるからね。ハードウェアとしての機能や評価は大切にしながらも社会全体、もっと言えば地球全体の規模の中でどうあるべきなのかを語っていかなければならない時代にきてる。
岡崎僕がクルマメディアに携わるようになった理由がまさにそれ。もちろん、ニューモデルに試乗して、そのハンドリングや出力特性を語るのは大切な仕事だけど、クルマそのものに留まらず、その立ち位置や背景を通して見えてくるものがあるんじゃないか。そういう考えに至ったことが大きい。
近藤たとえば?
岡崎60年代から70年代のアメ車って、それはきらびやかで派手で、華やかさの象徴だったでしょ? なのに、ベトナム戦争が泥沼化するにしたがって、国力も人々のマインドも低下し、その落ち込みがクルマの出来やデザインに如実に表れた。日本で言えば、GT-R、セルシオ、ロードスター、NSXといったモデルが一堂に会した’89年の東京モーターショーと、それ以降の違いがそう。つまり、クルマは良くも悪くも世相を映す商品であり、だからこそ、語るに足る価値や社会的意義があるってこと。
近藤なるほど。’89年に話題になったクルマで言えば、見ても乗ってもその魅力が分かりやすかった。それに対して近年は、GAFA(グーグル/アップル/フェイスブック/アマゾンを筆頭とする情報技術の象徴)のようなIT企業が自動車業界へ参入してくるようになり、乗り心地の良さとか、シートアレンジの豊富さとはまったく異なる方向の快適性や利便性がもたらされるようになった。しかも、それらすべての要素がシームレスに繋がっているため、単純に切り分けられない。パソコンやスマホを選ぶ時、CPUもメモリも一定以上の水準にあるのは当たり前で、重視されるのはその先の広がり。クルマもその領域に入ってきたよね。

日本をクルマで元気にしていきたい
岡崎少し前までは、ディーラーでクルマを買い、そこでメンテナンスして、車検を受けて……と、バリューチェーンのサイクルが見える範囲の中で完結していた。今はそこにアプリやサブスク等の外部サービスが加わり、自動車メーカーはその分野を牽引するIT産業とバランスを図り、時に闘う必要がある。そんな中でどうやって生き残り、リードしていくのか。メディアは、そういうところにも目を向けていないとどんどん乗り遅れていく。
近藤メディアもユーザーも、その多くはハードウェアを優先しがちだけど、一方でいくつかの自動車メーカーは、すでにCASEを強化するための人材や組織作りを進めている。これまでの考え方やしがらみを取り払ったアイデアを積極的に支援しようとしていて、その一端が今回のジャパンモビリティショーでも見られたはず。未来に向けた、新しい局面に立ち会えたことが嬉しくもある。
岡崎僕がこういう場でなにか言ったり、書いたりする時、その下地には、日本をもっと元気にしたい、元気になって欲しいという願いがある。これはもちろん、外国のモノをけなして国産を持ち上げるような話じゃない。自動車は日本の基幹産業であり、その動向は少なからず日々の生活に影響を及ぼす。残さなきゃいけないし、残すべき砦だから家電産業のような没落は避けたいんだよね。日本のメディアに軸足を置く者として、そのためにどうコミットしていくか。自分の言葉や文字には、少なからずそういう思いを込めていて、ともすればフェアじゃないと受け取られかねないけれど、日本人としてそういう視点は忘れたくない。
近藤書き手としてのスタンスや、メディアとしての姿勢を持っていることは大切だと思う。確固たる考えもなく、むやみに欧米を偏重する人も多いから。

日本はCO2排出量の削減が世界一進んでいる
岡崎実際、「世界は進んでいるのに日本は遅れている」という論調をテレビや新聞で毎日のように目にする。つい先日も「日本にはEVがあまり走っていない。海外から来た旅行者の目には意識が低い国に見えているだろう。だからこの国は恥ずかしい」という主旨の記事を読んだ。これはとんでもない誤解で、日本はこの20年の間にCO2の排出量を23%も削減している。主要国の中ではダントツの成果を上げていて、北米やドイツは逆に増えているくらい。なぜそれを実現できたのかといえば、普通のガソリン車じゃなく、ハイブリット車や軽自動車を選ぶユーザーの意識だったり、それらを魅力ある商品に仕立ててきたメーカーの技術と努力があったから。それを単にイメージだけで「恥ずかしい」とはなんだ、と。百歩譲って、ユーザーが口にするならまだしも、ファクトとデータを元に、正しく伝えるべきメディアが間違ったことを語っているのだからこの問題の根は深い。
EVの二元論は不要
近藤CO2削減に対するソリューションは、EVだけではない。ただし、政治的にも規制的にもEV化は進めざるを得ないため、それに取り組んだ上で、ガソリンを活かす方法や新しいモビリティの可能性を提示する技術力と発想力が求められる。
岡崎その通り。世の中の論調として、いつの間にかEVか、そうじゃないかっていう二元論になってしまっていることが大きな問題。環境のためにはEVも重要なファクターだけど、他にもいくつかの選択肢がある。ただ、それをきちんと説明するには広く情報を集める必要があるし、膨大な時間と労力を伴うから、つい多くのメディアがキャッチーで楽な方向へ逃げてしまう。
近藤自動車メーカーに新しい人材が集まりつつあるのと同様、メディア業界にも広い視野を持つ人材が必要だよ。ハンドリングを言語化できる能力と同様に、IT、経済、環境、世界情勢も含めてクルマを語れる見識を持たないと、表層的なことしか発信できない。
岡崎先月号の僕の連載ページでも書いたけど、テスラが推し進めている「ギガキャストこそ最高」みたいな流れもそう。部品点数も工数もコストも劇的に削減できる製造革命みたいな物言いが独り歩きした背景には、出された情報をそのまま鵜呑みにしてしまうメディアの責任が大きい。真実に辿り着く能力や努力がどんどん軽んじられ、なにもわからず、誰もなにか変だな、と立ち止まらないまま、物事が進んでいく現状に危機感を持っている。
大手メーカーとスタートアップ企業が組む時代
近藤新興メーカーや、異端的な人材からもたらされる新しいスタイルにも学ぶべきところがあるのも確か。そこに日本のメーカーが長年培ってきたノウハウが組み合わさり、それをきちんと伝えられる場があれば、日本は再び強くなれる。そういう意味で注目すべきは、今回のジャパンモビリティショーにおいて、多くのスタートアップ企業が集った点。彼らと大手メーカーが出会う機会が設けられ、そこで生まれる新たな息吹を、一般来場者も感じられる。そんなユニークな取り組みが必要なんだよ。
岡崎同感。日本の企業は、特にその規模が大きくなればなるほど、外部の人や若い人に冷たくしがちなところがある。「俺たちの方が優秀。俺たちの方がよくわかっている」という上からの意識がどうしても滲み出てしまって、結果的に可能性をつぶしてしまうことが多い。既述の通り、日本の自動車メーカーにがんばって欲しいと願っているのは事実だけど、テスラとトヨタが出会った時に、トヨタ側の対応がもう少し柔軟だったなら、今と色々な状況が違っていたかもしれない。そういう経緯を見てきたからこそ、ジャパンモビリティショーにおける主要なコンテンツのひとつ『スタートアップフューチャーファクトリー』の成功が大事なんだ。

ジャパンモビリティショーの果たす役割
近藤この企画は、若いスタートアップ企業と既存のモビリティ産業を結びつける場として、モビリティショーを活用してもらおう、というもの。賞金総額1200万円のピッチコンテスト(プレゼンテーション)が開催されたことも画期的で、スタートアップ側はもちろん、自動車メーカーやパーツメーカーからの期待が大きいと聞いてる。
岡崎ショーの概要を知れば知るほど、企業側は積極的に変わりつつあること、変わろうとしていることが分かる。我々メディア側もクルマをクルマ単体のみで評価するのではなく、あらゆる視点で捉えられるようにならないと。とっくにそういうタイミングにきてる。
近藤新しい視点を持つ人が、新しい機会を得て飛躍のチャンスを掴む、という意味でジャパンモビリティショーはひとつのケーススタディになっただろうし、メディアを運営する立場としても、大いにプラスになったものがある。次号では、『スタートアップフューチャーファクトリー』のプロデューサーを務めた橋本健彦さんにも加わってもらい、企画の狙いや展望、ピッチコンテストの詳細を聞いてみよう。
岡崎五朗/Goro Okazaki
1989年 青山学院大学理工学部機械工学科卒
1989年 モータージャーナリスト活動開始
2009年より 日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員
2009年より 日本自動車ジャーナリスト協会理事
2009年より ワールド・カー・アワード選考委員
近藤正純ロバート/Masazumi Robert Kondo
1988年 慶應義塾大学経済学部卒
1988年 日本興業銀行入行
1996年 米コーネル大学留学MBA取得
1998年 レゾナンス設立代表取締役就任 現任
2008年 日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員
2012年 日本カー・オブ・ザ・イヤー副実行委員長
2023年 日本カー・オブ・ザ・イヤー執行部
ahead TV 自動車大改革時代の幕開け 前編
ahead TV 自動車大改革時代の幕開け 後編

〜対談 岡崎五朗 vs 近藤正純ロバート
文・伊丹孝裕