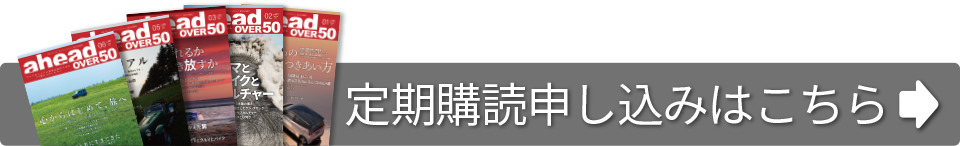若い頃は、歳をとったら演歌を聴くようになるのかと思っていたし、バイクを捨ててゴルフバッグを積んだクルマを走らせるかもしれないと考えたりもした。
しかしフタを開けてみればまったくそんな気配はない。演歌を聴きたいとは思わず、歪んだギターを鳴らすロックが今も変わらず好きだ。クルマを所有こそしているがあくまで道具だし、ゴルフもやらない。走らせて楽しいのは、バイクのままだ。
これは何も私だけの話ではなく、プロアマ問わずロックやパンクのミュージシャンや多くのバイク乗りにとっても同じだろう。歳をとって創る音楽が丸くなっても、ロックから演歌に転向したミュージシャンを私は知らない。レースから引退する、乗る頻度が減る、スピードを求めなくなり、ゆったりツーリングするようにはなっても、バイクに乗り続ける。変化はあるにせよ、本質は変わらない。
趣味嗜好は加齢で変わるのではなく、時代や世代と繋がっているのだろう。
ロックとバイクに興味を惹かれたのは、否応なく組み込まれる社会のシステムに馴染めず、かといって逃げることもできない憤りをいくらか和らげてくれる、あるいはだからといって諦めるのではなく多少なりとも立ち向かおうと思わせてくれるものだったからだ。既成品の服のサイズやデザインがピタリと合うように社会のシステムに馴染める気質だったなら、ロックもバイクも要らない。おそらく社会の大半はそういう人たちで回っている。自分を取り囲む環境に疑問や不満を感じることなく、心をまっすぐに育めた人たちがシステムをうまく利用し、都合のいいようにシステムを作り変えていく。
残念ながらそういう人間になれなかった落ちこぼれや、はみ出し者には、ロックやバイクが必要だ。たとえていうなら、それはメガネや羅針盤だ。まともな人間が作った狂気の世界を往くには、正気を保つために何かが要るのだ。
ロックともバイクとも関係ないが、純文学を主軸としていた小説家・吉行淳之介がエッセイでこんなことを書いている。彼はある時期、今でいうストーカーに悩まされていた。妄想が綴られた手紙が連日届き、さらに自宅へ押しかけてくる。その影響もあって彼は鬱になるのだが、あるとき担当編集者にこんなことを言われる。
「純文学なんて普通の人には必要ないし読まないんだから、ファンなんて多かれ少なかれどこかおかしい人なんですよ」
そう言われて「それも一理ある」と苦笑ひとつで終わったというエピソードなのだが、ロックやバイクも似たようなものである。
もしロックやバイクが恋のような一時の熱病だったら、どちらもすでに飽きているはずだ。しかし欠けた自分の機能を補うものだから、たとえ飽きたとしても忘れたり捨てたりはできない。ただひたすら自分の一部として、死ぬまでそれを必要とするのだ。ひとことで言えば三つ子の魂百までということなのだが、いつまでも子供のままで大人になれないろくでなしともいえる。もっといえばロックもバイクも必要としない世界こそが理想的な社会なのだろう。だがそれは、絵に描いた餅にすぎない。
しかし何事も時代のふるいにかけられてからが真価ともいえる。どちらも今は、まともな人間たちの玩具になりつつある。そこまでしてロックやバイクが生き長らえるくらいなら、いっそ消え去ったほうがましだ。
さて、昨年12月発行の本誌229号で、左膝を粉砕骨折したため本格的なバイク鑑賞家になるかもしれないと書いた。負傷から10ヶ月ほどが経ち、日帰りツーリングできるほどに回復した。頻度が減っているのはあいかわらずだが、もう少しバイクに乗り続けられそうだ。バイク鑑賞家になるのもなかなかむずかしい。