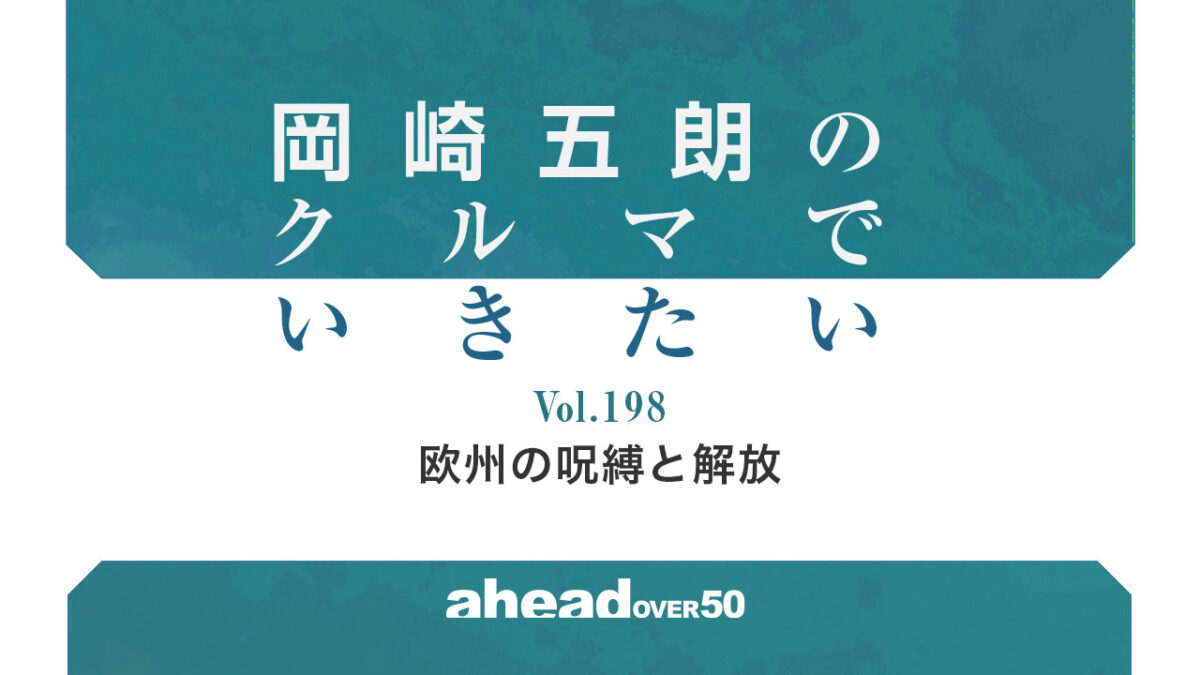来日していたVWブランドCEO、トーマス・シェーファー氏にインタビューする機会を得た。
ゴルフ7が登場した2013年、僕はVW幹部に「なぜ大衆車なのにここまで質感を高めるのか」と尋ねたことがある。彼は笑ってこう答えた。「喉が渇いた時、人は水ではなく美味しいビールを飲みたいだろう?」 そう、VWは大衆車メーカーであると同時に、生命維持に必要な「水」ではなく、人生を潤す「美味しいビール」を提供し続けてきた企業だった。
だが、ディース前CEOの時代、この哲学は大きく後退した。「EVこそ正義」という脱炭素の理想論に取り憑かれ、急進的なEVシフトとコストカットを断行したからだ。さらにテスラを無批判に模倣し、物理スイッチを廃してタッチパネルに集約するデジタル化も進めた。結果、内装は安っぽくなり、長年のファンは離れ、ブランドの基盤である「信頼」は損なわれた。
シェーファー氏が掲げる新戦略「ラブ・ブランド」は、この行き過ぎた意識高い系路線への反省に他ならない。彼は「100メートル先から見てもVWと分かるデザイン」や物理スイッチの復活を明言し、イデオロギーや株価やESGスコアではなく、再び「顧客」の方を向き始めた。インタビューで印象的だったのは、彼が「未来はEV」と言いつつも、「未来の到来時期は地域によって異なる」というきわめて現実的な考えを述べていたことだ。例えば南米では、バイオ燃料を活用したエンジン車が当面残り続けると認めているのだ。
しかし、VWが直面する現実は厳しい。シェーファー氏は「それでも新規のエンジン開発は行わない」と断言した。トヨタがマルチパスウェイで全方位の技術を磨くのに対し、VWは資金的な制約から、既存技術の延命とEVへの集中を選ばざるを得ないという。脱炭素という「高コストな理想」と、生き残りという「経済の現実」。この挟撃のなかで、シェーファー氏はかつての「美味しいビール」の味を取り戻せるのか。それは単なる一企業の再建劇ではない。欧州自動車産業が、自ら招いた呪縛から解き放たれるかどうかの試金石なのである。

Goro Okazaki