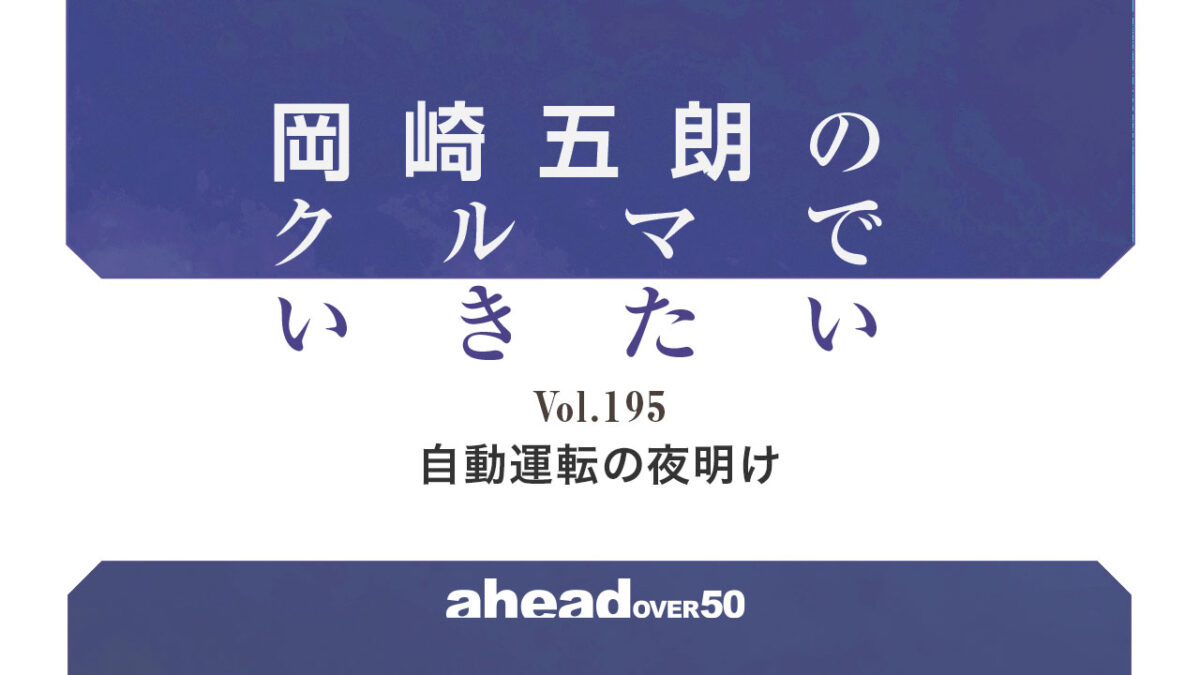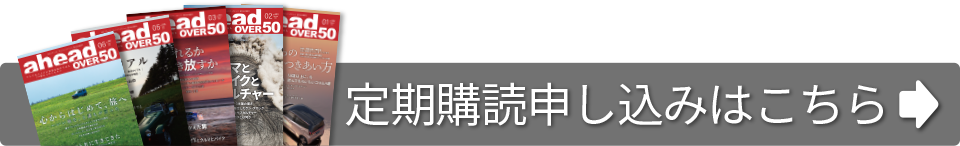日産が開発中の次世代プロパイロットを都内で試した。
助手席での試乗だったが、予想以上の完成度に驚いた。右折信号のない交差点、人や自転車でごった返す道、駐車中の車両回避のための車線変更などを、まるで意思があるかのように最適な「間合い」を計り、ベテランドライバーのような滑らかさで走っていく。これはもう、従来の運転支援の延長線上の技術ではない。
その秘密は「エンドツーエンドAI」にある。英国ウェイブ・テクノロジー社と組んで開発した新技術だ。7年前の試作車は12個のソナー、12個のカメラ、9個のミリ波レーダー、高価な6個のレーザースキャナー(LiDAR)と、まさにセンサーの塊で、なおかつ高精度地図も必須だったが、今回は11台のカメラと少数のセンサーのみ。AIが人間のように「見て、考えて、判断する」から、少ないセンサーで、ルールベースでは不可能な複雑さへの対応や、しなやかな動きができるのだ。
この進化を最も象徴するのが、開発責任者である飯嶋氏の変心だろう。彼は長年AI主導の自動運転に懐疑的だった。僕自身、カメラとAIだけで自動運転は可能だというビジョンを語るイーロン・マスク氏よりも、日産の現実的な視点を信頼してきた。その彼が「去年考えが変わった。AIはすごい」と断言したのだ。これは重い。とはいえ、テスラと違い、1台のLiDARと5台のミリ波レーダーは残している。カメラだけでは夜間の高速道路で障害物の発見が遅れるからだ。このあたりは、すべてをAI任せにしない現実的な安全思想である。
次世代プロパイロットは2027年にまずレベル2として世に出る予定だが、そのポテンシャルは計り知れない。飯嶋氏は言う。「平均的な運転者ではなく、集中したベテラン運転手を超える安全性が証明されれば、以前は夢物語だったレベル3やレベル4への進化も十分期待できます」。長年この分野を取材してきたが、初めて本当の意味での自動運転の夜明けを見た気がする。どんなクルマに、どれぐらいの価格で搭載されるかはまだ発表されていない。しかし、今回の試乗で感じたのは、机上の空論ではない、確かな未来がそこにあることだった。

Goro Okazaki