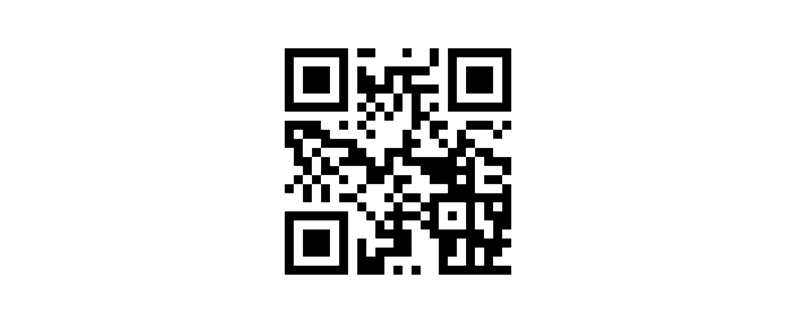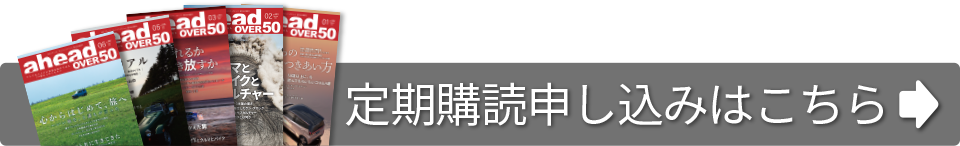トヨタはメセナ活動の一環としてエイブルアート・カンパニー*とともに、障害のある人たちの芸術活動を応援している。
なぜ自動車メーカーがこのような取り組みをしているのか。そこには、根底でクルマ作りにもつながる深い理由があった。
心が動くクルマとは何か
岡崎トヨタはエイブルアートを応援しているわけですが、僕はそれが純粋な障害者支援とは一線を画した活動なのでは? と踏んでるんです。もちろん確信はありません。でも、デザイナー、ブランド戦略、社会貢献活動を経てトヨタ博物館のシニアキュレーター、という異色のキャリアをお持ちの布垣さんであれば、きっと僕のモヤモヤを解決してくれるだろうなと思い話を聞きに来ました。
布垣そうきましたか(笑)。
岡崎aheadは自動車雑誌なので、単なる企業メセナ活動の紹介にはしたくないというのもあります。で、クルマ視点で考えたとき、最近のクルマはつまらなくなったという人が増えてきたのは議論すべき大きな問題だと思っています。
布垣僕も開発の現場にいたとき、若者のクルマ離れという言葉をよく耳にしました。でもある日、初代セリカに乗っている23歳の若者に出会った。驚いて「なんでそんな昔のクルマに乗ってるの?」と聞いたら、「トヨタ博物館で見て、いいなと思って調べたら売ってたから買いました」って。まるで古着を買う感覚でクラシックカーを選んでいたんです。この彼の価値観って、時代に取り残されたはずの“何か”で、偶然じゃないと感じました。
岡崎分かります。たとえば昔の2CVとか、ビートル、mini、パンダなんて、ベーシックカーなのに趣味性も高くて今でも愛され続けている。それはきっと、あの頃のクルマは作り手が自分の理想をストレートに形にできたからなんじゃないか。でも今は、排ガスや安全性などの様々な規制をクリアすることに作り手がエネルギーの大半を割く必要があって、クルマというキャンバスに自由に想いを書き加える余地がなくなってきている。余地というか、システムといったほうがいいかもしれませんが。
布垣僕らが一生懸命“新しいもの”を作っているつもりでも、それが若い人の目には新しくは見えてない、あるいは響いていない可能性がある。たしかにそこは問題意識を持つ必要がありますね。
例えばスバル360は実際に博物館で見てみると、「えっ、こんなに小さかったっけ?」と思います。でもかつてはその小さい空間に家族ぎゅうぎゅうに笑顔で乗っていたのを思い出すと幸福感はスペックでは語れません。今のクルマの方が性能も広さも圧倒的に上ですけど、あの頃のクルマにあった“幸せ”は、もしかしたら今より豊かだったのかもしれない。
岡崎スバル360といえば、知人にEVにコンバートして乗ってる人がいるんです。僕なんかはクラシックカーの魅力はエンジン含めての魅力だと思っているので、最初は「そんなもったいないことを…」と思ったんです。でも突っ込んで話を聞いたら、「これ、おじいちゃんの形見なんですが、冬はエンジンが一発でかからなくて手に余ることがあって。でもこの形が好きだからEVに変えてでも乗りたいんですよね」と。つまり、クルマを機械としてだけじゃなく、デザインや記憶、思い入れの対象として見ている。その視点はすごく大事だと思います。
布垣ですね。世の中が右肩上がりを前提にしていた時代は終わり、今は「本当の幸せってなんだろうか」と問い直す転換点にある気がします。

エイブルアートとは?
(*)エイブルアート・カンパニー

感性が文化をつくる時代へ
岡崎ということでようやく本題に入っていきますが、こうして今のクルマの在り方を見ていると、エイブルアートの持っている自由さ、多様性がすごく魅力的に思えてきます。
布垣僕が一番驚いたのは「たんぽぽの家アートセンターHANA(※)」で見たエイブルアートの作品でした。施設で障害のある人が描いたって聞くと、「かわいそうだから支援しよう」という視点が出てしまいがちだけど、実際には「すごいアイデア」とか「ユニークすぎる発想」がそこにあった。僕らが会社で“良いアイデアを出そう”って頑張ってるのとまったく同じレベル、むしろそれ以上の自由さがあったんです。




岡崎彼らは、実は僕らには思いつかないものを思いつけるんですよね。そういう人たちを支える仕組みがあるから社会全体が成り立ってる。企業の中も同じで、突出した才能だけじゃなくて、それを支える人、繋ぐ人、全部が必要。ただ、トヨタが文化活動を支援できるのも、ちゃんと利益を出しているからというのがあると思うんです。同時に、「良いものを選ばれるように作らないと、利益も出ない」っていう循環の中にいる。選ばれる価値とはスペックや価格だけじゃない。
布垣そう、まさに鶏と卵。良いものを作らないと選ばれない。でも選ばれるってことは、ただ便利ってだけじゃなく、心が動くものじゃないといけない。手を焼いても「こっちのほうが好き」と思わせる何かが必要なんです。それは、「幸せの量産」という豊田章男の言葉にも通じます。前述の初代セリカだって、いつ壊れるか分からない。でも「これがいい」と心が動いたから選んだ。それが本当の幸せだと思うんです。
岡崎今の911空冷ポルシェが高騰してる理由もそこにある。機能やスペックの話じゃなくて、「そこにしかない魅力」があるんです。今のクルマはそういう魅力を失っていないか、僕らは真剣に考えないといけないんですよね。
布垣メーカーとして、お客様の声を聞くのは当然ですけど、それだけじゃだめだと思ってます。「心を豊かにする何か」に気づいてもらえるかどうか、そこが勝負なんじゃないかと思うんですよ。

岡崎そうなると、もうスペックの時代じゃなくて、「心が動いたかどうか」でクルマが選ばれる時代になっているってことですね。
布垣トヨタがエイブルアートを応援しているのも、「感性」や「心の動き」に価値があると分かっているからなんです。「障害のある人が描いたから」ではなく、「何が伝わってきたか」が大事。でもそこはなかなか伝わりにくい部分なので、目利きが必要な時代なんですよね。
岡崎結局、良いものが分かる目がないと文化は育たない。高級寿司が分かるからこそ、回転寿司の良さにも気づける。なんでも「安けりゃいい」では文化は育たない。

布垣多くの人は、モナリザのような有名なアート作品だけを「見る価値があるもの」と捉えがちです。でも忘れてはいけないのは、モナリザの価値を見抜き、それを世に広めた人の存在なんです。描いたのはイタリア人ですが、有名にしたのはフランス人。その“目利き”が文化をつくるんだと思います。エイブルアートのTシャツやコップを見て「クルマと関係ない」と思う人もいるかもしれません。でも、そうした作品の本質を感じ取れる人でなければ、良いクルマの本質も見抜けない。作り手の思いを汲み取る感性があるからこそ、クルマの魅力も見えてくるはずです。
岡崎僕らメディアも、その“目利き”としての役割をもっと自覚しないといけないですね。「これは手抜きしてるな」って思ったら、ちゃんと指摘しなきゃいけないし、責任重大です。
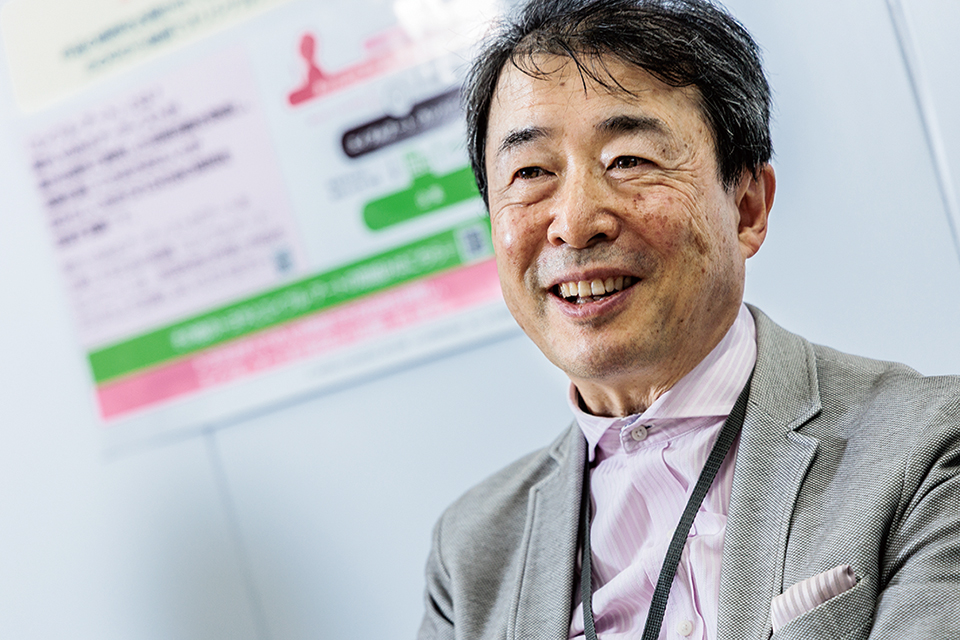
布垣直昭/ぬのがきなおあき
富士モータースポーツミュージアム 館長
1982年入社以来デザイン部門に携わる。
2006年部長、ブランド戦略や先行開発を担当。
2014年トヨタ博物館館長、社会貢献部長としてメセナ活動やエイブルアートも支援。
2022年、自ら監修した富士モータースポーツミュージアム館長に。
2025年、シニア・キュレーターに就任。歴史文化の専門家としてクルマ文化醸成に尽力。
岡崎五朗/Goro Okazaki
華音/Kanon
“暮らしの中の何気ない選択が新たな文化の目になる”ー華音

対談を通して強く感じたのは、「心を豊かにするものに関心を向けること」の大切さだ。効率やスペックばかりが重視される時代だからこそ、自分の“心が動く”瞬間を大切にする感性が、これからの文化を育てていく鍵になるのではないかと思う。
特に海外で暮らしていると、自分の感性を信じて選ぶ人が多いと感じる。それは特別に自信があるというよりも、「自分は何が好きか」「どう感じたか」という主語で日々の選択をすることに慣れているからだ。たとえば、洋服を選ぶときでも、「今の自分に似合うかどうか」や「自分らしいかどうか」を自然に基準にしている。
一方で日本では、「周りにどう思われるか」「浮かないか」といった“他者の目”が判断基準になりやすい。これはおもてなしの心や、和を重んじる文化に根ざした美徳でもあるが、その一方で、自分の感性に素直になることが難しくなってしまう場面も少なくない。
だからこそ今、自分の内なる声に耳を傾け、「これはいい」「これが好き」と感じたものを信じて選ぶ力が、より重要になってきているのではないだろうか。誰かが決めた“正解”ではなく、自分自身の感覚を基準にする。その積み重ねが、「良いものを見極める目」を育て、結果的に文化そのものを豊かにしていく。
そして少しずつ、日本でもその変化が生まれ始めているように感じる。クルマやアート、暮らしの中の何気ない選択を通じて、「心が動いたかどうか」に価値を見出す人が増えてきている。その感覚に気づき、言葉にし、共有していくことが、新たな文化の芽になる。
「感性」とは、ただ何かを選ぶ力ではなく、「自分を信じる力」だと思う。私もまた、その感性を信じて、自分の言葉で「これが好きだ」と言える人間でありたい。