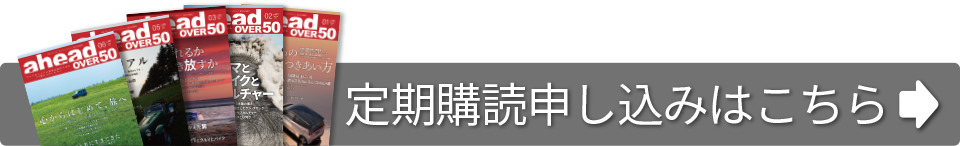この1年間は、過去の膨大な記事の中から、今再び届けたいテーマを見つめ直す1年だった。
それは翻って、「aheadとは何か」と作り手である私たち自身が問い返される作業でもあった。
今月号で、本誌は創刊20周年を迎える。
「aheadとは何か」
元編集長・若林葉子の連載コラム「ひこうき雲を追いかけて」(’08~’20年)を振り返ることで、その答えを紐解いていきたい。

「若林さん、今、ドライブという言葉は、若い人のあいだでは、もう死語なんだそうですよ」。少し前に、ある自動車メーカーの方が、いかにも困ったことだというふうに、そう話された。
事の真偽は分からないが、コストの掛かるドライブ記事というものが世の中に少なくなったのは、需要が減ったことの表れではあるだろう。
私は、といえば、ひょんなことから『ahead』に関わることになり、ペーパードライバーから脱して、ようやく3年半が過ぎた。最初の半年はエンジンをかけるたびに心臓が口から飛び出しそうになるくらい緊張し、編集部に入ると同時に「えいっ」と購入したクルマは一度は道路に停車中のトラックにミラーをぶつけ、一度は車庫入れでリアをぶつけて修理した。
それでも取材へ、撮影へと、どんどん出掛けて(ドライブと言えるかどうかは別として)、ようやく「あー、ワタシってけっこうクルマが好きなんだな」と実感できるまでになった。
クルマに乗るようになって、それまでと一番違ったことは、自分でも意外だったが、空が近くなったことである。多分、スピードが速い分、視界を遠く、広く取るからだろう。
数年前のある日、湾岸道路の大井埠頭近くを走っていて、頭上を行く大きな飛行機のおなかと遭遇した。
高く晴れた空を背景に下降していく飛行機と、高速で疾走していくクルマの、一瞬の邂逅。
「キャー! すごーい」。興奮のあまり、その時私は年甲斐もなく黄色い声をあげ、運転していた同僚に呆れられた。でも呆れられたっていいのである。
用賀インターから乗った徹夜明けの東名高速で見た、カーブの先の富士山。夜のベイブリッジ下、357号線から見える煙るような幻想的な夜景。それから、橋のように道路上に架かった飛行場をゆっくりと歩いていく飛行機も、「おなか」と同じくらい、私をうれしくさせてくれる。
東京にいながら、大きな空と広い風景がいつも身近にある。それは紛れもなく「ドライブ」の力なのだと思う。

aheadにときおり登場してもらっていた竹田津敏信さんが亡くなった。バイクに興味のない読者の方には遠い話かも知れないが、私たち編集部にとっては大切な人だったので、やはり書かせていただく。
編集長の神尾は15年以上にわたる家族ぐるみの付き合いであったが、神尾を通して私が知りあったのはわずか4年ほど前のこと。学年は違うが同い年で、すぐ仲良くなった。編集部の飲み会にも都合の許す限り来てくれた。いつだったかは、怪我のあとの松葉杖の不自由な足で駅からの道をえっちらおっちら歩いてきたっけ。
タケの口癖は「へっ」だった。正確には「へ」と「は」の間くらいの「へっ」。いつもどこか反抗的で、かっこつけしいで、何かにいら立っていることも多かった。タケのその“何か”が少しだけ私には分かる気がした。
私もタケも1971年生まれ。スーパーカー世代にも乗り遅れ、バイクブームにも間に合わず、バブル絶頂期には、ほんの少しでその恩恵にありつけなかった。しかしそれらはいつも視界の端にちらほらと見え隠れしていて、無視することは難しいという微妙な世代。私たちの周りには“ど真ん中”世代がたくさんいて、スーパーカーと言えば盛り上がり、バイクブームと言えば自分の蛮勇に事欠かない。バイクの世界で“ど真ん中”でなかったタケが、老舗バイク雑誌の編集長を務めるということがどんなに大変だったか。ど真ん中世代は憧れでもあり、尊敬する先輩でもあり、目の上のたんこぶでもあったはずだ。
海外の試乗会で誰も乗ったことのないバイクに乗り、サーキットで走りを極め、経験を増やして自信はついても、どこか肩肘張っていなければならなかった。タケの「へっ」は彼の複雑な心境の表われだったに違いない。タケのしんどさを通して、初めて私は、自分の世代について考えるとっかかりを得た。
昨年、編集部で開いた飲み会で、私のモンゴルラリーのオンボード映像を流した時、すっぴんの私の顔を見て、「だめだよっ、眉毛は描かなきゃ、オトコは傷付くっ!」。 酔っ払いのタケはそう繰り返して、皆で大笑いした。その夜、正体不明になったタケを、神尾と一緒に藤沢の自宅へ運んで行った。空が白み始めているというのに、酔っ払いは、コーヒーを飲んで行けと言う。仕方なく家へあがったら、少しして顔を出した奥さんの早苗さんは、きれいに眉を描いていた。タケは愛されてるなと思った。早苗さんのような奥さんと一緒になれたタケは幸せなヤツだと思う。良かったね、タケ。



私が初めてaheadに原稿を書いたのは2004年8月号(Vol.21)だった。その後、2005年1月に正式に編集部に入り、2020年6月号(Vol.211)で辞めるまでの15年半の間、実に190冊のaheadの制作に携わったことになる。私も含めたくさんの人間が編集部に入っては去って行ったが、その中で最も長いというだけでなく、最も深くaheadに関わった者の一人と言って差し支えないだろう。
編集部に入った2005年当時、まだ日本経済は緩やかながら成長基調にあり、世の中の空気も明るかった、と思う。何よりahead自体に勢いがあった。代官山の編集部はアパレルショップかインテリアショップのような凝った造りで、メンバーも何だかみんなおしゃれで華やかだった。
その後、2009年夏に編集部を代官山から現在の横浜市港北区の大倉山に移すことになる。2008年に世の中を騒がせたリーマンショックの影響が無かったとは言えないが、それよりも「自分たちは何屋なのか」という問題意識が編集部の移転につながったように思う。Car&Motorcycle Magazineである以上、広報車の出入りは避けられなかったから、借り出した広報車を常にコインパーキングに停めておくという代官山の環境は何かと不便が多かった。大倉山の編集部には4台はクルマが停められるし、その気になれば、社屋の中にクルマを入れてしまうこともできる。移転と同時にKTCの立派な工具棚も揃えたから、ちょっとしたメンテナンスもできるようになった。
雑誌の読者というものは編集者以上にその世界に精通していることが多い。そういう人たちに何かを伝えようとするならば、編集者は読者に負けないくらいの熱意が必要とされる。「お前は何屋だ」というのが5代目編集長・神尾の口癖で、ただ編集部に座って考えていても企画は生まれない、と時間のある時にはよくクルマやバイクであちこち出掛けたものだった。
思い起こしてみると、「誰かが何かを経験する」ということに対して、編集部にはとてもポジティブな雰囲気があった。私がラリーレイドに深く関わるきっかけとなったのは、当時、aheadの表紙を撮影していた桐島ローランドがモンゴル・ラリーに出場すると聞いて、「面白そう」と何気なく呟いた一言で、それを聞いた初代編集長・高畑の「行ってくれば」が、その後の長きにわたる私のラリーチャレンジの始まりとなった。
そういう経緯でプレス参加したその年の夏から4年後、2009年に今度は選手としてモンゴルに行くことになるのだが、会社からは経済的援助こそなかったものの、快く10日間の休みをもらえたし、個人的に少なくない金額を餞別として手渡してくれたのも社長の近藤だった。後に2015年のダカール・ラリーにナビとして参戦することになったときには1ヵ月、日本を留守にしなくてはならず、そのときも近藤は「若林さん、すごいね」と行って送り出してくれた。留守中、実務を代わってくれたのは神尾を始めとする編集部のメンバーであり、私はなんと恵まれていたことだろう。
本当にずぶの素人だったから、私のラリーレイドへのチャレンジは華々しいことなどひとつもなく、ただ惨めなことや情けないことばかりだった。それでも、その惨めさや情けなさを取り繕うことなく全て文章に残した。それが編集者の私がチャレンジすることの意味だと思っていた。
そうやって経験を積んでいったのはもちろん私だけではない。編集部のみんながそれぞれのやり方でクルマやバイクと関わってきた。現在は大阪で2人の子の育児をしながら、リモートワークでaheadの編集をサポートしている村上が「aheadは仕事というより修行でした。2度と同じことはできないけど、あの時代だからできたし、ある時代を懸命に駆け抜けた実感があります」と言うが、本当にそのとおりだ。
毎号送り出されてきたaheadの記事(企画)にもそれは自ずと反映されていたはずで、そういったことを意気に感じてくれた人たち――執筆者、カメラマン、デザイナーを始めとするスタッフ、クライアント、そして読者の方たち――が、一緒になってaheadを応援してくれたのだと思う。
この1年ほど、aheadに掲載されているアーカイブスを読んできたが、昔の記事も色褪せることなく、当時とはまた違った発見や感慨があることに驚いている。クルマやバイクを通して表現された記事の一つ一つが、懸命に生きる人々の生の実相に触れているからではないだろうか。Webほどには情報性が求められない紙媒体であるからこそ可能だった、と言えるかもしれない。
aheadから離れて2年半が過ぎようとしている。その間に私は結婚し、1匹の猫を迎え、ベランダでガーデニングなるものをささやかに楽しみながら、フリーランスとして仕事を続けている。ずいぶんと生活のペースは変わったが、相変わらず、そろそろ10万キロに届こうとするシトロエンDS3のシフトノブを動かしながらあちこち出掛けては、愛車のある暮らしを楽しんでいる。
Yoko Wakabayashi
「ひこうき雲を追いかけて~aheadとは何か 若林葉子」の続きは本誌で