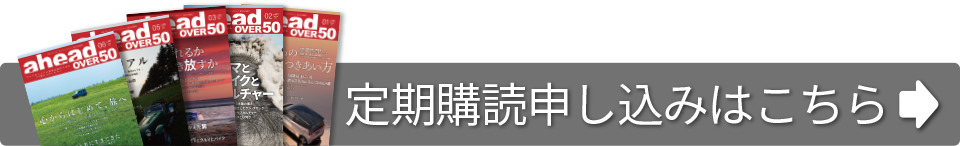レゾンデートルとは、フランスの哲学用語だ。
直訳すると「存在理由」や「存在意義」といった言葉になる。しかしそれは、周囲が認める存在価値という意味ではない。自己完結した自分自身の価値観や生き甲斐のことを指す。
世間から存在価値を認められようとするのか、自らの存在意義を貫いて生きようとするのか。
それを決めることができるのは自分自身でしかない。


オートバイに乗る人は不思議だ。
クルマと違い、生活に必要なものではなく、背負うリスクも他の趣味に比べて極端に大きい。
なのに、オートバイに乗る人は趣味の域を超えてオートバイにのめり込む。
オートバイに興味がない人からみると、その価値に意味を見出すことは難しい。
「どうして、オートバイなんかに乗る」
常識では理解し難いその答に少しでも近づいてみたい。
「スナフキンみたいな人」。
それが浅川邦夫さんを初めて見かけたときの印象だった。4年ほど前のことで、確かHYODの走行会だったと記憶している。場所は富士スピードウェイ。編集長の神尾(当時)と立ち話をしているのをぼんやりと遠目に見ていた。決して強いオーラがあるとか、目立つとかいうのではないけれど、わさわさとした空気の中で、物静かでたんたんとした様子がかえってその存在を強くしているといったふうで、その時、何者であるかも知らないその人は私の中に強く印象付けられた。
その後も何度かお見かけする機会はあったものの、きちんと挨拶を交わしたのは’12年の鈴鹿8耐、これもまたHYODのホスピタリティでのことだった。その頃には、浅川邦夫さんという人がどういう人かについていくらかは知るようになっていた。
浅川さんは、かの有名な「ヨシムラ」の全盛時代に、4サイクルエンジンの神様と謳われたポップヨシムラ(故 吉村秀雄)のもとで、メカニック兼テストライダーとして、レース活動を支えたひとりだ。
「いやぁ、あの頃はめちゃくちゃだったよ。ヨシムラの親父さんはさ、寝なくたって、食べなくったって、気合があれば何だってできるだろうって、そういう人。あの時代の人はみんなそうだったけど、全てが根性論だったね」と本人も振り返るように、バリバリの戦闘集団の最前線で、人生の一時代を、寝ても覚めてもただひたすらに、生活のすべてをオートバイレースに捧げたのである。
そうであるにも関わらず、浅川さんから、〝スナフキンのような〟という、どことなく孤独を愛する哲学者のような、そしてときに皆の導き手となるような印象を受けたのはなぜだろうか。
「オレはさ、別にオートバイ乗りが増えなくってもいいと思ってるんだ」。
浅川さんは常々そう考えているという。それにはもちろん訳があって、常に転倒の恐れがあるオートバイは、いい加減に取り組むと危険なのである。だからこそ乗る人は安全な装具を付け、安全な場所で練習しなくてはいけない。世の中にいい加減なオートバイ乗りが増えてもらっては困るという想いが浅川さんにはあるのだ。
浅川さんの主宰する「アサカワスピード」のホームページの言葉からもそのことが分かる。
―もっと真剣に、もっと深く 知ってほしい
そうすれば上手くもなって、
安全に、速くもなって
長くバイクを楽しめる
アサカワスピードは、
そのお手伝いをします
「要はいかに力を抜くかだよ」。
小学生の頃には、運送業を営んでいた実家の敷地内でカブを乗り回し、大学生の頃にはレースに出場し、テストライダーとしても数限りなくサーキットを駆け抜け、58歳になる現在(’12年当時)も常にオートバイで走り続けている浅川さんの言葉だ。シンプルと言えばこれ以上シンプルな答はないのだが、浅川さんがこの境地に辿り着いたのはここ数年のことだという。
きっかけは50歳になる年に挑んだ全日本ロードレース選手権だった。「50歳を目前にして、何かやり残したことはないかって考えたんだ。20歳の頃、もともとは全日本チャンピオンになりたくてレースを始めたんだよ。でもその後、すぐにヨシムラに入ることになって。だから、もう一度やってみようってね」。
やると決めたら何でも徹底的にやる浅川さんは、生活の指標のすべてを全日本選手権に向けた。そのひとつが体を鍛えること。「まずはそのリズムに乗りたかった」と、毎朝5時に起きてトレーニングに励んだ。九州、岡山、鈴鹿、仙台と、レースのある前の週にはレースが行われるサーキットで練習し、いったん仕事場の横浜に戻ってきて、翌週のレース日程に合わせて再びサーキットへ行く。
国際A級ライダーでもある浅川さんは、ヨシムラでテストライダーをつとめていた頃は、辻本 聡(’85、’86年のTT-F1チャンピオン)らと比べても遜色のない走りができていると自分の走りに多少の自信があった。しかし、ふたを開けてみれば全戦で予選落ち。選んだオートバイの性能差が大きな理由だったが、長年のブランクをはじめ、原因がいろいろあるとはいうもののショックは大きかった。「あとコンマ何秒ってところで全戦予選落ち。日曜日の決勝はいつもスタンドでレースを観ていたよ」。
ある瞬間は前走者に付いていけても、その先のコーナーで曲がりきれない。無理してついていって転倒したりコースアウトしたりして、自己嫌悪に陥った。
そしてそれまでより、いっそう真剣にライディングについて考えるようになったという。どんなオートバイであれ、タイヤがグリップしようがしまいが、速いライダーには、力みが感じられない。同じスピードで走っていたら、バイクの旋回力を妨げない人が上手い人だと気付く。
「それで自分のコーナリングを分析したんだ。膝を擦るほどバイクを寝かしてるのに、体はアウト側を向いていてチカラが入ってる。その状態でアクセルを開けるから早くからタイヤが滑り出す、今見ると危うい乗り方になってるのに気付いた。曲がる方向に体が向くのが自然なのに、変な癖がついてたんだね。若い時は勢いだけで速く走れてたんだ。ブレーキングとかアクセルの開け方とか、これまで培ってきたものが大きく崩れたよ。それでまたひとつひとつを練習したんだ。長年培ってきた乗り方を変えるっていうのはすごく怖かったね。勇気がいるんだよ」。
そして辿り着いたのが、詰まるところ、「いかに力を抜くか」ということだった。


浅川さん自身、トレーニングで筋力を付けたけれど、それは逆効果だったと振り返る。「時速200キロというとんでもないスピードの中で無理にバイクを押さえつけたら、自分が飛んでっちゃう。だから変に押さえつけちゃダメ。押さえ込む筋力がある方がいいならムキムキマンが一番速いことになる。いかにバイクの動きに合わせて自然体で乗るかが重要なんだよ」。その考え方はオートバイの整備や日常生活にも及んでいる。
整備をしているときに、不自然な手の曲げ方をしていることに気付くと、なるべく自然な姿勢になるように立ち位置を変えてみる。座って誰かと話をしているときでも、肩に力が入っているのに気付くと、なるべく力を抜くようにしてみるなどだ。
確かに肩が痛いとか腰が痛いとか、日常的に誰もが感じる体の不具合は、不自然な姿勢が原因であることが多い。力を抜くことは力を入れることよりはるかに難しい。第一、力が入ってることにさえ気が付かない。気が付いた時は、すでにどこかが痛かったり凝ったりしているものだ。
「店の前の坂を下りて行くのを見ているだけで、その人の普段の乗り方やバイクがどんな整備をされているのかは、すぐに分かるよ」。
長年の経験を通じて辿り着いた答ではあるが、浅川さんがどのくらい真剣にずっとオートバイについて考え続けてきたかを知ることができる書物がある。
それは、神尾が18年前に浅川さんから譲り受けた『禅とオートバイ修理技術』(ロバート・M・パーシグ著、1990年4月10日発行)という本だ。この本を開くと、いくつもの箇所がマーカーで塗られている。浅川さんがバイクについて考え続けてきた長い道のりと真剣さが伝わってくる。
―「目標を意識せずにひたすら登っている人が、最も高いところにいる」
―「自分がどれだけ大きな人間かを誇示するために山に登ろうとすれば、それは九分九厘不可能である」
―「観察する物に評価を与えてはいけない。頭を空っぽにし、観察した事実から公平無私に推論を下していくのだ」
―「とにかくやってみよう…もしうまくいかなければ…何か別の方法を試してみよう」
―「行き詰まりは、何事においてもその本質を理解する上での先達である。だから決して避けてはならない」
―「発見してみれば、何であれ単純なものだ。だがそれはすでに知ってしまったから、そう言えるだけのことに過ぎない」
―「オートバイの修理をしようとするならば、何よりもそれ相当の覇気がなければならない。それが最も大切な道具なのだ」
―「求めるべきは心の落ち着きであって、単なるオートバイの修理ではない」
―「『退屈』も覇気の罠の一つである。(中略)退屈なときは、作業を中断してしまうに限る」
Etc…
浅川さんは、本を読んだだけで分かったような気になる人ではないはずだ。本で読んだことを自分のことに置き換えて、頭と手と体で、繰り返し試行錯誤してきたのだと思う。
別件の取材の途中、「トライアンフ横浜港北」のメカニックであり、浅川さんを尊敬しているという坂上裕史さんに、その理由を訊ねたところ、「数字の理詰めじゃないところ」という答が返ってきた。マニュアルの数字に囚われないで、ボルト一本を締めるにしても緩まずに折れない〝ちょうど良いトコロ〟を浅川さんは、経験から導き出しているのだという。


1999年の別冊モーターサイクリストの記事『the way to DAITONA』(浅川さんが1972年型トライアンフでデイトナに挑戦する姿を追った記事)の中で浅川さん自身、こう語っている。
「このトラをいじっていく上で注意したのは、ある一か所だけ精度を出すようなやり方をしないようにしたこと。一か所だけを100分の1ミリ単位で精度を出したら、それに組み合わされる部分も同じ精度を出せなきゃ意味がない。そうやっていくと(中略)全部の部品を造りなおさなきゃならなくなる。そんなの不可能でしょ。だからできるだけ精度を出すんだけど、全体のバランスを見てそこそこにしてやらないとね。この辺が勘どころといえば勘どころ」。
また神尾によると、「オートバイの調整の仕方が5段階あるとしたら、普通は予測を立て、2つほど試して大きく外れていなければ、どちらかを選んで終わりにする。でも浅川さんは、5段階の全てを試してみたい人。先入観を持たずにまずやってみて、これはダメだとはっきり分かってから次にいく根気強さがある。なのにその反面、『おまえあの部品を持ってないか』って深夜2時に家まで来た事もある。ただ待ってられないというのか、思い立ったらすぐに動き出す人でもある」。
以前、魂が宿ると言われたヨシムラのエンジンに興味を持った大学生が、吉村秀雄さんのところに取材に来たことがある。
「物に魂を込めるとはどういうことか教えてください」と。その時の吉村の親父さんの答はひとこと。「魂なんか宿るわけないだろ!」 浅川さんは言う。「そりゃそうだよね。やってるときはみんな魂込めよう、魂込めようなんて思ってやっちゃいない。もっと無心だよね。無心でやった結果として魂が宿ってるとしか思えないモノができるということはあってもね」。
考えることと、乗ること。理論と感覚。知識と知恵。真面目さとユーモア。慎重さと大胆さ。どちらか片方が欠けても、人は不自由だ。オートバイを通してその両方を、自分の中にバランスよく育ててきたことが、浅川さんという人の力であり魅力なのだと思う。

aheadに関わる以前の私にとって、オートバイに乗る人は遠い存在だった。偏見よりは憧れの方が少しだけ勝っていて、〝ナナハン〟という言葉の響きにもちょっと心が躍った。それでもオートバイと言えば、〝アウトローでスピード狂〟といった世間と同じ型通りのイメージしか持ってはいなかった。それなのに今、気が付けば、親しい人の多くがオートバイに乗っている。十人十色でいろいろなタイプの人がいるのは当然だが、意外だったのは、オートバイに乗る人は、乗っている時間と同じくらい、いやそれ以上に、オートバイについて考えたり整備したりしている時間が長いということだ。
考えたり整備したりする時間が乗っている時間よりも長いというのは、オートバイが構造上、エンジンやサスペンション、マフラーなど剥き出しの部分が多く、人が関与しやすいということでもあるだろう。だが、それ以上に、自立できない乗り物であることが大きいのではないだろうか。停まると自立できないし、転倒して怪我をするリスクもある。それがオートバイの宿命だ。
同時にオートバイは、極めてパーソナルな性格の乗り物でもある。製品としては完成していても、乗り手の体格や体重、技量のみならず、天候や気温、湿度に至るまで、さらには乗り手の性格までをも反映してしまう繊細な側面がある。最後には乗り手自身が責任を持って注意深く付き合うことでしか、オートバイとの良好な関係は保てない。
天気予報を気にするだけでなく、日に何度も空を見上げ、帰り着けば心から「あぁ良かった」と無事であることを実感する。日常の中で頭のどこかに生死を意識している、それがオートバイ乗りではないだろうか。
それゆえにオートバイに乗る人は、ライディングにも真面目に取り組むし、整備にも真剣にならざるを得ない。すべては安全に走りきるためであり、世間のイメージとはうらはらに、本物のオートバイ乗りには〝考える〟人が多いように思う。
浅川さんはそんな「考えるオートバイ乗り」であり、本物のオートバイ乗りの象徴のような人だった。
人生とは誰にとっても不確かなものだ。それでも、必ずどこかにより良い答、もっと確かな何かがあると信じて、人は手探りで進む。
だが、オートバイという相棒は、「良い」も「悪い」も一方通行ということはなく、感じようとすれば、その度にちゃんとフィードバックしてくれる。本物のオートバイ乗りは、リスクと引き換えに、退屈とは無縁の人生が送れるのだろう。オートバイに乗らない私にはそのことが素直にうらやましく思える。
「レゾンデートル ある者の存在する理由 archives」の続きは本誌で
2014年8月号 Vol.141
僕の中には浮谷東次郎がいる~加藤
2012年11月号 Vol.120
たかがオートバイ、されどオートバイ 若林葉子
2017年12月号 Vol.181
ミニは階級社会が生み出したパンクだった 吉田拓生