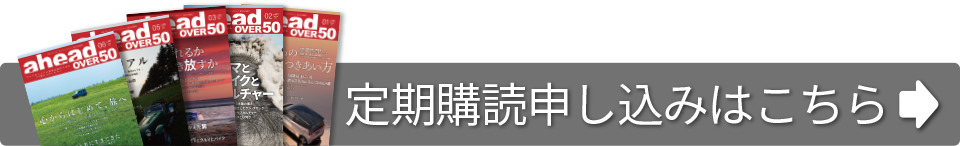60年代から70年代に電車や汽車を乗り継ぎ、北海道を旅する人達は改札を抜ける時に背中の荷物が邪魔になって横歩きになることから『かに族』と呼ばれていた。
80年代から90年代にかけては移動の手段はバイクが主流となり、その走り過ぎる音から『みつばち族』と呼ばれるようになった。
以前は世間から皮肉られるほど、北海道を旅する人が多く存在していた。それぞれの時代によって『北海道』に求めるものは違っていたのかも知れないが、共通しているのは日常から脱却するためだ。
仕事も生活も今の場所をいったん離れて外側から自分を眺めてみると見えてくるものがあるはず。
現実から切り離されると本来の自分が必ず目覚める。

心になにがしかの曇りを持っているとき、漂泊の旅先にはなぜか北の方角を選ぶことが多い。少なくとも自分はそうだった。
北海道へ旅立ったのは、大学3年の夏のことだ。旅の道具に選んだのは、カノジョ作りよりも夢中になっていたバイクだった。ただ、本当にバイクが好きだったのかというと明言できない。というのも人生の行く先が見えず、心はさまよっていたからだ。好きで学ぶことを決めた考古学にも夢中になれず、考古学で身を立てようという情熱など、すでに失っていた。どうするのか、この自分。何かを掴もうとして伸ばした手の先は、すでに霧の中にあって掴むべきものが見えなかった。唯一指先に触れたのがバイクに過ぎなかったのだ。
バイクで走っている時だけは、目の前の霧が薄らいでいくように思えた。その時だけは自分がおぼろげに見えた気がしていた。大学3年の夏の旅。時間はありあまるほどある。ただ金はなかったから小さなテントと駅舎やバス停の軒先を寝所としながら北海道中を回った。しかし観光地には興味がなかったので、その日の行き先を決めようにもアイデアが湧かない。地図を広げて思案するのは数日であきらめ、漠然と東西南北の、どこへ向かうかだけを決めてバイクを走らせた数ヶ月だった。
行き先が見えなかった大学生時代。北海道の旅から帰ってきても相変わらず漂泊者であることに変わりはなかった。北海道の旅では駅舎の屋根がわずかな安息の場だったが、東京に戻ってきてからは、それがアパートの屋根に変わったにすぎない。毎日の生活の先には、頼りなげな、か細い将来がわずかに見え隠れしているに過ぎなかった。
大学4年の、それも冬になって、ようやく編集プロダクションに入社することは決まったが、自分の将来が安定したとは思わなかった。なんせ、たった数名の小さな会社だ。大樹の下の庇護など感じることはできず、社会の雨風をしのげる程度の場所でしかないことは、入社直後に悟っていた。ただ、この編集プロダクションでは漂泊感を覚える暇もないほどがむしゃらに働いた。編集していたのはバイク雑誌。唯一、情熱を持って接することができるバイクの世界に関わることができて高揚した。五里霧中の毎日の中で、少しでも多くの表現を拾い出そうと作業に熱中した。結局この会社には、関わっていた雑誌が休刊するまで在籍することになった。
休刊、業務縮小…そんな波に抗しきれず、会社を辞し、別の編集プロダクションで雑誌作りに関わった。その後、わずかばかりの経験を頼りにフリーのライター兼編集者として独立、自力で泳いでもみた。幾度も波にもまれ、おぼれかけ、ようやく泳ぎ着いた岸辺が『ミニ』の専門誌の編集部だった。再就職して久しぶりに安定した収入を得ることができた。しかし嬉しかったのは、そんなことではなかった。仕事を通して接することになった『ミニ』が、バイクに匹敵するほど自分を熱中させてくれる存在だということに気づいたからだ。ここで『ミニ』の魅力を語ることは避けるが、自分の感性に共鳴する存在が『ミニ』だったのである。
編集部の方針で取材には必ず社用車の『ミニ』で出掛けた。それがどこであろうと。東北道をひた走り、青森まで突っ走ったこともあるし、1人で運転して高速道路のサービスエリアで仮眠をとりながら、20時間以上掛けて鹿児島まで行ったこともあった。またフェリーに『ミニ』を乗せ、北海道を走った回ったこともある。数回だけだったが、ジムカーナや『ミニ』のワンメイクレースにエントリーしたこともあった。
編集部の『ミニ』以外に自分自身の愛車としての『ミニ』を手に入れてからは、デイリーメンテナンス以外に、クルマをジャッキアップして、リジットラックをかませ、車両の下に潜って整備することまで覚えた。クルマのメカニズムというものに関してはまったく知識も技術も持たなかったのに自分の変容ぶりに驚いた。人間、変われば変わるものだ…他人事のように思えて、そんな自分に苦笑した。
好き、と素直に思える素材が身近にある。この『ミニ』というクルマの魅力をあますことなく伝えたい…。その気持ちは、編集者としての情熱をかき立てた。アイデアの糸を何十、何百とたぐり寄せ、次々と企画書に仕立て上げた。オーナーインタビューのページを任され、毎号さまざまな話を取材し、その数は積もりに積もって3,000人を超えていた。『ミニ』に浸りきり、それこそ寝ても醒めても 『ミニ』のことばかり考えていたのがこの時期だった。
『ミニ』とは、クルマというものに対して意識の変革をもたらしてくれたと同時に、編集者としての成長を促してくれたクルマだったと言っても過言ではない。『ミニ』との蜜月の中で、「自分は漂泊者」という思いは、いつしか心の底にしまわれ、気づくこともなくなっていた。
突然、編集部から離脱を余儀なくされたのは一昨年のことだった。それは自分自身の根っこが相変わらず漂泊者だったことを思い出させるには充分だった。編集部には関わり続けるいっぽう、ライター、あるいは編集者としての活路を他にも求めなくてはならない…。結局、またフリーランスに戻った自分がいたのである。暫くぶりのフリーの生活に、解放感とないまぜになった不安を感じていた。
これまでの
かつてもフリーランスとして編集者という仕事に携わっていたことはある。フリーの生活がどのようなことかも分かってはいた。ただ、40代になってからのフリーランスは、20代の頃のような自由さとは縁遠いものだった。当時とは違って妻がいる。息子どもも。とくに長男はもう中学生だ。そして、この不況。数え上げるどれもが不安や焦燥をあおるものばかりで、閉塞感に暗澹たる気持ちにさせられるばかりだった。かつて自分の先行きが見えないことを指して、「漂泊者」と表現したけど、そんな格好をつけている場合ではない。いわば、単なる「根無し草」ではないか…ふと、そんなことを考えて、なおさら閉塞感を深くしている自分がいた。
いま深く関わっている仕事(当時)を美化して言うわけではないけれど、雑誌タイトル名の『ahead』という言葉には、ずいぶんと勇気をもらった気がする。一歩、前へ踏み出そう。一歩、一歩、確実に踏み出せばいい。…霧の中に消え行く遠くの道のりに不安を抱くより、まず、明確に見える一歩先へ確実に歩を運ぶことが大切なんじゃないかと教えるものだった。一歩、一歩、足を大地にしっかりと着けて進む中で、必要であれば、自身を変える、チェンジさせる。
好きなバイクや『ミニ』にこじつけて言えば、高いギアを選んで一定速で走っていた人生を、適切なギアまでシフトダウンし、加速力を得るべき時期にいるんじゃないかと気付かされたのである。北海道へと向かうこの特集は、まさにそんなさなかの取材だった。
大学を卒業して編集者という職を得て以降、北海道には仕事で幾度も足を運んできた。ただ、それは到底〝旅〟などと言えるものではなく、ひたすら駆け足で、目的の仕事をこなしたらすぐに東京の編集部に引き返す慌ただしい〝出張〟でしかなかった。学生時代の北海道の旅のような、甘い感慨や人生の先行きへの淡い焦燥を感じる余裕はなかった。クルマやバイクを運転することはあっても、それは仕事のためであり、不安を振り払うようにアクセルを開けた学生時代のような旅は、そこにはなかった。
しかし、この特集の旅は、これまでの仕事とは異なり、さまざまなことを考えさせられる〝旅〟になった。それは、40代半ばにして人生の新たな局面を迎えた感傷や感慨、決意といったものがそう感じさせたのかもしれない。

取材車両の『ミニ』を貸し出してくれた「ガレージミニ・ノースランド」の代表が、エンジンキーを渡しながらこんな言葉を贈ってくれた。
「『ミニ』っていうクルマはな、大地を掴んで走るクルマなんだ。北海道の大地を楽しんでこい」。
古典的なFFの機構、大きな前輪荷重。ショートホイールベース、コンパクトなボディ。10インチというホイールサイズ…どれをとっても、『ミニ』は個性的なクルマだ。『ミニ』でしか体感しえないダイレクトな操縦感は、相変わらずドライビングを楽しませてくれる。
夢中で走っている時にふと気付いた。ただ、漂っていたわけじゃない。根を張るべき場所を求めていたら、いつの間にか積み上げるべきものは積み上げていたじゃないか。これまで感じていた霧がすっと晴れた。すでに家族もいる。もう漂泊者なんて言葉は使わなくていいな…。
相変わらず、『ミニ』はときにぽんぽんと跳ねながらも、しっかりと大地を掴みながら走っている。
「北海道、再び archives」の続きは本誌で
現実逃避のすすめ 桜間 潤
北海道、再び 春木久史
須藤英一の撮った夏 須藤英一
対峙を迫る風景 春木久史