“世界一過酷なレース”と称されるダカールラリー。その2015年大会に本誌・若林葉子が、HINO TEAM SUGAWARA 1号車のナビとして参戦した。
想像を超えるトラックの激しい揺れに、毎日のように車内で頭をぶつけ、4,500mを超える高地では高山病に悩まされながら奮闘した14日間。ダカールから戻ったばかりの若林に、自身もサハラ砂漠のラリーを走った経験のある、まるも亜希子さんが話を聞いた。
予想に反して、彼女はとても元気そうに見えた。世界一過酷なラリーを完走し、帰国した翌日で時差もあるはずなのに、そんなことも全く感じさせない。ただ、「ニットのカーディガンなんて久しぶりに着たわ」などと笑う言葉や表情から、闘いの場から無事に戻ることのできた安堵感が、じんわりと彼女を温めているように感じた。

若林さんは私にとって、ラリーの想い出を話し合える数少ない女性だ。年齢が近く、もともとクルマやレースにまったく興味がないのに、この世界に入ってしまい、なぜかラリーを目指してしまったという背景も似ている。私は’04年、’05年にサハラ砂漠を2500㎞走る女性だけの、通称「ガゼルラリー」に参戦し、命からがら完走した経験がある。若林さんは’09年にモンゴルラリーに初挑戦し、やはり苦難の連続を乗り越えながら完走。計4回の挑戦のうち、ナビゲーターとして参戦した2011年にはクラス優勝している。私は挑戦し続ける彼女の姿にいつも感銘を受けているし、そのための見えない努力や精神力に尊敬の念を抱いている。だから、昨年の秋に若林さんがダカールラリーに参戦するというニュースを聞いた時は、「ついにきたか!」と心が躍った。雑誌編集者という立場ゆえ、「なにかのタイアップ企画なんでしょ」と思った人もいたかもしれないが、これは紛れもなく、これまでの彼女の頑張りが認められ、お金でも媒体力でもない、ひとりのラリーストとして最高のオファーを受けたのだ。しかもチームは、ダカールラリーの連続出場記録を持つ菅原義正さん率いる日野チームスガワラという、伝統と実績あるワークス。これがどんなに凄いことなのか、一度でもダカールを夢見た人ならば、全身が震えるほどに実感できるはずだ。
とはいえ、参戦を決めるのは勇気のいる決断だったと振り返る。「モンゴルラリーで、確かに私はラリーという競技に魅せられたところはあるの。でも、その先に〝いつかはダカールラリー〟 という目標はなかった」との彼女の言葉に、私も共感を覚える。アマチュアの私たちにとって、ダカールラリーは憧れの存在でありながら、おいそれとは足を踏み入れられない「別格」の存在でもある。しかも今回のオファーは、若林さんがモンゴルラリーに初参戦した時から陰で見守り、さまざまなアドバイスや指導を行ってきた菅原義正さんの息子であり、同じく優秀なラリードライバーである菅原照仁さんが若林さんの実績と可能性を買って、チームの成績アップのために迎え入れたいと言ってくれた経緯がある。その期待に、果たして自分は応えられるのだろうか。そんなプレッシャーも彼女を悩ませたはず。でも、若林さんはついに、菅原義正さんがドライバーを務める日野レンジャー・1号車のナビゲーターとして、ダカールラリーへの扉を開いたのだ。

そこからスタートラインに立つまでの数ヵ月は、いったいどんな日々だったのだろう。「とにかくまずは国際C級ライセンスを取得しなければならなかったから、時間を見つけてはサーキットへ通ってた。なんとか条件を満たした時は、本当にホッとしたわ」と若林さん。たとえナビゲーターとしての参戦であっても、一定のドライビングスキルが求められるのは、何が起こるかわからない命がけの闘いの場に入れてもらうための、最低限の身支度なのかもしれない。今年も残念ながら1名が命を落とした。
一方、若林さんにとって良かったのは、モンゴルラリーとダカールラリーはコマ図などの様式がほぼ同じなので、それを新たに学び直す必要がなかったことだ。
「じゃあ、あとは人間関係と体調管理だね」と言うと、今回は体調管理がとてもうまくいったのだと若林さん。「これまでの経験から、まずは体調管理だなと思って、日本でシミュレーションしていったの。毎朝スタートの時に、いいコンディションにもっていくには何時間前に起きて、朝食はどれぐらい前に済ませればいいか。モンゴルでは便秘に悩まされて辛かったから、そうならないためには何が最も効果的なのか。いろいろ試したの」

さすがだ。女性が長丁場のラリーに出ることの障害として、「トイレ問題」というのがある。競技中、1日ごとのゴール&スタート地点となるビバーク(野営地)には、簡易トイレが用意されているが、それ以外はない。男性のようにサッとは済まない女性が用を足したい時は、物陰や草むらなどを探し、人目を避けるわけだが、プレスやギャラリーがいる場所ではそれも難しい。でも、競技中に水分補給をしなければバテてしまう。それをコントロールするのは並大抵ではない。帰国直後の若林さんが元気なのは、これをやり遂げたことも大きいのではないだろうか。
「あとね、私は2週間、一度もシャワーを浴びなかったの。ビバークのシャワーは基本的に水なの。夜はけっこう気温が下がるから、水のシャワーを浴びて風邪なんか引いたらアウトだなと思って。チームのサポートカーがタンクに水を用意してくれているから、シャワーは浴びずに髪だけほぼ1日おきに洗って、靴下は毎日替えてね。どうしようかな、浴びちゃおうかなと思う日もあったんだけど、菅原さんが『シャワーを浴びなくて死ぬ人はいないけど、風邪引いて死ぬ人はいるよ』って。ほかのレースになくてラリーにあるものは、生活だよね。でも、その生活には無いものだらけ。水、トイレ、お風呂、ベッド、……普段の生活にある快適なものはほとんど無い。そんな『無いもの』にとらわれると、心が疲弊するでしょう。口に入れるものには気をつけるけど、それ以外はおおらかにいられることも、大事なんだよね」

女性として身綺麗でいることよりも、完走するためにあらゆるリスクを排除し、無いものにはとらわれないことを選んだ。でも、途中経過のレポートで見た写真の中で、彼女がとびきり輝いていたのを私はしっかりと目撃している。女性の真の美しさとは、シャワーを浴びる浴びないなんて次元では決して語れないことを、あらためて実感したのだった。そして若林さんはこうも語った。「ラリーには最低限の荷物しか持って行けないから、『これだけあれば生きていけるんだな』という、自分にとってのミニマムがわかるよね。どうしても、男性よりは多くなってしまうけど」
これは、目に見えるモノだけでなく、心の中のモノにも同じことが言えると感じている。恋愛・結婚・出産・離婚、年齢や容姿、仕事や人間関係など、それまで心を占めていた感情たちが、ラリーでは取るに足らないちっぽけなことになる。毎日、ゴールに向かって走ることだけに集中していると、心の中には本当に大切な感情しか残らない。そうした「心のリセット」ができたことは、私がラリーを経験して良かったと思うことのひとつだ。

さて、人間関係の方はどうだったのだろう。チームはドライバーやナビゲーターのほかに、マネージャーやエンジニア、メカニックなど総勢16名という大所帯。でも以前からの顔見知りも多く、スタート前に最後の準備や整備をする期間が現地で約10日間あり、そこでチームに馴染むことができた。ただ、人間の本性を剥き出しにしてしまうのがラリーの怖さだ。競技中はどうだったのかと心配になる。「いちばんに心がけていたのが、どんな時もドライバーが気持ちよくいられるようにしよう、ということだった。もうひとりのナビゲーター、羽村さんはもう13回も菅原さんと組んでいるベテランだから、私の役割はコマ図のダブルチェックとタイヤの空気圧管理などがメイン。ただ、羽村さんとのコンビネーションが本当にうまく機能するまでには8日間もかかってしまった。ラスト5日間は息が合ってるなと思うところまでいけたのだけど」

第一ステージからほぼ快調にアタックしていた1号車だったが、実は第4ステージでチェックポイントを3つ落とす大きなミスをしてしまう。これがのちのちまで響き、トラック部門の総合順位は32位と、昨年を上回ることができなかった。「チームとしては10ℓ未満クラスの1、2フィニッシュは死守できたけど、私は総合順位でもっと上にいくために起用されたことを考えると、この結果はちゃんと受け止めなければいけないね」と若林さん。「チェックポイントを落とした日は本当にショックでこれ以上ないほど落ち込んだの。でも同時に、もうただの一つもミスできない。このミスをいつまでも引きずっちゃいけないとも思った。気持ちを切り替えなければ、と。何とかそれができたのは、『DAY BY DAY』という気持ちの在り方だったと思う。1日の距離もレース期間も長いラリーでは、過ぎたことや先のことを考えると、もたない。その時すべきことを淡々とする、その日が終われば次の日の準備をする。『ただその日があるのみ』という気持ちの持ち方は私がこれまでのラリーから学んだことのひとつ」

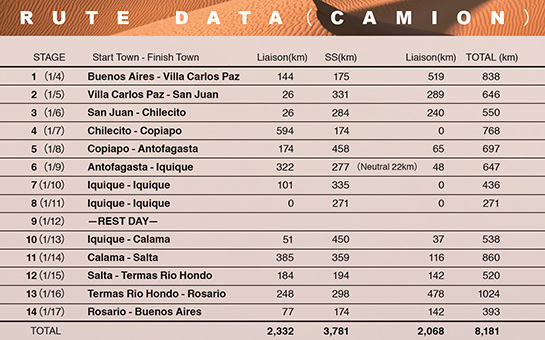
4回のモンゴルラリーは若林さんを着実に成長させていたようだ。「意外と私ってタフなんだなぁと気づいたわ」と笑う。ただ、競技としてのダカールラリーは、冒険のような楽しさやワクワクがあったモンゴルラリーとは別世界。プロによる本当のコンペティションであり、クルマでいける限界を走っている厳しさを感じたという。「今は先のことは考えられない。今回、自分に何が足りないのかがよく見えた。もし次があるとすれば、それらを中途半端にはできないし、さらに本気で取り組まなきゃいけないと思うと……ね」 てっきり来年もやると言うのかと思っていただけに、この言葉は意外だった。競技中、すべてをラリーという目で見て吸収する菅原さんや、一丸となってサポートするチームメイトたちという、プロ中のプロを間近で見たからこそ、よけいにそう感じているのかもしれない。でも、ほんの少し分かる気もする。今はまだ、ダカールラリーという闘いに全身全霊を出し切って、空っぽの状態だ。ラリーの感動は、時間差でじわじわと、ゆっくり染みてくる。
砂丘の向こうに沈む夕陽や、ブルーに輝く山肌、リエゾンで通過する村の家々や、一生懸命に手を振ってくれる沿道の人々。このダカールラリーで若林さんの心を打ったものたちは、これからひとつひとつ彼女を彩っていくはずだ。その時に、いったいどんな若林葉子が現れるのか。楽しみにしていたいと思う。

Yoko Wakabayashi
Akiko Marumo

