「推し活」とは、アイドルやキャラクター、ミュージシャンやスポーツ選手などを情熱的に応援することをいうが、今や3人に1人が何らかのカタチで推しを持っていると言われる。
推し活は単なる趣味の枠を超え、自己表現や心の拠り所となり、さらには大きな経済活動の一部としても定着した。そしてクルマやバイクの世界にも推し活は存在している。
推し活は現代へのアンチテーゼ
文・若林葉子
先ごろ開催された「東京オートサロン2026」に私も足を運んだ。いろいろな感想を持ったが、印象に残ったもののひとつが、“デリ丸。祭り”の様相を呈する三菱自動車のブースだった。推し活は、クルマの世界とも無関係とは言えなくなっている。
推し活と言えば、私の仕事仲間に、還暦も通り過ぎたというのに、いまも地下アイドルの推し活に精を出す友人がいる。仕事でも立派なキャリアがあり、クルマに関してはかなりのマニアでもある。そんな彼が、ライブがあれば日本中、津々浦々、時間とお金を使っていそいそと推しの応援に出かけていく。
いったい何が楽しいのだろう。実際、いつも不思議なほど楽しそうなのである。
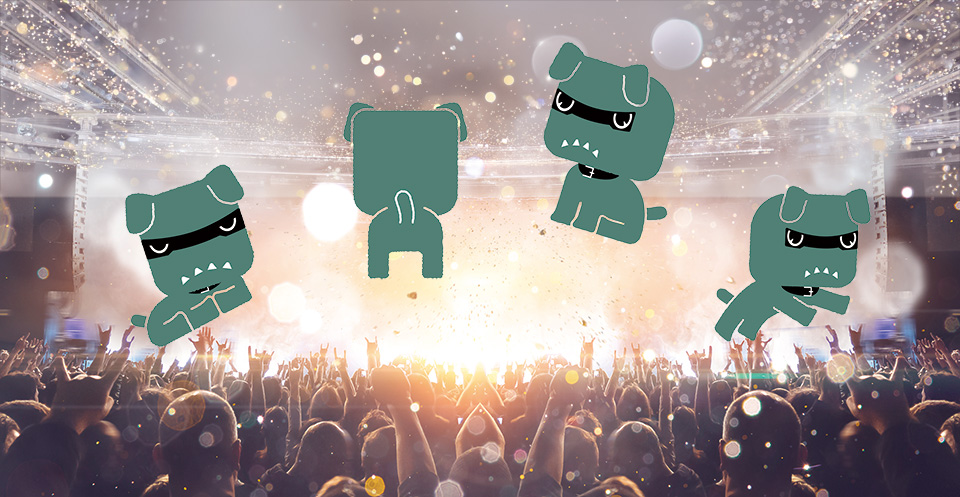
まさにその「何が楽しいのか」を考えるのが、ここで私に与えられたテーマだ。ちょうどよい機会だと思って、聞いてみた。「推し活って、なんなの?」
「それはな、ワカバヤシ。お金の使い方も、時間の使い方も、他人から見たら全然理解できないだろ? でもな、推し活は、その無駄だと思われる行いにこそ、ものすごく高い満足感があるんだよ」
自分の“推し”がいつかスポットライトを浴びるようになる。そうなったらうれしいとか、そうなった時にもしかしたら自分のことを覚えていてくれるかもしれないとか、そういう気持ちがまったくないわけではない。だが本質はそこではない。自分を覚えていてくれようがいまいが関係ない。自分が稼いだお金と自分がやりくりした時間を、自覚的に“無駄”にしている。その無駄な行為そのものに何物にも変えがたい充足感があるのだという。言ってみれば、きわめて純度の高い自己満足だ。
推しがそれを知っているかどうか、どんな見返りがあるかも無関係だ。ライブに行くこと、グッズを買うこと、SNSに投稿すること。そのすべてが自分を満たすための行為であり、だからこそめったなことでは揺るがない。
誰のためにやっているわけでもないのに、その自己満足は経済活動の一部となり、同じ推しを持つ者同士をつなぎ、メディアを動かし、いつしか文化のひとつになっていく。推し活が社会現象と呼ばれるゆえんである。
いま、推し活は日本社会のメインストリームのひとつとも言われている。だが、彼の話を聞いていて、私はこれはむしろ現代におけるカウンターカルチャーの一種なのではないかと思い至った。効率、コスパ、タイパ。早く、無駄なく、損をしないことが善とされ、「うまくやった者」が評価される時代。その価値観の対極に、推し活はある。
合理性が支配的な社会のなかで、あえて非合理を選び取る。
コスパやタイパでは回収できない自由や幸福を、人は推し活の中で手にしているのではないだろうか。
そうした時代の空気を、うまくすくい取ったクルマの代表例が、冒頭のMITSUBISHI、デリカミニだと思う。
発売と同時に登場したマスコット「デリ丸。」は、瞬く間に驚くほど多くのファンを得た。もちろんメーカーが意図的に仕掛けたものだが、それは単なる話題づくりではなかった。クルマという無機質になりがちな工業製品に、最初から「推せる余地」を組み込んだ点が、現代の消費者心理とうまく噛み合った。
デリカミニは、このクルマを選ぶ理由をきちんと説明できなくてもいい。性能や数値、合理性を語らなくてもいい。「かわいい」「なんとなく好き」という私的で曖昧な感覚だけで、クルマとの関係が成立する。

いわゆるマニアでない人間が、特定のクルマを「好き」と言うのは実は勇気がいる。たいてい「なぜ?」と理由を求められるからだ。だからマニアでないクルマ好きはいつも居心地の悪さを感じている。デリカミニと「デリ丸。」はそれを払拭した。目の前に「デリカミニ、好き」と言う人がいても、なぜとは聞かないだろう。「そうだよね」と思うだけだ。マニアでなくても堂々と「好き」と言える。堂々と推せる。そこが多くの人に響いたのだろう。
競争することが当たり前で、勝ち取ることが前提で、努力と結果がすべてだった時代を生きてきたOVER50世代からすると、推し活はとても現代的に見える。
競争しなくていい。勝負しなくていい。比較しないし、評価もしないし、評価を求めない。これまで私はそれを、どこか緩いものだと感じて眺めていた。
だが、違う。
推し活は緩く見えて、やっていることは全力投球だ。しかもそれは消耗戦ではない。勝負だの覚悟だのを言わないぶん、誰に迷惑をかけることもないし、好きな対象に集中できるし、結果として長く続く。持続可能であることもまた現代的である。
すでに体力も時間も無尽蔵ではなくなったOVER50にとって、この「全力だが消耗しない」推し活のあり方は、これからの人生において実はとても示唆に富んでいるのではないだろうか。
若林葉子/Yoko Wakabayashi
モータースポーツも推し活の時代
文・村上智子
ここ最近のモータースポーツファンの変化も、“推し活”という文脈に当てはまるだろう。これまで中高年男性ファンが圧倒的多数だったF1やモトGPの世界に、若者や女性といった新たなファン層が流入し始めたからだ。ファンのスタイルも変化しており、選手の顔をどアップにした自作ボードやウチワといったアイテムを手にした若い女性、お目当てのドライバーが姿を見せると手を振ったり歓声を上げたりといった、まるでアイドルや大好きなアーティストを応援するような光景も珍しくない。それは観客動員数にも影響しており、2025年シーズンはモトGPで初めて360万人を突破、F1は史上最高の670万人に達している。

特に今までと違う勢いを感じさせるのが、米国を中心としたF1人気だ。2025年の調査では、世界のF1ファンは2018年比で63%も増加。1年以内にファンになったうちの約6割が35歳未満という若い層で、新規ファンのほぼ半数が女性だという。モータースポーツといえば、元々クルマやバイク好きで、マシンの性能や技術力勝負を好む人が観るもので、中には両親や彼氏の影響でハマる人もいる、というのが一般的なイメージだと思うが、新たなファン層は全く違う角度から生まれている。
そのきっかけとして知られるのが、コロナ禍直前にスタートしたF1ドキュメンタリー番組『Drive to Survive』(Netflix制作/2019年~)だ。この番組がスポットを当てたのは、最高峰レースの舞台裏。ヘルメットの中のドライバーの素顔や苦悩、チームの人間模様やライバル関係といった“人としての物語”は、普通の人々がモータースポーツという競技を乗り越え、感情移入できる入り口を作った。モトGPで言えば、マルク・マルケスの大怪我による苦難と復活への挑戦を赤裸々に追った『All IN』もその一つ。2025年シーズンに6年ぶりにチャンピオンに返り咲いたことは、背景を見てきたファンにとってはなおさら特別な感慨があるだろう。

考えてみれば、モータースポーツには推し活にうってつけの条件が揃っている。まずは、各ドライバーのキャラが立っており、それぞれに上り詰めてきた歴史がある。そんな一流選手である彼らが、時には運に左右されながらも、悩み、自分と闘い、1人の人間として挑んでいく。こうした生々しい人間ドラマを追うことは、オーディションから見せるボーイズ/ガールズグループにハマっていくのに近いものがある。
しかも、特にF1で顕著なのだが、レース直後にオフィシャルサイトから選手の表情や名言、ベストバトルなど良い素材をバンバン出してくれるものだから、彼らのバックストーリーをチェックしているファンは、推しについての想いを語らずにはいられない。それら素材にハッシュタグが付けられSNSでどんどん拡散されることで、感情や興奮が共有され、それがまた新しい熱狂を生み出すことにつながっていく。


驚いたのは、「2025 Global F1 Fan Survey」によると、ファンの約6割がレース当日に限らず、普段の生活の中でもなんらかのF1コンテンツに毎日接触しているということだ。ドライバーやチームは、人間関係が垣間見えるオフショットやファッションといったサーキット外の日常配信にも積極的で、ファンの世界構築に一役買う。例えばメルセデスはF1チームを家族に見立て、ドライバー達は兄貴分や熱心な弟分、チーム代表が父親といったような雰囲気を作り、ファンはそのキャラクター設定を踏まえて彼らの一挙手一投足を追い、表情や距離感に意味を見出して考察を楽しんだりしているといった具合だ。
こうしたSNSの駆使により、F1は今や観戦を楽しむものから、みんなで感情を共有し合うスポーツへと変化している。他のモータースポーツも、推し活を意識したアプローチを繰り出しつつあり、今後ファンの動きがどのように変わっていくのか注目したい。
村上智子/Tomoko Murakami
「クルマとバイクの推し活について」の続きは本誌で
推し活は現代へのアンチテーゼ 若林葉子
バイクの推し活はマイノリティとマジョリティが交錯する 山下 剛
モータースポーツも推し活の時代 村上智子
映画の中に見つけたOVER50の推し活 山下敦史

