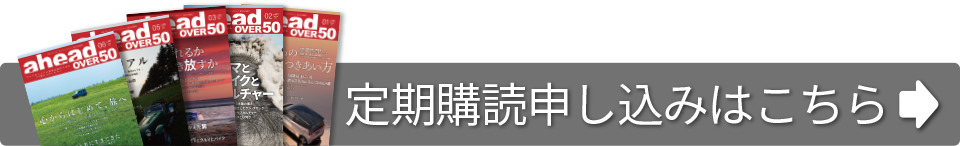“誰にでも忘れられないクルマやバイクがある”をテーマに本誌で連載したリレーコラム「忘れられないこの1台」の中から、今月号に携わった執筆人の思い出の1台を集めてみました。
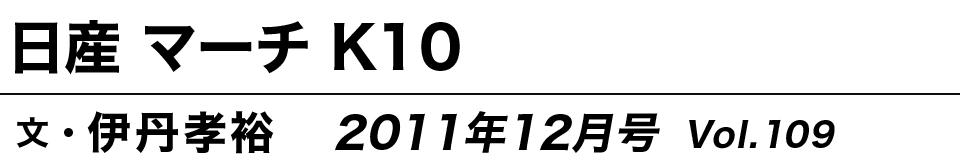
その中古車屋さんの前を何度か通り掛かるうちに、衝撃的な事実に気が付いた。
店の片隅にポツンと置かれたマーチのフロントウインドウに、殴り書きされた「5」という数字。それを見るたびに、「5万円かぁ。安すぎて怖いな…」と思っていたその数字は、よくよく見ると5万円どころか、5円だったのだ。
ゴエンである。穴の空いた硬貨一枚で買えるクルマ。そこまで突き抜けて安いと誰からも敬遠されるらしく、1ヵ月経ち、2ヵ月が経っても売れる気配はなかった。
僕はと言えば、そうやって動向を気にしているうちにだんだん情が湧いてきて、1ヵ月も経てば、「けっこういいかも」なんて思うようになり、2ヵ月が経った頃には、「もし爆発炎上しても、ゴエンなら許せるよな」と、自分に言い聞かせるようになっていたのだ。
結局、僕はそれを買った。
’87年型の初代マーチ。4速のマニュアルでエアコンとラジオ付き。当時すでに12年落ちではあったけれど、エンジンは絶好調。さすがに5円玉1枚を店に置いてくるだけでは済まなかったものの、数万円の諸費用でクルマを手にしたのである。
当時の僕はクルマ雑誌『Tipo』の熱心な読者で、誌面を飾る小さくて軽いクルマ達に感化されて、シトロエンAX、プジョー205、スーパー7…と、手頃な中古車を見付けてきては乗り継いでいた。
マーチを選んだのもその流れ…ではなく、実はクルマ趣味をリセットするためだった。というのも、その頃は結婚を考えていたにも関わらず、生活はフリーター同然。あまりにも宙ぶらりんな生活に我ながら不安を覚えたため、お金を貯めるつもりで乗り換えたのである。
ところがひょんなことで誘いを受け、それから数カ月も経たないうちにその『Tipo』の出版元に入社することになったのだから不思議なものである。
’99年の夏、僕は当時住んでいた京都から出版社のある東京へ引っ越すため、夜の高速道路をマーチで走っていた。ペラペラのドアとフロアからはエンジン音や風切り音が容赦なく入り込み、助手席の彼女との会話もままならない。荷物を満載すると最高速度はせいぜい80㎞/hほど。おまけにダンパーが完全に抜けていたから、ギャップを通過する度にブワンブワンと揺すられ、まるで小舟にでも乗っているような感覚だった。だからこそ、行き着く先にとんでもなく楽しい冒険が待っているような、大航海気分で上京できたのだ。
人生の岐路をともに過ごしたマーチ。今でも街で見掛けると、なんだかワクワクしてしまうのだ。

Takahiro Itami
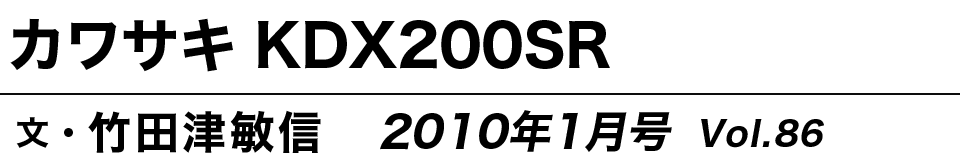
忘れもしない18歳の夏。僕は10万円を握りしめて八王子のバイクショップの前に立っていた。
『KDX200SR』。それが自分で買った最初のバイクだ。わざわざ八王子まで出掛けたのには理由がある。僕が欲しかった黒い車体が、そのショップにしかなかったからだ。
いかにも競技用という感じの、カラフルなモトクロッサーは馴染まなかった。でも、ドコにでも行けるオフロードバイクが欲しかった。探してみると初期型の’89年式にだけ、黒とライムグリーンという〝ちょいワル〟なカラーリングが存在した。「オレが乗るのはこれしかない!」。
それからはせっせと警備員のアルバイトに精を出し、ついに僕は、バイクのオーナーになった。
『KDX200SR』は、カワサキ製のトレールバイクで、エンジンは2ストローク単気筒。ライバルはヤマハの『DT』、ホンダの『CRM』、スズキの『TS』などだが、それらがモトクロッサー的なバイクだったのに対し、『KDX』はどちらかというとエンデューロマシン的なコンセプトで造られたバイクだった。もちろん購入当時はそんなことを知る由もなく、ただ「ワルそうでカッコいい」から手に入れたのだが。
バイクを受け取った瞬間の、何とも言えない感動は忘れない。バイクという自由の扉を手に入れた悦び。「これで何処にでも行ける」。背中に羽根が生えたような気分だった。
その日のうちに先輩に連れられて、深夜の奥多摩に走りに行った。僕はこの日、2回転んだ。1度目は立ちゴケ。そして2度目は自爆。
たいしたスピードじゃなかったけれど、下りの右カーブを曲がりきれずにオーバーラン。前輪が側溝に落ちて外側に投げ出された。「曲がれない」と思った瞬間、身体が石のように固まって、外側にまっしぐら。カーブミラーに頭を打ったときの「コーン」という音は、さぞかし夜の奥多摩に響いたことだろう。
特に痛くはなかったけれど、バイクに乗る以上、こういうことが起こり得るのだというショックに打ちのめされていた。それまで一緒に走っていたはずのバイクが手を離れて路面を滑っていくあの音。その後に訪れるぞっとするほどの静寂。夏の夜の虫の声。愛車の後輪がむなしく回る。「カラカラカラカラ…」。
カーブの手前でどれくらい減速すればいいのか。バイクで一緒に走るとき、どれほどの距離を取ればいいのか。すべて『KDX』から教わった。
地図も持たずに九州まで走った。林道ツーリングにも出掛けた。台風の中、キャンプもした。『KDX』は、まさに僕のバイクの先生だった。
いまでも、中古車雑誌で見つけると、欲しくなる1台だ。

Toshinobu Taketazu
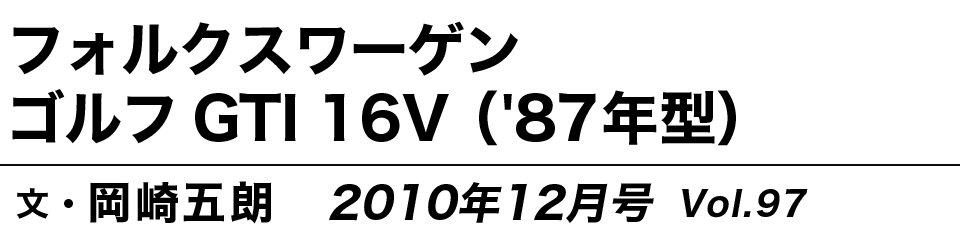
朱色のGTI16V(ゴルフ2)が僕のもとにやってきたのは’88 年夏のこと。手に入れたのは走行距離2万8,000㎞の格安中古だったのだが、こいつは僕のクルマ観を見事にひっくり返してくれた。
GTI16Vに出会うまでの僕はといえば、速いほうがエライ、だからエンジンのスペックは大事だよね、というような、どこにでもいるごく普通のクルマ好きだった。ところがGTI16Vに乗った途端、スペックに対する興味は見事に消え失せてしまった。というのも、スペックなんかよりもずっと大切なモノがあることを知ったからだ。
GTI16Vはそれなりに速いクルマだった。けれどそれ以上に、それまで僕が出会った国産車にはない〝味〟があった。握った瞬間から掌と一体化したかのような感触を伝えてくるステアリングホイール、背筋がスッと気持ちよく伸びるシート、ハンドルを切った瞬間の軽快でいて安定した動き、アクセルを踏み込んだ瞬間の気持ちのいい反応、音、タイヤが路面を捉えるたしかなグリップ感などなど。クルマを運転するってこんなに気持ちのいいものだったのか! 目から鱗が落ちた。
当時の日本はバブル真っ盛り。国内の景気は絶好調で、日本製のクルマや電気製品が世界中で飛ぶように売れていた。すべての日本人が「ジャパン・アズ・ナンバーワン」を謳歌していた。そんな自信に満ちあふれた世の中の片隅で、まだ学生だった僕は、GTI16Vがもたらしてくれたものについて考え始めていた。それはまさに「クルマは通学の手段であり、デートのための小道具であり、仲間と遊びに行くための足である」という当たり前のクルマ観から脱却した瞬間でもあった。
考えれば考えるほど、面白かった。かくして「クルマとは語るに足るものである」という結論に至った僕は、モータージャーナリストという道を選ぶ。あのときあのクルマを選んでいなかったら、きっと別の職業に就いていただろう。
GTI16Vとの出会いから22年。その間、3,000台以上のクルマに乗った。味わい深いものもあれば、味気ないものもあった。社会や人々の価値観も大きく変化した。バブル崩壊と、その後の失われた10年ですっかり自信を失った日本では、クルマといえば広さと便利さのみに関心が集まり、最近は燃費のことしか話題にのぼらなくなってしまった。
伝え手としての無力さを痛切に感じつつ、でも僕は、これからも、クルマの真の魅力とは便利さやスペックではなく、味わいにこそあるのだというスタンスを貫いていくつもりだ。なぜって、そっちのほうが絶対に楽しいから。

Goro Okazaki
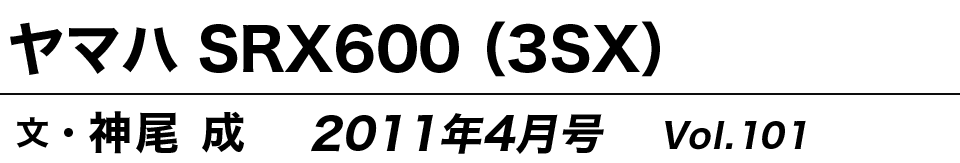
80年代半ばの二十歳の頃、レプリカが全盛の中で突如登場した初代SRXは、後ろ向きとも言えるクラシック指向の大人のバイクとは違う、〝前向きな大人のバイク〟として新鮮に映った。当時は大型の「空冷四気筒」に興味があったので、今すぐに欲しいとまでは思わなかったが、フルモデルチェンジされた4代目は、おとなしめのスタイルが一新され「いつか乗りたい」から「近い将来必ず乗る」という気持ちにさせた。それから数年経ったある日、SRX600が生産中止になるという話を聞き、すぐに知り合いのシングル専門店に相談すると、新車で寝かせたままの車両があるので格安で譲るという。その場で決断して試乗もしないまま翌週に納車することになった。
SRX400には乗ったことがあるので600も似たようなものだろうとタカをくくっていたが、600は400とは明らかに違う乗り物だった。いつものコーナーをいつものように攻めてもギクシャク感が出てしまう。強烈なエンジンブレーキや一回ごとの爆発がはっきり伝わるトルキーなエンジン、スリム過ぎる車体にも戸惑った。前後サスの調整に始まり、二次減速比の変更、パイプハンドル化までして改良を試みたが上手くいかない。広告コピーの「辛口シングルスポーツ」とはこのことだったのか、とかなりへこんだ。しかしこのままでは終われないと『ビッグシングル』なる書物を手に入れ、ライテクの理論からもSRXを乗りこなそうと決心した。
それまで、カタナの750や油冷のR1100J、GSX1100E等の大型4気筒を乗り回していたので「自分はそこそこ乗れる」という自負があった。だがそれは、バイクの許容に助けられていただけだった。4気筒は、どのギアでもアクセルを開ければスムーズに吹け上がり、車体も大柄で重いことから多少ラフに扱っても許されていたのだ。その事に気付き、謙虚さを持って試行錯誤するうちに、SRXに合わせた乗り方ができるようになっていった。コーナーの手前で意識的に回転を落とし、いつもより高いギアで進入、高回転を使わずに早目にシフトすると、4気筒では味わえない快感が得られることを発見。努力が報われたことより、こういう世界があるのかという驚きの方が大きかった。絶対スピードだけでは語れない人車が一体になる悦びを感じることができたのだ。
現在は残念なことにSRXのようなビッグシングルの〝純〟ロードスポーツは、どこのメーカーからも販売されていない。しかしバイク趣味人の平均年齢が高くなった今こそ、辛口で奥深さのあるモデルが必要なはず。キャリアのあるライダーは、向上心を持ち続けているのだから。

Sei Kamio
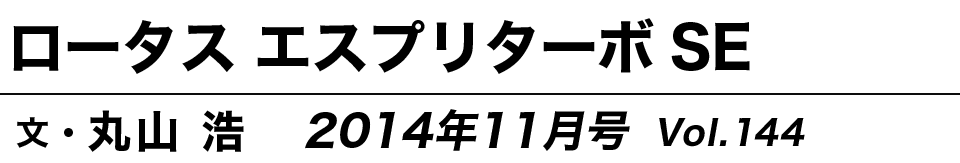
以前の私は四輪にそれほど興味がなく、二輪のロードレースにどっぷりだった。そして四輪と言えば、積載能力No1のハイエースが最高のクルマだと思っていた。
初めて所有したのがキャラバンだ。実はそれ以前も、別の友達のキャラバンを借りてサーキットに通いつめていた。そして全日本参戦が決定した時、昇格のたびに、キャラバンからハイエースGL、ハイエースのスーパーロングへと、積載レベルをステップアップしていった。
さらに国際A級に昇格した際、自分へのご褒美としてフェアレディZ32を追加購入。その後レース資金に困った際に一度手放そうともしたが、何とかスポンサーを見つけ、結局は6万キロ以上乗り続けた。
転機が訪れたのは、HONDA・CB1000SFで挑んだオープンクラスのレースでのこと。2連勝・2連敗・3連勝と、7戦を通してライバルたちと優勝争いを繰り広げていくと、勝つために拘り抜いて製作した自社ブランドのマフラーが飛ぶように売れた。当初は製作費がペイできれば、と販売を始めたのだが、蓋を開ければ数百本もの売り上げ。国際A級ライセンスを持って初めて「勝てば稼げるんだ」とプロレーサーを意識させてくれた経験だった。
そこでまたステップアップとして選んだのが、ロータス・エスプリ。理由は、当時の映画作品「氷の微笑」や「プリティ・ウーマン」の劇中に「仕事でがんばって稼いでいる人が乗るクルマ」として登場したのが、純粋に、単純にカッコよく映ったからだ。
いざ乗ってみると、スーパーカーの部類にしては、小さめの排気量。しかし軽量なボディとの組み合わせで実現されるハンドリングは、あたかも線路の上を走っているようにシャープで(先の劇中でも「オン・ザ・レール」という比喩表現があった)、二輪にも通じる運動性能を感じたものだった。
これを機に会社としても四輪の事業拡大に取り組み、S耐などにも参戦。同時にエスプリのチューニングにも力を注いでいた頃、二輪で付き合いのある編集部から、ロータスの特集本を作りたいとの話が来た。
その監修を引き受けることになり、制作過程ではイギリスのロータス本社を訪れ、テストコースでプロトタイプエキシージに試乗したり、イギリス中の数あるロータスの老舗チューニングショップをインタビューして回ったりと、とても貴重な経験をさせてもらった。
今では会社もロータスの販売店となり、エキシージでレースもしている。思い返せば、人生の節目ごとに思い入れのあるクルマたちに出会っているが、僕にとって最も大きな転機を与えてくれたのはエスプリだ。

Hiroshi Maruyama
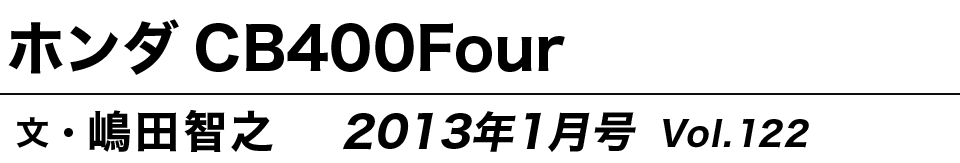
スーパーカー・ブームに一段落の気配が漂い始めてたから、きっと1978年頃、中学2年生のときだったと思う。暇さえあればクルマ雑誌を広げていた僕は、オートバイにも興味を持つようになっていた。クルマの免許は遠くてもオートバイの免許は1年ちょっとしたら取れる、と気付いたからだ。友達の兄貴のミニトレを運転させてもらい、エンジン付きの乗り物を走らせる楽しさと風を切る爽快さを知ってしまったのも大きかった。そんな頃、僕は出逢ってしまったのだ。目の前でヒラリと左に傾いて、流れるように美しいエキゾーストパイプを見せつけながらコーナーを抜けていく赤いホンダに。その瞬間からそのオートバイは、僕にとっての永遠の憧れになった。
──ホンダCB400F。
その時点では生産中止になっていたけど、400㏄クラスで唯一の4気筒エンジンを積んでいて、純正の集合マフラーはそのままでも何ともいえない気持ちいいサウンドを放っていて、それより何より断然カッコよかった。衝撃的だった。絶対に〝ヨンフォア〟を買う、と心に決めた。まるでガキの初恋、みたいなものだ。
そして僕は念願を果たす。7年も後になって、だが…。高校時代は免許の取得が許されない規則だったし、うかうかしてるうちに中古車の相場は上がる一方で、そうこうしてるうちにクルマの免許を手に入れてポンコツを乗り回すようになり…で、なかなか手を伸ばせずにいた。そして、やっと思い切ったわけだ。
ヨンフォアは素晴らしかった。最高だった。速くはなかったけど、滑らかに吹け上がっていくフィールは気持ちよかったし、サウンドも心地好かった。50㎞/hで流していても、存分に興奮できた。だから、あっちこっちを漂流した。それに走らせないでいても楽しかった。眺めてるだけでうっとりできた。ガレージの中でヨンフォアを前にして、いったい何本のビールを開けたことか。
なのに3年くらいして実家の使っていない部屋に仕舞い込みに行って以来、僕はヨンフォアを眠らせてしまった。理由らしい理由はない。クルマ雑誌編集者の仕事がやたらと忙しくなって乗る機会が極端に減り、車検が切れ、梅雨が来たから、くらいのものだ。ずっと手放す気にはなれないまま、もう20年以上が経ってしまった。会社員をヤメて持ってた何台かのクルマを全て手放したときも、残しておこうと思った。いずれ手を入れ直して走らせる気持ちはあるのに、今もまだ何もしていない。
だからこうして日々の中でヨンフォアを想うとき、昔と同じように胸がときめくくせに、その奥の方ではチクリチクリと痛みが走る。今日はちょっと、痛みの方が強いけど…。

Tomoyuki Shimada