2ペダルのクルマと3ペダルのクルマのおもしろさの違いとは何か。
スポーツカーじゃない普通のクルマの中で走って楽しいクルマはどれなのか。またバイクを走らせる歓びはスピードの中にしかないのだろうか。そして還暦を過ぎてから趣味のクルマやバイクを買うことは、どういう意味を持っているのか。それぞれの視点からクルマやバイクを走らせることを深掘りしてみたい。
ライディングプレジャーとは何か
文・伊丹孝裕 写真・関野 温

ライディングの醍醐味が、どこにあるのか。それは「次はこうなる」、「あそこでこうしよう」という予測や計画に対し、その通りの事が起きた時、起こせた時だと思う。「いないいない、ばぁ」と同じで、 (くるぞ、くるかな、こい)という期待と、(きたぁ)という結果がワンセットになった、あの感じ。繰り返しによる学びがその手前段階にあり、それを根拠にした予想と、実際の現象が一致するプロセスに歓びがある。
「いないいない、ばぁ」は、物心がつく前に刷り込まれた、多くの人にとっての最初の成功体験ではあるけれど、3歳を待たずに飽きる。手と手の間から顔が現れるという未来にほとんど裏切りはない。その点、ライディングには不確実な要素が多く、いくつになっても鮮度を失わないところがいい。操作のアルゴリズムがあまりに複雑で、ライダーがバイクの上でなにをしているのかは、今もって精確に測ることはできない。4輪のドライビングシミュレーターのような高い精度での再現性を望めず、実際に走るより他はない。
そんなこともあって、ライディングには一か八かのギャンブル性がつきまとう。乗らない人よりは死が少し近い、という事実は確かにあり、良くも悪くもカジュアルに「死ぬかもしれない俺」というヒロイックな気分に浸れてしまう。スピードの向こう側がどうとか語り、雨風寒暑にさらされながらひた走るのもそう。ハードボイルドを気取り、今時の電子制御を拒絶し、ブレーキングやシフトダウンの技術を口にするのはいいけれど、そういうライダーからどんどん失敗している。若かった時代を、せっかく運よく乗り切れたのに。
速さを競い、バンク角を誇っていた頃は、それはそれで楽しかった。かつては同じような他者が周りにたくさんいて、そのおかげで自分の力を誇示できる環境があったわけだが、それもすっかりいなくなった。誰が見ているわけでもないのだから、なにに期待するでもなく、スピードを少し落としませんか。いけるかどうか迷った時は、必ずいかない方を選択しましょうよ。
長い間、ロードレースに軸足を置いてきた。300㎞/hの領域にライディングプレジャーなんてあるわけもなく、あるとすればパドックに戻ってから感じられる安堵の手応えだ。ある時、それにひと区切りをつけ、エンデューロやトライアルに没頭した。そこは平均時速が20㎞/hにも満たないどころか、止まっている時間も短くなく、そういう世界がとても新鮮だった。2輪を操ることを仕事にしてきたのに、自分にはできないことがこんなにあるのかと驚き、それもまた楽しかった。
どんなバイクでも、スピードを落とせば「次はこうなる」を前にして、ゆっくりと考えることができる。瞬く間に過ぎ去っていく風景の中では無理だった答え合わせも、ゆっくりとできる。答えが間違っていても、取り返しのつかない失敗にはならず、すぐにやり直せる。その行ったり来たりの中で、バイクが思いのままになる瞬間がたまに、本当にたまにあり、それがすごく気持ちいいなぁとしみじみ感じている。
以前、『官能』という特集のテーマで、2輪と4輪のコーナリングの違いについて考えたことがある。4輪の快楽が、進入時に一発で車体を組み伏せられた時だとすれば、2輪は、なだめながら限界を探る必要があり、時間の感覚がずいぶんと違う。そんなことを書いた。当時は、なだめて探る時間をどんどん切り詰めようとしていたが、今はその時間を引き伸ばし、ゆっくりと堪能しようとしている。
伊丹孝裕/ Takahiro Itami
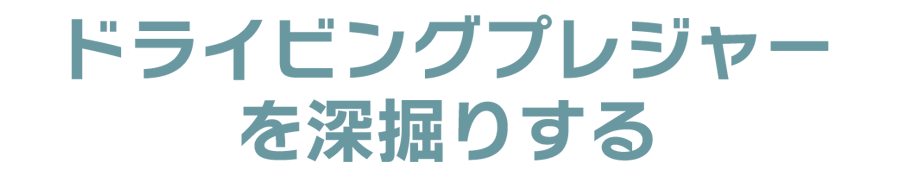
伊丹孝裕
