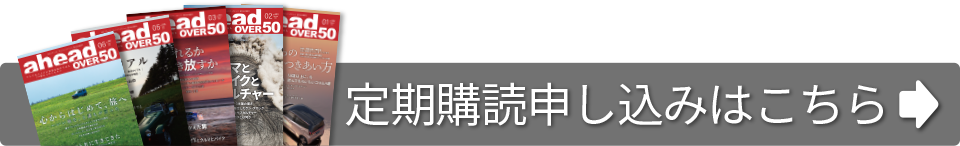本誌で連載を開始して今年で20年になる大鶴義丹が、2年がかりで油冷GSX-R1100のレストアを完成させた。
一方、究極の油冷GSX-Rといわれるヨシムラ・ボンネビルの開発を担当した浅川邦夫氏も70歳になった今、油冷GSX-Rに乗り始めたのである。今回、初対面となる2人は油冷の話題を皮切りにオートバイについて語り合った。そして社会的な見地のバイク記事を多く執筆する山下 剛が、自身のライフワークとして通い続けるマン島TTの魅力をレース以外の側面から紹介する。

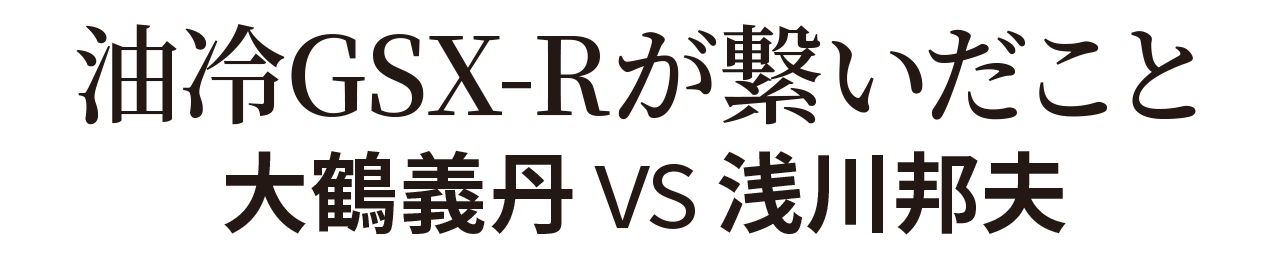
まとめ・神尾 成 写真・関野 温
ーー お2人は、同じ型の油冷のGSX-R1100に最近になって乗り始めましたが、どういうきっかけがあったのですか?
浅川お客さんから長年大切にしてしてきた車両を手放したいと相談があったので、それを自分が引き取ったんです。ヨシムラ時代に油冷を散々やってきたし、昨年の秋に70歳になったこともあって、これも一つの流れというかタイミングなのかなって思ったんです。
大鶴僕の場合は、知り合いの会社経営者から病気で乗れなくなったバイクを社員が処分したがっているので相談にのってやってほしいと頼まれたんです。それで見にいったら、3年くらい放置された状態で錆だらけでアルミフレームも白い粉を吹いてた。最初はバラして部品取りにすることを考えてたんですけど、転倒した痕跡がないのでレストアして自分で乗ろうと決めたんです。
浅川さっきバイクを見せてもらったけどフレームまでピカピカにバフ掛け(アルミを磨いて鏡面仕上げにすること)してある。あれも自分でやったの?
大鶴そうです。バイクをバラバラにしてバフ研磨グラインダーで2週間くらいかけて磨きました。すごい埃で大変でしたね。健康にも悪そうだし、もう2度とやりたくないです。
浅川ウチのお客さんでもバイクを預かる度に、少しずつ磨いているところが増えていく人がいるけど、バフ掛けは根気がいる作業だしバイクに愛情がないとできないことだよ。業者に作業を依頼することは考えなかったんだ。
大鶴いちおう知り合いのバイク屋に訊いたら60万円くらい掛かるって言われて。それに自分でやれることはやりたい方なんです。これまでもXR250(ホンダのオフ車)や1100刀のエンジンをオーバーホールしてきたので、今度は車体全体をオーバーホールしてみようと思ったんです。
浅川なかなかそこまで自分でやろうとは思わないよ。aheadのコラムを読んでるから知ってたけど、本当にバイクが好きなんだね。バイクに乗るのが好きな人と
大鶴僕は両方ですね。今は乗るのはオフロードの方に振っちゃってますけど、弄るのは、この時代のバイクじゃないと無理ですし、免許を取った頃の刷り込みもありますから。それに乗るためにレストアしてるというより、あの時代のバイクのことをもっと深く知りたいっていう感じなんですよ。

ヨシムラボンネビル
大鶴浅川さんに会ったら“ボンネビル”のことを聞きたいと思ってたんです。油冷ファンに限らず僕らの世代が憧れた、油冷GSX-Rの究極と言えるヨシムラボンネビル(※1)は、どういったいきさつで作られたんですか?
浅川ちょうど僕がレースグループから営業部に移った頃に、社内でヨシムラの象徴になるようなバイクを作ろうって話になって開発を担当したんだよ。油冷GSX-Rはヨシムラにとって3年連続でチャンピオンを獲った大事なものだから世界最速のバイクにしなきゃいけない。それまで部品として販売していたGSX-R750のキットパーツをベースに、みんなで試行錯誤を繰り返したんだ。
大鶴何が一番苦労されましたか?
浅川実は車検証のメーカー名(車名欄)を「ヨシムラ」にすることが一番たいへんだったんだ。日本で改造して登録申請しても車名欄は変わらないから、アメリカで車両を購入して改造してから日本に送ることにしたんだけど、ヨシムラR&D(USヨシムラ)に開発した部品を送って組んでもらったり、日本での登録手続きに1年近くかかった。当時はヨシムラの名前が付いた車検証にどうしてもしたかったんだ。
大鶴そこまでヨシムラの車名にこだわったのは、なぜなんですか?
浅川一番は親父さん(ヨシムラ創設者の吉村秀雄)の存在だね。ヨシムラの名前がついたバイクを世の中に出せば、ヨシムラが5番目の日本のバイクメーカーになれると思ったんだよ。親父さんには、若い頃から世話になってきて精神論というか今の根幹になるものを鍛えられた。親父さんは予科練出身の戦争経験者だから、他の人とは気合いが違うっていう感じだったな。あの人だったから大メーカーを相手にヨシムラはレースで勝つことができたんだ。
大鶴僕は、そういう人間の物語みたいなものに惹かれてバイクに乗ってきたんです。これはバイクに限った話ではないですけど、今は何事においても役割分担がはっきりしてるから、自分の責任以外は関係ないみたいな風潮が強くてクルマやバイクに人間臭さがなくなってきてると思うんです。だから若い子も含めて人の物語を感じる“あの頃のバイク”に、みんな憧れを持っているんですよ。



SUZUKI GSX-R1100G(’86年型)

バイクとデジタル
浅川少し前のことだけど、お客さんから知り合いのバイクを診てやってほしいって頼まれたんだ。だけどよく話を聞いてみたら、ネットでの知り合いなので会ったこともないって言うんだよ。それは知り合いじゃないだろうと思って、忙しいこともあったから断ったんだ。
大鶴僕の友人でSNSを通じて集まったツーリングに参加したヤツがいたんですけど、途中で1台のバイクが動かなくなったらしいんです。だけどその人を置いてけぼりにして他の人はツーリングを続けたって聞いて、何か引っかかっちゃって。
浅川それで、その置いていかれた人はどうしたのよ?
大鶴そいつが言うには、自力でJAFとかを呼んだらしいんです。バイク乗りだから助け合おうって言いたい訳じゃないけど、せめてJAFが来るまで付き合うのが一緒に走った人間の責任なんじゃないかと考えてしまうんです。これはネットとは関係ない話ですけど、仲間と林道にいって休憩したあとに走り出そうとしたら、最新のアドベンチャーバイクの電子ハンドルロックが解錠できなくなったんです。原因はコンピューターのバグだったんですけど、山の中だったんで大変でした。結局、麓まで台車を取りにいって、前輪を台車に乗せて仲間全員で無理やり引きずって脱出させたんです。キャブレターに戻せとまでは言いませんが、アドベンチャーバイクは絶対にアナログにすべきですよ。状況によっては生命に関わりますから。
浅川今はなんでもデジタル化されてしまってバイクをパソコンに繋がないと修理することができなくなってる。それも時代の変化だから仕方ないことだけど、バイクは整備においても人間の介入する幅があることが大切な乗り物だと思うんだけどね。
大鶴そうなんですよ。そもそもバイクに乗ること自体がアナログみたいなもんですから。今回、刀のエンジンやGSX-Rを自分でバラし組みできたのもアナログ時代のバイクだったからです。最近のバイクはブラックボックス化が進みすぎて、整備する気にもなれない。バイクを弄るという楽しみが奪われているようにも思うんです。このままではエンジンに興味が持てなくなるから“油冷伝説”みたいな物語は生まれてこないですよ。
浅川僕があの時代に、親父さんとヨシムラでレースをやってこれたのも、ボンネビルを作れたのもアナログならではの可能性があったからかもしれないな。

SUZUKI GSX-R1100H(’87年型)
OVER50のバイク乗りについて
ーー お二人は、50歳以上でバイクに乗っている人についてどういうお考えですか?
浅川お客さんで50歳を過ぎて初めて免許を取ってバイクに乗り始めた人がいるんだけど、今は67歳で富士スピードウェイをアプリリアRSV4でガンガン走ってるよ。それなりの年齢になったら、体力を維持するために食べ物や健康に気を使うことが必要になってくるのは確かだけど、スポーツとして取り組めば問題ないと考えている。

大鶴オフロードならクルマがいないので僕も大手を振って賛成できるんですけど、街中については慎重にならないと危険だと思います。特に死亡率が高い右直事故(右折するクルマと直進するバイクの衝突事故)は、長年の勘というか本能的な部分に頼ることが大きい。クルマしか運転してこなかった人は、ルールを守っていれば大丈夫だと考えがちなんだけど、事故はルールとは関係ないところで起きるから正しい正しくないを言っても怪我をするのはバイクになります。
浅川それは確かだね。高速道路の出口付近で渋滞してるクルマのすぐ横をバイクで走っていく人を見るとヒヤヒヤする。いつ車線変更してクルマが飛び出してくるかを想像しないと。街中は常に意識を戦闘状態にしてないと危ないよな。
大鶴極端に言ってしまうと、右直事故に関しては自分次第で防げるんですよ。それはルールに依存してるか、常に想像して考えてるかが分かれ目になります。その人の性格や人間性みたいなものが一番大事なのかもしれません。
浅川バイクは、その人のことを剥き出しにしてしまうからね。
大鶴僕はリターンを含めて、バイクを始めようとする人に対しては何も思わないんですけど、逆にやめていく人とは、どうしても心の距離を感じてしまう。やめた理由がお金の問題とかなら納得できるんですけどね。だから年齢に関係なく、「来る者は拒まず、去る者は追わず」でいようと決めています。
浅川かれこれ55年もバイクと関わってきたけど、バイクは仕事であって趣味でもあるけど人生の全てじゃない。だからといって軽い気持ちで付き合っていけるものでもなかった。それこそバイクは「たかがオートバイ、されどオートバイ(※2)」ということなんだよ。

浅川邦夫/kunio Asakawa
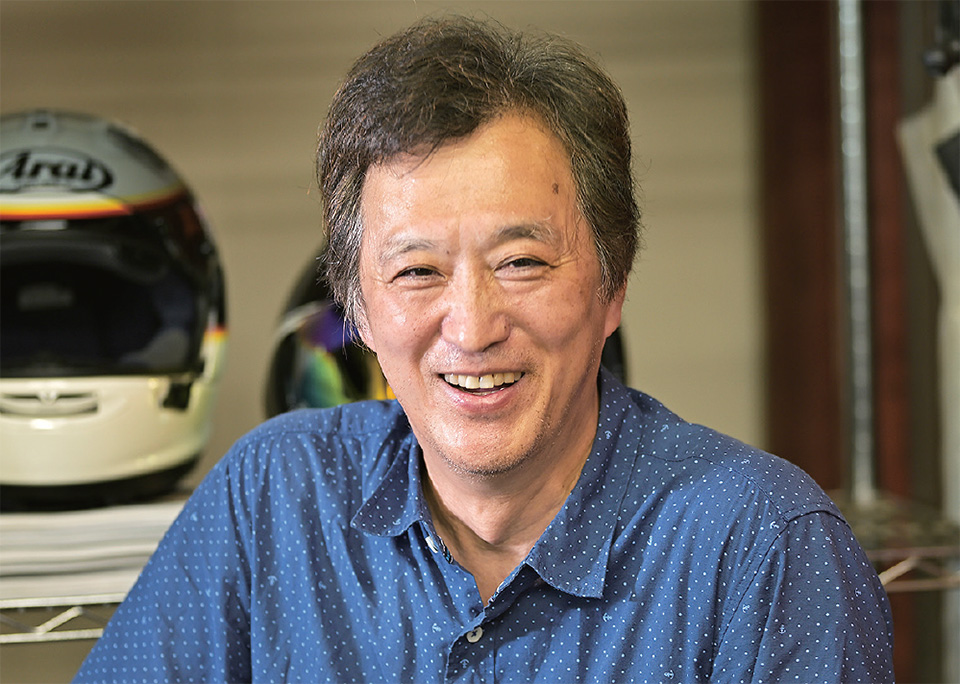
大鶴義丹/Gitan Ohtsuru
「オートバイについて語ろう」の続きは本誌で
油冷GSX-Rが繋いだこと 大鶴義丹VS浅川邦夫 まとめ・神尾 成
マン島TTへの