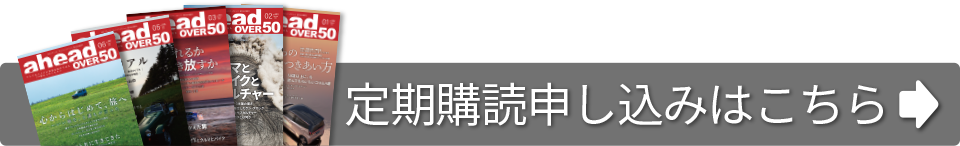ネオクラシックと呼ばれるジャンルが定着して久しい。
それらは普遍的なネイキッドスタイルだったり、もっと直接的に昔の名前が与えられている。このジャンルは、一世を風靡した歴史的アイコンを持つメーカーが強い。Z、CB、カタナ、トライアンフ・ボンネビルあたりが最たる例で、復刻が望まれるだけのストーリーがそれぞれにある。

YAMAHA XSR900 GP ABS
総排気量:888㎤
エンジン:水冷4ストローク直列3気筒/DOHC・4バルブ
車両重量:200kg
最高出力:88kW(120ps)/10,000rpm
最大トルク:93Nm(9.5kgm)/7,000rpm
燃料消費率(WMTCモード値):21.1㎞/L
(クラス3、サブクラス3-2)1名乗車時
一方でそうした路線から外れ、独自のネオクラシック像を描いているのがヤマハだ。エポックメイキングなモデルとしては、DT-1(’68年)やRZ250(’80年)があるものの、ビッグバイクにおいてはそれが乏しい。結果的に何にもとらわれず、そのため、ウルさがたの顔色をうかがう必要も、足かせもないことがよかった。ヤマハはネオクラシックに対する解釈を拡大し、固有の名ではなく、ある時代に焦点を当てたのだ。ここが新しい。
新しいといっても、ヤマハは「XSR900」を通じて、用意周到に事を進めていた。’16年の発売以来、「レトロ」や「ヘリテージ」を謳いつつも、徐々にスポーツイメージを強め、’22年モデル登場の際は、「1980年代レーサーを彷彿とさせるデザイン」とリリースに明言している。広告規制を踏まえ、ロゴや商品名こそ出していないが、この時に追加された色鮮やかなフレンチブルーの外装は、当時のゴロワーズカラーに他ならない。そして、「Legend Reborn」と題されたPVでは往年の名ライダー、クリスチャン・サロンが重要な役割を果たした。
これを助走とし、ヤマハ流ネオクラシックをさらに推し進めた存在が「XSR900GP」(’24年)だ。単にXSR900をセパハン化してカウルを追加しただけでなく、前後サスペンション、車体各部の剛性チューニング(エンジン懸架/ステムシャフト/ピボットまわり/リアフレーム)、ブレーキホースの変更といった専用のあつらえで、高負荷・高荷重への備えを図っている。

走りに対するこうした実利もさることながら、XSR900GPが持つ本当の吸引力は、見る者、触れる者の心を引き戻し、饒舌に語りたくなる、デザインの“あの頃感”にある。それは、フレームとアッパーカウルを繋ぐ丸パイプ、その締結に用いられたアルミカラーとベータピン、後付けのナックルガード、大きくラウンドしたクリアスクリーン、イエローのゼッケンプレート、サイドカウルを固定するクイックファスナー、デルタボックスを思わせるシルバーのアルミフレーム…と至るところに見つけられ、極めつけは独自の赤と白に塗り分けられた外装だ。誰の目にも「Marlboro」の文字が浮かぶ。
XSR900GPは、特定のモデルを下敷きにしていない。便宜上、それを「YZR500」としていながらも、無論2ストロークエンジンであるはずはなく、気筒数にも排気量にも近似性はない。カウルもハーフタイプに留められ、なにをイメージするかは見る側に委ねている。
キングと若き天才が死闘を繰り広げた伝説のシーズンなのか、孤高の仕事人が優勝を積み重ねた混沌の80年代半ばなのか、90年代の序盤にかけてヤマハ最強時代を完成させた王者の不屈さなのか。あるいは世界グランプリに限る必要もなく、悲運と悲願が入り混じった灼熱の鈴鹿8耐だったり、空前のレーサーレプリカブームが生んだTZRやFZRのレストモッドとしての在り方だったりと、それぞれがそれぞれの熱狂を自由に投影することができる。
獰猛さと野蛮さが渦巻いていた、あの頃の残り香を封じ込めた存在がXSR900GPだ。60年代でも70年代でもなく、80年代の、しかもレーシングマシンという他にないモチーフだからこそ、今一度時代を振り返り、継承すべき情景が詰まっている。

YAMAHA XSR900 ABS
総排気量:888㎤
エンジン:水冷4ストローク直列3気筒/DOHC・4バルブ
車両重量:196kg
最高出力:88kW(120ps)/10,000rpm
最大トルク:93Nm(9.5kgm)/7,000rpm
燃料消費率(WMTCモード値):20.9㎞/L
(クラス3、サブクラス3-2)1名乗車時
伊丹孝裕/Takahiro Itami