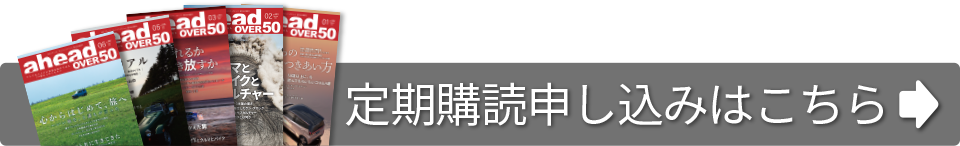1955年に純国産乗用車として世に出た初代クラウン。
すでに70年の時を重ね、欧米に追いつけ追い越せと走ってきた日本も、気がつくとすでに成熟した豊かな自動車文化が築かれていた。瀬イオナが、国内外の歴史的車両を所蔵する「トヨタ博物館」を取材し、日本車の歴史とその文化について岡崎五朗に話を聞いた。
初代クラウンは元祖メイド・イン・ジャパン
岡崎五朗(以下、岡崎)イオナさんは今月号の取材で「クラウン70周年記念展~なぜ70年生き続けているのか~」に行ったじゃない? 1955年にクラウンはメイド・イン・ジャパンでデビューしたけど、当時、日本の自動車メーカーはまだ独自でクルマを作る技術がなかったから、海外メーカーの技術を参考にしていたんだよ。
瀬イオナ(以下、瀬)クラウンの特別展示と合わせてトヨタ博物館の常設展示も見学させていただいたのですが、自動車の黎明期から現在に至るまで世界中のクルマが鎮座していて圧巻でした。日本車は20世紀に入ってから生産が始まり、自動車が大衆のものとなったのはようやく昭和の時代に入ってから。世界から遅れをとっていたことがよく分かりました。
岡崎明治は軍需工業中心の重工業、大正は繊維産業中心の軽工業が盛んで、トヨタ自動車の原点である豊田紡織も豊田佐吉氏によって大正7年に創業された。その豊田佐吉氏の長男、喜一郎氏が1924年の関東大震災で、鉄道が被害を受ける中、代わりの輸送手段として自動車が活躍するのを目の当たりにして、自分たちで自動車を国内生産したいと願った。そして1933年に豊田自動織機製作所の中に自動車部を作り、1937年にトヨタ自動車工業が設立された。最初は輸入車から学んで行くわけだけど、国内生産したい気持ちは変わらず、試行錯誤を経て、ようやく1955年にクラウンが誕生したという経緯があるんだ。日本のモータリゼーションはクラウンのように70年以上も続くブランドの長さと深さとイコールだと思っているんだよ。
瀬スタートは遅くても目まぐるしく進化して、とても歴史が濃いですね。

トヨタ博物館
住所:愛知県長久手市横道41-100
Tel:0561(63)5151
詳細はHPでご確認ください。
https://toyota-automobile-museum.jp/
日本車はすでに長い歴史があり海外でもリスペクトされている
岡崎最近、中国車が絶好調だよね。BYDも「すごい」とか言われてる。新興の中国や韓国に対して、日本の強みはやはり長い歴史に裏打ちされた成熟したクルマ文化を持っていることだと思うんだ。それはメーカーだけではなく、ユーザーも同じで、世界中で強みを発揮できるという仮説を僕は立てているんだ。
瀬中国勢もそうですが、韓国のヒョンデやアメリカのテスラも勢いがあって、自動車のあり方に変革が起こっていますね。
岡崎今、テスラ、BYD、ヒョンデとどんどん新しい勢力が興ってきて、「100年に1度」の変革期と言われている。そういう大きな構造変化の中で「このままだと日本はやられるのでは」など様々な意見が出ているけど、本当にそうなのかな? 日本車は壊れなくて経済的で燃費がいいことを売りに世界に受け入れられたけど、この数十年で日本には芳醇なクルマ文化が育まれた。それを活かせば新興勢に簡単には負けるわけがないと思うんだよね。たとえば『
瀬多様性かぁ。それが日本のクルマ文化を理解するうえでのキーワードになりそうですね。私、サブカルチャー系は公道では違法となってしまうようなイメージがあってあまり良く思ってなかったんですが、すでに一ジャンルとして確立していて、JDMも海外の若者に大人気だと聞きます。「クルマ好き」と言っても正統派や、旧車、カスタムカー、サブカルチャー的なものなど多様で、その多様性こそが海外にはない日本独自のクルマ文化なのかもしれませんね。
岡崎日本の発信したクルマ文化って、ドリフトや痛車、JDMなどだよね。それらが否定されず認められたときにクルマ文化はものすごく広がると思う。イオナさんと同じで、僕もあの世界は全く理解できなかったし、自分は絶対に片足も突っ込みたくないと思ってた(笑)。それが、最近、少しずつ変わってきて、「あり」かも、みんな楽しんでいるのだからいいじゃんって思えてきたんだよね。
瀬きっかけは何だったのですか?
岡崎僕はもともと正統派のクルマ好きだった。岡崎五朗=正統派モータージャーナリストである、と(笑)。するとサブカル系はやっぱり自分の範疇外だし、風潮としてあまり認めたくなかった。それが変わってきたのは、近年、80~90年代の日本車の魅力にはまった外国の人たちが、本気で楽しんでいる姿をYouTubeでみたことかな。灯台下暗しというか。
瀬私たちはもっと自信を持つべきなのかもしれませんね。これまで40年間、欧米でしか開催されてこなかった「世界自動車博物館会議」が昨年(2024年)秋に初めて日本で開催されたのも、日本車がすでに正統な工業製品として約100年の歴史がある上に、アニメや漫画、ゲームといったサブカル、ポップカルチャーを通して日本の人気が高まってきているから、というのが理由だそうです。トヨタの豊田章男会長も、今まで欧米に追いつけ追い越せだったけど、日本が世界から一目置かれるようになったことを非常に喜んでおられたと聞きました。正統派とサブカルという2つの文化がどちらも海外で評価されたのは、確かに嬉しいですね。

旧いクルマにわくわくするのに今のクルマにできない理由
岡崎イオナさんは、今のクルマにわくわくすることはある?
瀬ちょっと言いにくいのですが、正直ないのです。昔、盛り上がっていた時代の旧車とか、80~90年代のクルマにはわくわくするのですが……。
岡崎それはね、実際そうなんだ。今は排ガス規制や安全基準とかの規制にミートするためにメーカーはがんじがらめになっている。昔は、どこのメーカーでも開発陣がとにかく何をやったら面白いか、何をやったらユーザーに喜んでもらえるか、俺たちはもっと独自の路線で行こうぜ、みたいな気運が全社的にあったと思う。規制も少なかったから作り手が自由に面白いクルマを作ることができたんだ。それを盛り立てたのが経済状況。1989年は日本車のヴィンテージイヤーと言われていて、ユーノスロードスター、セルシオ、レガシィ、GT-R、NSX(発売は翌年)などが次々と世の中に出てきて、この時代日本のクルマは世界の頂点に立ったと言われたくらいだった。でも翌年のバブル崩壊で状況が一変。燃費が良くて壊れなきゃいいでしょみたいな空気になってしまった。さらに2008年のリーマンショックが落とした暗い影は計り知れなくて、トヨタでさえ赤字に陥った。この時の開発費削減がクルマの質に与えた影響は大きかったね。

日本が愛されている理由の中にこれからのクルマのヒントがある
瀬クルマってつくづく世相を映す鏡なんですね。
岡崎その通り。工業製品の中ではダントツにその傾向が強いと思う。実際、クラウンも最初に言った通り戦後の高度経済成長、国産車構想が絡んでいる。カローラは東京オリンピック開催後の1966年に登場し、ようやくマイカーをもてるようになった庶民の足になった。経済とクルマは必ずくっついているんだ。
瀬クルマは、歴史や経済など社会の背景を通して見ていくことが大切なのですね!
岡崎むしろ時代背景や世界情勢と併せて考えないとクルマの評価はできないと思う。そう考えると、経済や歴史が大きく変化する中で、クラウンやカローラが現在も存続していることは凄いことだし、時代に合わせてしなやかに変化してきたからこそ生き残ってこられたとも言えるんじゃないかな。
瀬それって、作り手側がユーザーの気持ちにいかに寄り添うのかということですね。
岡崎その通り。日本車が世界中で愛されている理由を考えてみると、実はわれわれの国民性が受け入れられているんじゃないかと思うんだ。外国人から見るとコンビニで売っているおにぎりやサンドイッチも美味しいし、バッグを置き忘れてもなくならないし、道にはゴミが落ちてなくて、電車だって5分遅れただけで謝るわけだよね。それって、煎じ詰めれば他人を思いやる気持ちだったりするわけでしょ。
瀬ですね。日本のおもてなし文化やもの作りの姿勢は約100年の歴史を持つ日本の自動車産業にも「強み」として築き上げられて来たんですね。凄く誇りを持てますね。今はわくわくするクルマがないと言いましたが、今後また、そういうクルマが出てくる可能性もあると考えて良いのですよね?
岡崎うん。さっき言ったみたいに日本が観光地として海外から愛されている理由を因数分解していくと、日本車のあるべき姿っていうのも見えてくるかもしれない。自動車メーカーだってもちろんそういうことを考えていないはずはないしね。これだけの成熟したクルマ文化のある国だから僕はこれからに期待したいと思っている。
瀬そうですね! 私もわくわくしながら待ってみようと思います。
岡崎五朗/Goro Okazaki
瀬イオナ/Iona Hayase