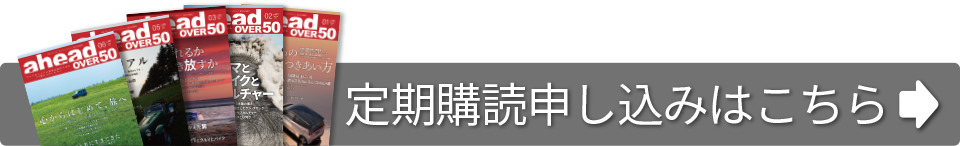ソノートブルーを纏ったヤマハのグランプリマシン「YZR500」がガレージに置かれている。
1986年型のゼッケン3。かたわらに立つのは、かつてそのマシンを駆ったクリスチャン・サロンだ。顔に刻まれたしわこそ深くなったものの、穏やかな目もスマートな体躯も現役時代と変わらない。今も蒼き紳士のままだ。
アングルが切り替わり、手前にあるもう一台のバイクをカメラが捉える。燃料タンクは鮮やかなブルーメタリックで彩られ、YZR500との近似性が意識されていることが分かる。そして、現役時代さながらのヘルメットを被ったサロンがそのバイクにまたがり、ワインディングやストリートを颯爽と駆け抜けていく……と、そんな映像がヤマハのウェブサイトで公開されている。この6月に導入された新型スポーツネイキッド「XSR900」のPVだ。
XSR900は、ヤマハがスポーツヘリテイジと名づけたカテゴリーに属している。一般的にはネオクラシックと呼ばれるスタイルであり、この20年ほどの間に定着。その多くは、60年代から70年代のテイストが強調されている。
そんな中、XSR900の存在はちょっと異端だ。丸目のヘッドライトやバーハンドルはネオクラシックの定番に従いつつも、多数派とは時代もモチーフになったモデルも一線を画している。先のPVで表現されている通り、XSR900のそれは80年代であり、レーシングマシンなのだ。
「どこが?」と思うだろうか。色がそれっぽいだけじゃないかと。しかしながら、あの時代を知っていれば「ああ確かに」と腑に落ちる人もいるに違いない。たとえば、XSR900を真横から眺めてみる。すると、メンテナンスを受けるため、サイドカウルが取り払われたYZR500のたたずまいとイメージが重なってくる。
その象徴が、鋭利な三角形を描くメインフレーム、異形の平行四辺形を思わせる燃料タンク、台形のタンデムシートなどだ。形状やサイズの差異こそあれ、それらはあの頃のヤマハの流儀に倣ったもの。シートは低め、ヒップポイントは後方、車体姿勢は軽く前傾しつつもほぼ水平なところもそうだ。フルカウルを纏った2ストロークレーサーのシルエットを、ネイキッドの4ストロークモデルを介して表現しているところが新しい。

もう少し車体に近づいてみる。ドリリング加工が施されたヘッドライトステー、エアプレーンキャップを思わせる凝った作りの給油口、クイックファスナーで留められたサイドカバー、空気を通すためのタンクスリット。各部に散りばめられた、そうしたディティールにも「らしさ」を見つけることができる。
そしてもうひとつ。ささやかながら、しかし決定的なのが、燃料タンクとシート表皮の間に設けられたクリアランスだ。サイドカバーが車体左右から回り込み、上面でつながる部分の、わずか数センチほどのスペース。たったそれだけのことではあるが、この造形ひとつで、すぐさま脱着できる一体型レーシングシートカウルに見えてくるからおもしろい。もう少し想像力をふくらませると、ライダーシートは簡易なスポンジラバーに、タンデムシートはゼッケンスペースにも思えてくる。
タンデムステップは、外部からほとんど見えないように収納され(なのにペグもブラケットもアルミ鍛造だ)、光っていなければテールライトの存在感もない。つまり、徹底してシリアスな雰囲気が追求されているのだ。
すべての準備が完璧に整えられた、戦いの前の緊張感にレーシングマシンらしさを見出すファンは多い。その一方、精密なメカが剥き出しになったストリップ状態にセクシーさを覚えるマニアも多いはずだ。XSR900から感じられるのは、後者の匂いである。それこそが他のどんなネオクラシックにも、先代のXSR900にもなかった部分であり、使っているデザイン言語がまるで異なっているのだ。
ヤマハの歴代レーシングマシンが保管されている場所がある。XSR900の開発を前にして主要なエンジニアとデザイナーの全員がそこに赴き、実際に触れて、またがり、このモデルが生まれた。ゆえにカタチだけではない。ハンドリングにもまた、かつてのヤマハらしさが再現されることになった。一定の世代のライダーにとって、なにかを呼び覚ますトリガーになる存在である。

YAMAHA XSR900 ABS
エンジン:水冷直列3気筒・4ストローク・DOHC・4バルブ
排気量:888cc
車両重量:193kg
最高出力:88kW(120ps)/10,000rpm
最大トルク:93Nm(9.5kgm)/7,000rpm