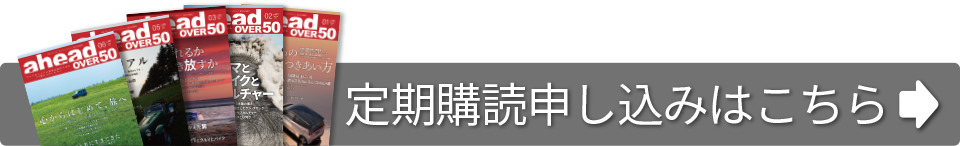か細い排気音に混じり、コッチンコッチンと気の抜けたウインカーの点滅音が近づいてくる。どうやら無事に帰ってきたようだ。
最近小型2輪の免許を取り、クロスカブ110に乗り始めた娘である。こうして原稿を書いている仕事部屋は道路に面していて、駐車スペースの真上にある。だから、センタースタンドを掛け損なったり、ハンドルにぶら下げていた(と思われる)買い物袋を落とした様子も聞こえる。他のバイクやクルマの音は気にならないから、親として多少は神経が敏感になっているのかもしれない。
クロスカブを選んだのは娘自身だ。スーパーカブには好みの色がなく、ハンターカブは「自分にはまだ早い」というのがその見立てだった。新車より中古に憧れがあるとも言い、近所のショップで見つけた2年落ちの個体が我が家へやってきた。
今、女の子とスーパーカブにまつわる物語が話題になっている。漫画や小説に加えて、アニメでも放送中だ。娘はその主人公と同じ16歳の高校2年生だが、だからといってそれらを読んでも、見てもいない。2輪系の動画にもほとんど興味を示さず、それでもバイクに乗ることを決めたのは、家庭環境と自発的な何かがそうさせたのだと思う。
学校以外では、独りの時間をごく自然に楽しんでいる。クロスカブは、そういう日常にちょうどいいらしい。スクーターほど生活に密着しておらず、マニュアルのスポーツバイクほど存在が重過ぎない適度な軽さがある。これはアニメの中のスーパーカブやハンターカブもそうだ。いずれのカブも淡々とした日々の中に在る一方、望めばいつでもそこから抜け出せる扉の役割を果たしている。
カブに乗っているモトブロガーやユーチューバーと呼ばれる女の子達にもそれと似た空気を感じる。たまたまメディアを介して発信しているが、本質的には日常の一部やその延長線を切り取っているに過ぎず、影響力を持とうとか、優位に立とうとする意図は見られない。等身大の姿がそこにある。速い遅い、勝った負けた、カッコいいダサいと、常に誰かと、もしくはなにかと比べて一喜一憂していた我々の十代とは違い、ある種の成熟を感じさせる世代だ。
もっとも、こうしてすぐに世代論で括りたがること自体、古い世代の証に他ならない。数字や勢力でモノの価値をはかってきたのが我々で、なにかと言えば80年代を振り返り、今の時代のバイク離れを嘆くことがルーティンになっている。そして、余程のことがない限り、この凝り固まった価値観から脱することはできない。
かつては数の力で大きなうねりを作り出し、それが時代の象徴になってきた。昔ならブームが1つあれば1年はそれで持ち切りだったものだが、今はあふれる情報の中で100のバズリネタが1ケ月で消費されていく。
そんな中、彼女達はわざわざバイクを手にしたのだ。16歳になると免許取得が当たり前だった時代とは、そこが根本的に違う。「だって、みんな乗ってるから」は、「みんなファミコン持ってる」、「みんな塾に行ってる」を理由にしているのと同じで、大してなにも考えていない、単なる仲間意識が下地になっている。
ところが彼女達は誰に流されるわけでもなく、明確な意志でバイクのある生活を始めた。この差はとても大きく、80年代を生きてきた者より遥かに積極的に向き合っている。自分のスタイルを持っていると言ってもよく、それを表現するコンテンツとしてバイクを選んだのだ。
アニメ『スーパーカブ』の第7話に、こんなセリフがあった。
「無理だと思ったことはやらない方がいい。怖がりながらカブに乗ると、カブもこっちを怖がってシートから放り出したりする。乗りたい、走りたいって思って乗らないと走ってくれないようにできている」
とても的確で、地に足がつき、カブをファッションとして見ていないことが分かる。我々は妙な老婆心を出さず、お節介も焼かず、ただ黙って見ていればいい。