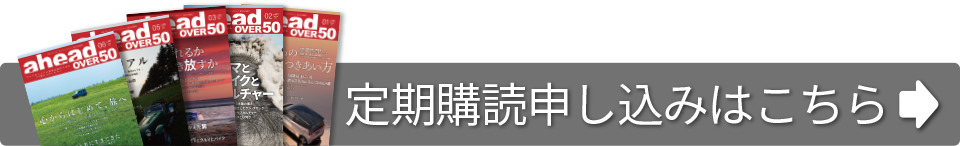SRが43年の歴史に幕を閉じる。工業製品でありながら温かみを感じさせるSRは、バイクに乗らない人にとっても気になる存在だったはず。
SRは言うまでもなくYAMAHAを代表する二輪車であり、文化的な匂いを感じさせる数少ない日本車でもある。
SRは、バイクがロックだけではなく、バラードも奏でることを証明してきた。

SR的な風景
多くの雑誌メディアで、大排気量の改造車やオフロードの過激な話ばかり書いているが、実は2010年型SR400を所有している。余計な改造はせずに、シートだけを台座から作るので有名な、「K&H社」の特注カラーにしている。
多くの昭和バイク乗りは、バイクというものに対して特別な「風景」を押し付けたがる。1100カタナや900ニンジャを持っていれば、公道レースに命をかける中年男の背中を劇画チックに自分に当てはめる。大型オフロードバイク、アフリカツインで林道に向かうものは、パリダカで砂漠を疾走している自分をイメージする。最新スーパースポーツで峠に向かうのなら、コーナーでヒザではなくヒジを擦りながらドリフトしている、マルケス兄をイメージしているかもしれない。
バカげた話ではあるが、それがいまだに昭和を引きずっているライダーのリアルのはずだ。
だが、今時の若者というのは全く違う「風景」の中を走っている。もっと正確に言うと、昭和バイク乗りのように共通の「風景」を持っていない。逆にSNSなどで自由な「風景」を発信していたりする。
昭和は昭和で楽しんでいるのだ、今どきのバイク乗りと無理に関わろうとは思わない。でも、そんな若者たちの「風景」をちょっとだけ知ってみたいと思ったのが、SR400を手に入れた理由のひとつだ。
そんなときにたまたま出会ったのが、「K&H社」のシート開発車両の役目を終え、隠居状態にあったSR400だった。
乗ってみて、まず最初に感じたことは、ただ乗るだけでは「何も物事が起きない」ことだ。単気筒独特の「味」があるなどと言われるが、私はそんなものを感じることは出来なかった。
私が今まで好んで乗ってきたバイクというのは、世界一速いエンジンが付いていたり、垂直の崖を登れるような性能であったりなど、ただ乗るだけで「何か事件が起きた」バイクばかりである。
だがノーマルのSR400というバイクは、速くもなく、ことさらに曲がるわけでもなく、乗りにくいわけでもなく、その逆に乗り易いわけでもない。1978年に設計されたまま43年も生き続けてきた、ただの中型バイクである。
世間ではSR400のことを「深い味わい」などと持ち上げることがある。16歳からオンオフ両刀遣いで、無数のバイクを知り尽くしてきた自負があるが、ノーマルSR400の味わいというものを上手く表現できない。
他人から、SRってそんなに良いのですかと聞かれることがあるが、私はいつも「とくに良いところはないです」と答える。そして「ただのバイクです」と付け加える。
ただし、ふらっと漁港の食堂で美味い魚を三味したくなったときや、紅葉の峠をノンビリ走りたいときなどに、SR400を走らせるとまるで違う「風景」が広がる。それを知ったとき、私は16歳からのバイクとの関係を強く反省した。
バイクの存在感がまるで自分の前に出てこない。主役はあくまでもその日の自分であり、朝から晩まで終始、ずっと脇役に徹している。主役を引き立たせ、物語の味を深める、まさに最強の「バイプレーヤー」なのだ。
「俺は世界最速だ」「俺は究極だ」「俺こそドリームマシン」だとか、四六時中バイクが自己主張してくることがゼロである。また昭和バイク乗りとのマウント合戦に巻き込まれることもなく、とても穏やかな休日を誰にも煩わされることなく過すことが出来る。
終わりを告げる鐘の音のように、SR400の限定ファイナルエディションが出た。足りないわけでもなく過ぎたるでもない、そんなバイクが今の時代にどれだけあるだろう。

SRがいなくなった未来
ホンダにはCBがあり、カワサキにはZがある。好みはあるにせよ、どちらも名機であることに異論はないだろう。いずれも伝統かつ革新であり、バイク史の転換点を作った歴史的車両だ。そしてどちらもメーカーを超えたブランドとして今も存在している。
いっぽう、2ストロークエンジンを主体としていたスズキとヤマハは、70年代の大排気量4ストローク、多気筒化の波に乗り遅れた。それでもスズキはGS750を作り出し、カタナや油冷エンジンへと継承していった。GSを軸としてスズキが語られる機会は少ないものの、GSXシリーズとして最新モデルにもその名称は受け継がれ、スズキの象徴的モデルとして在り続けている。
ヤマハはXSやXJで大排気量4ストローク多気筒化を果たしたものの、現時点でXJの称号は消え、XSの名前はかろうじて残っている。かろうじて、と前置きする理由は、ヤマハはXSRシリーズのモチーフをXSと公言しているが、私はそれを建前だと感じているからだ。XSRシリーズは、SRXのリベンジか、SRの後継として登場したように思える。いずれにせよSRという名前が大きすぎるがゆえに何らかのソフトランディングが必要だったのだろう。
ヤマハを象徴する代名詞となり、ブランドとなってきたのは特定車種ではなく、ハンドリングやデザイン(美しさ)といった、固有名詞でもなければ数値化もしにくい抽象的なものだ。あるいは先見性や革新性のあるコンセプトだろう。ロボットがバイクを運転するモトボット。ナイケンやトリシティのLMW。二輪二足走行という新概念を具現化したセロー。ビッグスクーターブームを引き起こしてカテゴリー化したマジェスティ。電動アシスト自転車という乗り物を発明したパス。そして、最高速追求のための水冷、大排気量、多気筒、ハイメカという先進技術が主流の70年代後半において、空冷単気筒OHC2バルブという目新しさのない構造をあえて用い、バイクを操る愉悦を純粋に体現したSRもそうだ。
先鋭を追求せず、シンプルな構造を不変としているからこそ改造の余地があり、ゆえに多様性が生まれる。完成された未完成とでもいうべきか。これはハーレーダビッドソンも同様だ。
だが、科学技術が日進月歩で進み、環境保護の声も高まるなか、バイクが不変でいられることは非常に困難だ。ハーレーは電動バイクのライブワイヤー、新開発の水冷エンジンを積んだアドベンチャーツアラーのパンアメリカを作り、変容を余儀なくされた。そしてヤマハはSRの生産を終了せざるをえなくなった。
CBやZほどではないにしろ、SRをヤマハの象徴と感じている人は少なくないだろう。なにしろ43年間にわたってその姿かたちと構造、走行性能をほぼ変えることなく作り続けてきたロングセラーであることは揺るぎない事実だ。SRの終焉を惜しむ人はやはり多く、最終型の予約注文数は6,000台を突破したそうだ。この数字は2017年から2020年までの4年間のSRの新車販売台数合計に匹敵するほどである。
SRがなくなったことで、ヤマハは象徴を失ってしまうのか。たしかにロングセラーモデルを失うことは企業にとって痛手で、SRだけでなくセローの生産終了もそのダメージを深くする。
しかし私はそうは思わない。むしろ〝不変であること〟から解き放たれることで、ヤマハらしさをもっと自由に具現化できるようになるのではないか。
なぜならヤマハは懐古主義的なものを創らない。それこそがヤマハらしさの主軸だと思うからだ。常に新しい価値観を創造し、かたちにしてきた。さらに加えて、美しくあることを信条としてきた。そうした思想と哲学はヤマハが作るほぼすべてのバイクに通じている。
たしかにSRはその象徴的存在であったし、キックスタート式の空冷単気筒という構造のバイクはヤマハのラインアップから消える。しかし構造的な特徴や魅力はともかく、コンセプトだけで見ればSRだけがヤマハの持ち味ではない。
これが大きな転換点となることはまちがいないだろう。しかしヤマハはこれをポジティブなスタート地点とすることができるメーカーであるし、そうなっていくと信じさせてくれるだけの実績がある。
そして生産終了によってSRの魅力が褪せることもない。43年間で生産されたSRは12万台以上だそうだ。現役の保有台数もさることながら、中古車の流通台数も多い。この世のSRすべてがなくなるわけではないのだ。企業経営として難題だろうが、ヤマハにはSRの純正部品供給を永劫継続してもらいたい。
SRを遺産とするのではなく、恒久的なブランドとして、そしていつまでも愛し続けられるバイクとして残してほしい。それはSRファンだけでなく、すべての旧車愛好者、いまは現行でもいずれ絶版車となるすべてのバイクオーナーの願いでもある。
SRは生産終了というかたちで、ヤマハだけでなくすべての車両メーカーに新たな課題を作ったのだ。

1978年

1979年

1983年

1985年

2001年

2010年

2018年

2021年