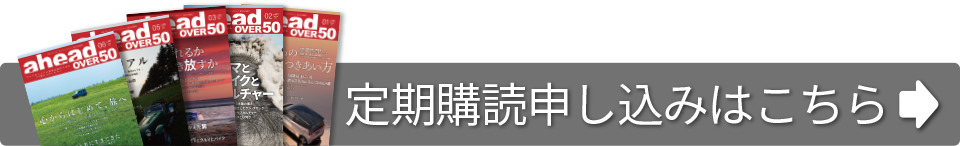2020年1月から「セロー250ファイナルエディション」の発売が始まっている。これをもって、セロー225時代からの35年という歴史に終止符が打たれることになった。
一抹の寂しさはあるものの、長年続いた連載漫画が無理な延命なく大団円を迎えたような、そんな爽やかさもある。
セローでバイクの世界へ足を踏み入れ、ライディングの楽しさを知った人は多い。年齢を経て再びセローに戻った人も、酸いも甘いも嚙み分けた末にセローの価値に気づいた人もいるだろう。大半のモデルがひっそりとフェードアウトしていく中、ファイナルエディションと銘打った特別仕様が送り出されること自体珍しい。これまでのセローファンと、これから手にする新しいユーザーへのヤマハの感謝がそこに見て取れる。
223ccだった排気量が249ccになり、やがてキャブレターがインジェクションになった。細かく見れば8つの世代に分けられるが、その間外観が刷新されたのはいちどしかない。時代や環境の変化に合わせて必要な時に必要な改良だけが加えられ、消費をうながすためだけのモデルチェンジも、スクラップ&ビルドもよしとしなかった。意味のある進化を一歩ずつ積み重ねることを許された稀有なモデルと言える。
セローは扱いやすいエントリーモデルというポジショニングを得ていて、それはまったくその通りなのだが、筋金の入った孤高の存在でもある。
というのも、初代モデルが登場した’85年という時代はオンロードもオフロードもレーサーレプリカが花形だった。なによりヤマハ自身がその最前線に立ち、TZR250やDT200Rをマーケットに送り込んで空前のバイクブームとレースブームをけん引。誰もが浮き足だっていた一方で、セローはその雰囲気に流されることなく、ずっと先を見据えて開発されていたからだ。
スピードという単能を追求したマシンは即効性の高い魅力に溢れるが、いつか限られたステージと限られたライダーにしか歓びをもたらさなくなる。それを危惧したエンジニアは、華々しいところがなくともあらゆる道を走ることができて、どんな使い方にも応えてくれる多用途なバイクが必要になることを確信していた。『走る・曲がる・止まる』というライディングの基本性能に『転ぶ(もしくは転べる)』という要素を加え、2輪2足でどこまでも突き進んでいける「マウンテントレール」というコンセプトに行き着いたのである。新しいカテゴリーを切り開くのは、革新の技術や斬新なデザインとは限らない。
より速く走れるように、より高く跳べるように、よりスタイリッシュな外装に。そうした声は、ユーザーはもとよりヤマハ社内からも幾度となく上がったに違いないが、豪華なコース料理に仕立てることも化学調味料に頼ることもなく、素材の味を愚直に守ってきたと言える。ニューモデルが出ては消えていくバイクバブルを横目に、セローはただの一度もブレたことがなく、だからこそライダーの拠りどころで在り続けたのだ。
今回、あらためてセローに乗った。久しぶりだったがそれをまったく感じさせることなく、すぐに身体に馴染んでくる。エンジンを始動させ、ギヤをニュートラルから1速に踏み込むと、コクッでもスッでもなく、カチョンと送り込まれる。特別滑らかなでもなければ、精度の高さを伝えてくるわけでもないものの、不都合はなにもない。こちらがひとつ操作すれば、そっくりそのままきちんとひとつ反応。電子デバイスの類はなにひとつ備えていないため、勝手にもてなされることも、先回りされることもない対等な関係がちょうどいいのだ。
スロットル開け始めのレスポンスは、おそらく多くの人がイメージするよりずっと鋭い。トルクの盛り上がりを全身で感じながら街中をスイスイと駆け抜け、ひと度林道に入れば力強いトラクションを自在に引き出すことができる。
そんな風に必要十分なスペックが与えられつつも、完全ではないところがポイントだ。カスタムやチューニングの度合いによってツアラーにもエンデューロマシンにも変化する。ユーザー自身の理想を盛り込める余白が最終形の今も残されているのだ。
決して完璧ではないがゆえの、朴訥とした愛おしさがセローにはある。80年代に、ヤマハはバイクの魅力を伝えるキャッチコピーとして「人間に一番近い乗りもの」と掲げていた。それに最も近いのが、他でもなくセローだと思う。セローにまたがるといつも陽だまりのような暖かさを感じるのである。

ヤマハ SEROW250 FINAL EDITION
エンジン:空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ単気筒
総排気量:249cc
最高出力:14kW(20ps)/ 7,500rpm
最大トルク:20Nm(2.1kgm)/ 6,000rpm
車両重量:133kg