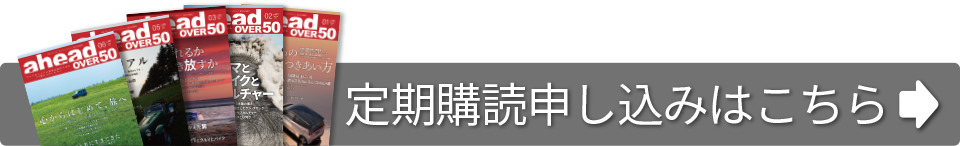今や日本を代表する文化と言える漫画は、時に社会現象を引き起こし、読む人の人生に大きな影響を与えることがある。
クルマやバイクについても、古くは「サーキットの狼」がスーパーカーブームを創り、「あいつとララバイ」や「頭文字D」に登場したZ2やAE86が、旧車の中古車価格を高騰させた。そして漫画で表現されたクルマやバイクの奥深さにインスパイアされ、バイブルのように何度も読み返し、その世界を大切にしている人がいる。

これはもうありとあらゆるところで表明し続けてきてることなのだけど、自動車ライターとしての僕のルーツは間違いなく『サーキットの狼』にある。1976年頃からの数年間、まるで熱病のように少年達をヒートアップさせた未曾有のスーパーカー・ブームを生み出したのが、まさしくコレだからだ。
1975年から1979年にかけて週刊少年ジャンプに連載された池沢さとし(現:池沢速人師)さん作のこの漫画は、主人公であるロータス・ヨーロッパを駆る風吹裕矢が、一匹狼の走り屋からF1ドライバーへと成長していくまでの、いわばグローイングアップ・ストーリーだ。もちろんストーリーそのものにもワクワクさせられたが、何といっても僕達の興味を惹きまくったのは、作中に登場するクルマ達だった。ロータス、ポルシェ、フェラーリ、ランボルギーニ、デ・トマソ、マセラティ……と並べはじめたらキリがない。そうしたクルマ達が、とにかくクルマが大好きで周囲にクルマ仲間もたくさんいた作者の経験を元に描かれる乗り味やパフォーマンスを僕達に伝えながら、首都高を、箱根から伊豆を、流石島を、そしてサーキットを縦横無尽にカッ飛んでいたのだ。それまでカローラやサニーしか知らずに一番偉いクルマはクラウンだと思い込んでたようなハナタレ小僧達に、世界にはこんなにもカッコいいクルマがあるんだということを、いや、自動車というのはカッコイイものなんだということを、みっちりと教えてくれた。いつかこういうクルマに乗れる男になりたい、という夢を与えてくれた。そんなふうに感じていた〝元〟少年が、ある世代には数え切れないほどいるはずだ。
僕に関していうならば、自分の所有物としてじゃなくて取材対象の預かり物としてだが、作中に出てくる代表的な車種にはひととおり試乗させていただき、原稿にも収めてきている。おかげでクルマへの興味はさらに広がり、ずっと離れられないままだ。
そして僕のiPadの中には、電子書籍で今も全巻が勢揃いしている。

バイク好きのahead読者なら、誰でもわかるマンガで恐縮だが、僕はこの作品に出会ってなければバイクには乗っていないと断言する。「バリバリ伝説」は、’83年から’91年まで長期に渡って少年マガジンに連載されていたが、リアルタイムでは読んでいない。’81年生まれの僕は、連載終了時点でも10歳だ。当然バイクブームも知らない世代なのである。
そんな僕が、初めてバイクに興味を持ったのは’95年の14歳、中学2年生の頃だと記憶している。当時、近所にCBR400RRが停めてあり、ブルーメタリックに塗られ、マフラーとテールがカチ上がった、いかにも横浜仕様なバイクが気になった。バイクをもっと知りたい、乗ってみたい、というスピードへの憧れが芽生え、影響を受けたんだと思う。そんな折、古本屋でバリバリ伝説全38巻のセットを見つけてしまい、勢い余って購入したのがバリ伝との出会いだった。
「バリバリ伝説」は、物語としては正統派というか、ストレートなサクセスストーリーだけれど、それがイイ。純粋に速さを求め、純粋にカッコよさを求める。今回この原稿を書くにあたって、改めて読み返してみたら、あの頃と同じように止まらなくなってしまった。
しかし、よく考えてみると、当時のバイクブームを知らない、連載中でもないバイクマンガに中学生の自分はどうして夢中になれたのだろうか。その答えは本誌の神尾と話しているときにピン! ときた。
「ビートルズと同じかもしれない」
当時の背景を知らなくても、心に響く物語や音楽、映画と同じで、イイものは、時代や世代を飛び越えて人を夢中にさせるのだ。
最近は、あの頃のように峠に行くことはめっきり減ってしまったけれど、今でも、コーナーに差し掛かれば「カメッ」と、心の中で叫んで、三点支持コーナーリングをイメージしたり、タイヤがグリップしなければ、「カレーライスにして食っちまうぞ」と独り言を言っている。さすがにガードレールキックターンはやらないけれど、僕のバイクライフはいつだって〝GUN BOY〟が原点なんだ。

クルマやバイク、カメラや時計。「男の趣味」と言われるモノたちは、どうしてちょっと古い方が〝らしく〟見えるのだろう? キーをひねり、フューエルポンプがコチチ……と響く音を確認してから、さらにもう一段これをひねる。クランキングの音に合わせ軽くアクセルを踏み込めば、咳き込むような初爆が起きて、ほどなく〝ヴァアーン!〟とエンジンに火が入る。うまく掛かったときはニンマリ。カブり気味のときはコッチも「うーん…」と顔を曇らせる。こうした儀式を必要とするクラシックカーが、当時高校生だった自分には、誰にでも簡単に動かせる現代の便利なクルマたちよりもずっと特別に思えた。
そしてそんなクルマ人生の〝初爆〟を、「GTroman」は僕に与えてくれた。
基本的に一話完結のショートストーリー。細いペンタッチが描く西風作品のクルマと登場人物たちは、しかし抜群に生き生きとしていた。ちょっと不良っぽかったり、気弱だったり。ウンチクばかりで走りはからきしだったり、逆に走り以外はてんでダメだったり。登場する主人公の誰もが本音で生きていて、何よりクルマが大好きなのだ。
多感な時期にGTロマンと出会った僕は、全11巻をアッという間に読破して、「DEADEND STREET」や「CROSS ROAD」といったアナザーストーリーも全て手に入れた。何をやっても失敗ばかりの主人公が、ミニのレースと共に大人へと成長して行く「PITZ START」は最高傑作だ。
西風のマンガには、かつて僕たちが暗黙の了解と共に繰り広げていたクルマの楽しみ方が全部詰まっている。クルマが移動の手段ではなく〝相棒〟であることを当然のことのように望む不良たちのロマンがここに描かれている。クルマをぶっ飛ばす場所が峠からサーキットへと移り変わった今でも、僕はやっぱり峠が好きで、走り終えた先に「カフェROMAN」があればいいのになと、今でも思う。

「バイクは不良の乗り物」 僕が学生だった頃はそんな認識が一般的だった。そのせいかマンガの中でもバイクと不良はワンセットとして扱われていることが多かった。しかし昔から不良やツッパリ、暴走族といった存在が嫌いだった僕にとっては、その世界観自体が馴染めなかった。そもそも自分はどこにでもいる一般的な高校生。無断で授業をサボることもなければ反抗的な態度で人とケンカをすることもなかった。だから不良が主人公のマンガには没頭できなかったのだ。
ところが「ペリカンロード」の主人公は、休み時間も参考書とにらめっこしているガリ勉で根暗な高校生。そんな彼が親に内緒で原付免許を取り「青春」を求めてバイクに乗るという二重生活を始める。その設定に興味を引かれた。話の中には家族や学校の先生、友人などが登場し、真っ当な高校生活を送りながらもバイクにハマっていく主人公の様子が描かれていた。普通の家庭で育ち、毎日学校へ行き、同級生と部活でワイワイやるという〝ありきたりの高校生活〟を送っていた自分には、特殊な設定のマンガよりも気持ちがリンクする部分が多かった。
もちろん物語としての演出は多々ある。主人公は暴走族の抗争や仲間内での三角関係、後輩の存在など本人の意思とは関係なくさまざまな厄介事に巻き込まれていく。その中で憧れのライダーと出会い、追いかけ、しかし届かない。そして悪夢のような一夜が過ぎると再び今までと同じ日常が始まる。その切り替わり方が自分の生活とどこか似ているように感じられた。
そして最終話は日常のワンシーンで終わる。ページをめくれば次の話が始まるかのように。いや、きっとこの話は終わっていない。彼らの人生は自分と並行して続いているはず。今も〝あの頃の気持を持ち続けたまま〟バイクに乗っていて、これからも一緒に時を刻んでいく。そんな想いを抱かせてくれるのだ。僕にとっての「ペリカンロード」は、バイクライフを始めた頃の思い出と夢が詰まった日記のようなストーリーなのである。

20年以上前の旧車が湾岸線を300キロオーバーで駆け抜けるという、「湾岸ミッドナイト」の世界は、免許を取る前のガキのくせに、漫画の世界だからと、どこか冷めた目で見ていた。ストーリーには心惹かれるけれど、さすがにそれはないだろうと。
だが、Vシネマとしてその世界が再構築された時、僕の興味はかなりそそられた。たしか東京中日スポーツ新聞の片隅に、小さく書かれていた紹介記事だったと思うが、「600馬力、300キロオーバーが現実に」みたいな話である。いま考えてみれば、それだってウソだったのかもしれない。けれども、現実にそれに近いクルマをつくり、実際に走らせたというVシネマ版の湾岸ミッドナイトは、リアルを求めていた僕に衝撃を与えてくれた。主人公は本誌執筆陣の大鶴義丹さんだから、こう書くのはファンレターのようで気恥ずかしいが……。
走りや音は現実におそらく近い状況で撮影がされたこともあり、とにかくリアル。いまじゃお縄を頂戴しそうなレベルの事を平然とやっていた時代が懐かしい。あおり運転だの、ドライブレコーダーだのと、窮屈な現代とはエライ違いだ。時にはクルマをクラッシュさせ、それを直していくという流れが見られたことも心に突き刺さった。愛車を大切にしようという姿勢を学べたのかもしれない。同じようなクラッシュを、後に僕も現実の世界で引き起こしてしまうのだが、バイトを重ねて何とかして愛車を直してやろうとしたのも、このVシネマのおかげだったのかもしれない。
Vシネマ版の湾岸ミッドナイトに心惹かれたのはそれだけじゃない。漫画とは違うオリジナルストーリーが展開されていたこともあった。主人公のアキオが社会人となり、様々な困難を乗り越えて、最終的にはチューナーになり、さらにプロドライバーにも誘われるが、最後は断って湾岸に戻るというストーリーも良かった。メジャーが正義じゃない。アウトローで居続けることもまた正義。これまた現代じゃ許されない終わり方が懐かしい。

「ライダーズラプソディ」は、80年代のMr.Bike誌に不定期で掲載された広井てつお氏の短編漫画を1冊にまとめたものである。レーサーレプリカが全盛だった当時、バイク雑誌に掲載される漫画でありながら、派手なバトルが繰り広げられる訳でもなければ、凄い才能を持ったヒーローが出てくることもない。それにハードボイルドと呼べるようなシーンもほとんどなかった。しかし創作の物語よりも、作者自身の体験を漫画化しているものが多かったので、バイクに乗っている人であれば共感できる言葉や場面が随所に散りばめられていたのだ。
中でも広井氏の出身地である岡山県を舞台にした「西大寺ぶるうす」と、その続編は、中国地方ならではの気骨さと暖かさが滲み出ているところが好きで何度も読み返した。東京での生活を一時中断して帰郷した際、仕事もせずにバイクのレストアに没頭する話や、高校生の頃に無免許運転で母親を泣かせたこと、バイクに乗り始めて自由を手に入れた開放感と同時に警察に対する反発心が芽生えたくだりなど、自分の周りで起きていたようなことばかりが描かれている。
また仲間とアメリカをバイクで横断した実話に基づく「ゲッティツオール」は、先住民族への差別や日本人に対する嫌悪、銃社会などのダークサイドな部分と、アメリカ大陸の桁外れの広大さやアメリカ人の包容力と逞しさが伝わって来た。良いことであれ悪いことであれ、どんなことも包み隠さずバイクを通して漫画にしてしまう氏の懐の深さからくる純粋さが「ライダーズラプソディ」には、詰まっているように思う。
今年の夏で広井てつお氏が他界して丸12年となる。しかし今でも彼の遺した絵やセリフは、バイク乗りの気持ちに寄り添い、人として大切なものは何かを訴えかけて来る。インターネットで作品の一部が閲覧できるので、興味のある方は、「広井てつおのHP」を検索してみてほしい。〝広井てつおのマンガ〟を読むと、あの頃の懐かしい空気に包まれて、少しだけやさしい気持ちになれるはずだ。