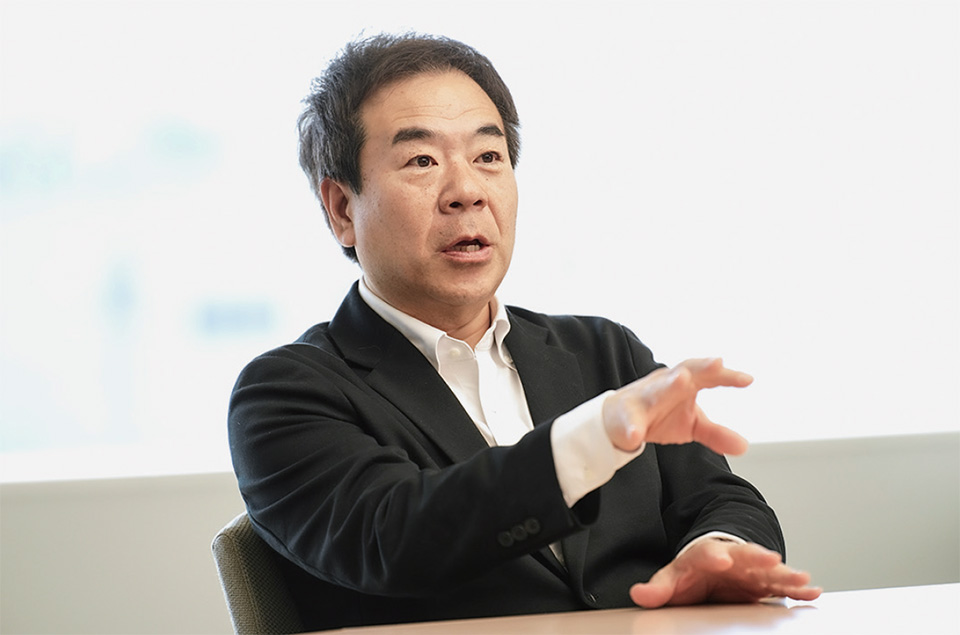ヘッドランプはただ「照らす」だけでなく、センサーなどによってAD/ADAS(自動運転と先進運転支援)を実現するために必要不可欠な役割を担うようになってきている。
ヘッドランプの変遷、これからの進化について、110年を超える歴史を持つヘッドランプメーカーの小糸製作所を訪ね、専務執行役員 技術本部長の勝田隆之氏にお話を伺った。
110年の歴史がある小糸製作所
岡崎五朗(以下、岡崎)_CES(コンシューマー・エレクトロニクス・ショー)ではお世話になりました。まさか勝田さんとラスベガスで会えるとは思っていなかったので嬉しかったなぁ。先代レクサスRXのチーフエンジニアをされていたとき以来ですから、かれこれ10年ぶりぐらいですかね。
勝田隆之(以下、勝田)_そうですね。その節は大変お世話になりました。で、なぜ小糸製作所がCESなんだという点ですが、うちがヘッドランプの会社だというのは皆さんご存じだと思うんです。でも実はそれ以外のこともやってるし、ヘッドランプそのものも大きく進化しているんだよということをアピールするのが、ここ数年、CESに連続出展している狙いです。
岡崎_たしかに興味深い展示がいろいろあって、これは改めて話をしっかり聞かなきゃということで、今回のインタビューをお願いした次第です。
勝田_ありがとうございます。小糸製作所には110年もの歴史があるんです。元々レンズの国産化から始まって、当初は鉄道用の照明が主な事業でしたが、モータリゼーションの進展とともに自動車用ヘッドランプにも進出し、現在に至っているわけです。技術面でも、シールドビーム、ハロゲン、HID、そして現在のLEDへと時代とともに大きく進化しています。ということで、小糸製作所をひと言で表現すれば、「光を扱うプロ集団」となります。
岡崎_なるほど。暗い夜道を照らすのも光ですが、それ以外の目に見えない光もあるわけで、最近は赤外線レーザーのような目に見えない光を使ったLiDARの開発に取り組んでいるのも自然な流れなんですね。
夜道を照らす光から、見えない光へ
勝田_自動車は100年に1度の変革期なんて言われていますが、そんなことを言われてからもう10年が経ち、残り90年しかないぞ!と感じております。そういった状況の中、今までとは違うメリットがあるものを出していかなければいけない。我々は光で何が出来るだろうと考えた結果、ドライバーサポート、センシングサポート、コミュニケーションサポートの3つを軸に設定しました。
岡崎_まさにヘッドランプメーカーからハイテク企業への変貌ですね。とくにLiDARは今後発展するAD/ADAS(自動運転と先進運転支援)には欠かせない技術になりますから。この部分に関しては後ほど改めてお聞きするとして、まずは従来の「暗い夜道を明るく照らす機能」としてのヘッドランプについて聞かせてください。この分野でも最近大きなブレークスルーが起こりつつありますよね。
勝田_はい。デザイン面では、規格サイズの丸形から始まり、異形ヘッドランプが登場し、最近ではより薄型なものや光り方に特徴を持たせたものまで登場し、車両デザインとの統合という流れがトレンドになってきています。加えて、ADB(アダプティブドライビングビームの略、ハイビーム点灯時に配光を制御して対向車や前走車には眩しさを与えないシステム)のような、夜間の見やすさをキープしながら他者に配慮するランプも増えてきました。
地域ごとに異なる配光の好み
岡崎_ADBは日本や欧州では比較的普及が進んでいますが、アメリカでは最近ようやくマーケットに入り始めたそうですね。何か理由があるんでしょうか?
勝田_地域ごとに配光の好みやルールが違うからなんです。基本的にはヨーロッパ型とアメリカ型の2つの配光があって、ヨーロッパでは遠くまで見えて、どこを照らしているかがハッキリと分かるシャープな配光が好まれます。それに対しアメリカだとこの配光ではカットラインの上下で途切れて標識の上半分が見えないなどの意見があって、照らしている部分の境界線がボヤっとした配光が好まれるんです。
岡崎_夜のアウトバーンを時速200キロで走るにはパキッとしたライトがいいけれど…みたいな交通環境の違いが、好まれる配光にも出ているんですね。
勝田_ええ。そういった背景もあって、ヨーロッパとアメリカでは、ヘッドランプに対するレギュレーションは似ているけど、求められる配光特性が違うんです。ADBはヨーロッパ配光から始まっていて、当然シャープな配光がベースにあります。ところがそれをそのままアメリカに持っていくと明暗が出過ぎて、ドライバーが疲れると評価されてしまう。一方で、決められた明るさを数字で保証しなければならないため、その塩梅を作り込んでいくのにかなり苦労しました。
岡崎_なるほど。僕のクルマにはADBが付いていて、あの便利さと安心感を一度知ってしまったらもう戻れない。それほど優れた技術だと感じているのですが、世界展開となるといろいろと難しいことがあるんですね。
勝田_はい。一度体験していただければ良さが分かるはずですし、安全性に寄与するというエビデンスもでています。今後はさらにコストを下げて、多くの車種に普及させていきたいと思っています。
岡崎_ヘッドランプはクルマの目としてデザイン上も重要ですし、小型化すれば空力やボディ設計的にも有利になる、そして安全性を高める上でもとても重要。ヘッドランプの重要性は今後高まる一方だと感じました。ところで、こうしてヘッドランプを時代ごとに並べてみると、その進化がより実感できますね。
勝田_まず現状で言えば、LEDになった時点で発熱が少なくなって、発光効率も良くなっています。効率の伸び率は最近落ち着いていますが、まだ詰め代はあるので、さらなる省電力化や小型化も狙えます。LEDの次はレーザーだと言われていますが発熱の問題もありますし、ここまでLEDのヘッドランプが普及しているとコスト的にも有利なので、まだまだLEDで進化していくと思います。
岡崎_今って新車で販売されているクルマのうち、どれくらいの割合がLEDなんですか?
勝田_むしろハロゲンで残っているのがエントリーモデルの廉価版グレードのみですね。HIDもほとんど無くなってしまいましたし、現状は8割超がLEDです。先に話していたADBはまだ1割程度ですが、これは高級価格帯のモデルにのみ採用されていることが多いのも背景にあります。今はエントリーモデルでもカメラが付いていて、ADBはそこからの情報を基に制御しているので、今後もっと普及できるはずです。
AD/ADASを支えるLiDAR
岡崎_CESでは大々的にLiDARの展示をしていましたね。人は目だけで運転している。だからカメラだけで自動運転ができるのだと主張する人もいますが、僕はAD/ADASの進化においてLiDARは絶対に必要だと思っていますし、国内の自動車メーカーのエンジニアと話していても、ほぼ全員がレベル3以上の自動運転をするならカメラだけでは無理だと言います。改めてLiDARの役割と必要性を教えてください。
勝田_カメラだけで自動運転が出来ると断言する人もたしかにいますし、もしかしたら将来的には出来るビジョンがあるかもしれません。でも現状のカメラの性能やAIの能力を考えると、現実的には難しいです。たとえば、カメラからの情報は2次元画像なので、重なってしまうとどちらが手前かわかりません。でも赤外線レーザーを使ってスキャンするLiDARなら距離まで測定できるので、どちらが手前にいるかを判別できるんです。運転支援システムはバックソナーがミリ波になって、そこにカメラが付いてと様々なセンサーがリンクして現在のシステムまで進化しました。今後も各種センサーを組み合わせて認識性能を向上させ、より安全にしていく方向性になると考えています。
岡崎_カメラだけでは補いきれない部分があるから、LiDARを始めとした各種センサーをリンクさせる必要があるんですね。
勝田_その通りです。実際、海外の自動車メーカーを含め、LiDARが必要ないと言っているところはほとんどないです。
岡崎_テスラと一部の中国メーカーぐらいですね。
勝田_機能安全を担保するのであれば、画像処理とAIの組み合わせだけではなく、しっかりと距離が測れるLiDARを組み合わせるのが世界のトレンドです。
小糸は光学のスペシャリストになれる環境
岡崎_今回お話を聞いて、ヘッドランプの進化からLiDARまで、小糸さんがやっていることは今後のモビリティ社会にとってとても重要なことだと思いました。なので若い人にもぜひ注目してほしい会社なんですけど、勝田さん的に『小糸はこうだ!』みたいなアピールポイントはありますか?
勝田_わかりやすい点で言えば、まずカタログの表紙になる(笑)。もちろん、街中で自分の仕事の成果を頻繁に目にするのも達成感を感じる部分です。うちの商品は複数の自動車メーカーさんに供給していますし、担当エンジニアも色々な会社とつきあうことで経験を積んでいるので、満足感とともに仕事に向き合っています。
岡崎_あ、あれ俺がやったヤツだ、と思えるのってたしかに嬉しいでしょうね。
勝田_あとLiDARは色々な使い道がありまして、クルマだけでなく、インフラ側に設置しようという動きもあります。ITSのシステムに入れ込んで、『ブラインドコーナーの先から車両が来るのを教える』といったような危険予知の仕組みを作ろうという取り組みもあります。光学で様々な可能性に挑戦できるスペシャリストになれる環境だと言えますね。
株式会社小糸製作所
専務執行役員 技術本部長 勝田隆之/ Takayuki Katuda
1985年トヨタ自動車株式会社入社。2006年レクサスセンターのチーフエンジニアに任命され、レクサスRXの開発などを指揮する。2016年株式会社小糸製作所入社。顧問、常務執行役員等を歴任し、現在は同社の専務執行役員技術本部長を務める。
岡崎五朗/Goro Okazaki
1966年生まれ。モータージャーナリスト。青山学院大学理工学部に在学中から執筆活動を開始し、数多くの雑誌やウェブサイト『Carview』などで活躍中。現在、テレビ神奈川にて自動車情報番組 『クルマでいこう!』に出演中。